
▼この記事でわかること
・抵当権の超基本
・被担保債権とは
・抵当権の付従性の緩和とは
・抵当権の随伴性とは
・登記に勝る強力な随伴性
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

抵当権の基本とその性質
抵当権とは、担保物権の一種で、目的物である不動産の引渡しを受けずに優先弁済権を確保する約定担保物権です。(約定担保物権とは契約等で設定する担保物権のこと)
これだとカタすぎてわかりづらいですよね。
もう少しわかりやすく解説するとこうなります。
抵当権とは、金融機関などが融資(お金を貸すこと)を行う際、その融資したお金が回収できない場合の担保(要するにリスクの担保)として不動産を確保して、実際にお金が回収できないような事態になったときは、強制的にその不動産を競売に出して(売っぱらって)、他の債権者に優先して(優先的に)その売却金からお金を回収できる権利です。
つまり、その権利(抵当権)を、お金を貸す側(金融機関など)とお金を借りる側が契約等で約束(約定)して設定する、ということです。
そして、お金を貸した側が抵当権者、お金を借りた側が抵当権設定者となります。
抵当権者 抵当権設定者
↓ 融資 ↓
金を貸す側 → 金を借りる側
(銀行等) (個人・法人等)
民法の条文はこちらです。
(抵当権の内容)
民法369条
1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
この民法369条の条文だと表現がカタいので理解しづらいですが、抵当権のポイントは「占有を移転しないで」と「他の債権者に先立って」です。
この2点が債権者にとって非常に都合が良く、現実の金融の世界でもっとも頻繁に利用される担保物権が抵当権である理由です。
(この点については「【抵当権の超基本】その特徴と意味とは?抵当権の強さの理由とは?一般財産って何?初学者にもわかりやすく解説!」でわかりやすく解説していますのでご参照ください)
また、抵当権は目的物の占有を伴わないので、登記という形でその権利を公示することになります。
これはどういう意味なのか、わかりやすく具体的に解説するとこうです。
例えば、Bさんに融資したA金融機関がB所有の不動産に抵当権を設定します。
するとA金融機関は抵当権者になります。
しかし、抵当権者であるA金融機関は、B所有の不動産を担保として確保していますが、B所有の不動産を実際に占有して利用するのはBさんです。
じゃあ「B所有の不動産に抵当権が付いていて、その抵当権者はA金融機関だ」ということをどうやって証明するのか?というと、それが抵当権の登記になります。
したがって、抵当権は登記という形でその権利の有無を公示(公に証明)しているのです。
また、抵当権が登記という形でその権利の有無を公示(公に証明)しているということは、登記(または登録)という形で公示している物でないと抵当権は設定できないということです。
原則として、抵当権は不動産に対して設定するものです。
民法上「動産」「債権」に設定することはできません。
この点はご注意ください。
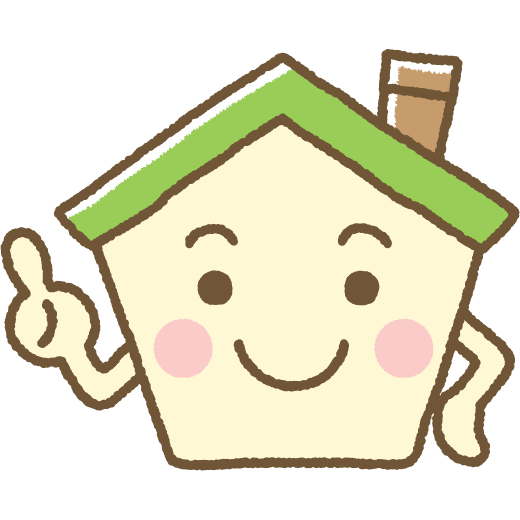
なお、民法369条2項にあるように、地上権・永小作権に抵当権を設定することはできます。
しかし、賃借権には抵当権を設定することはできません。
なぜなら、地上権・永小作権は物権ですが、賃借権は債権だからです。
被担保債権
抵当権は、被担保債権を担保するための物権です。
被担保債権とは、先述の金融機関の例で言うと、A金融機関が融資した相手方Bに対する「貸した金返せ」という貸金債権のことです。
つまり、その抵当権(担保物権)を設定する原因となっている債権のことです。
抵当権者 抵当権設定者
↓ 融資 ↓
A金融機関 → B
(貸す側) ↑ (借りる側)
被担保債権
また「抵当権(担保物権)を設定する原因となっている債権」が被担保債権ということは、抵当権は被担保債権の存在を前提としているということになります。
これを付従性といいます。
付従性の緩和
抵当権は被担保債権の存在が前提です。(付従性)
したがって、被担保債権が現に存在して初めて抵当権は成り立ちます。
しかし、抵当権は契約等で設定する(約定)担保物権ということもあり、実務上の要請から、抵当権成立時の付従性はかなり緩和されています。
付従性がかなり緩和されているということは、抵当権成立時には現に被担保債権が存在していなくとも、抵当権を設定できるということです。
具体例を挙げると、次のような債権を被担保債権として、抵当権を設定することができます。
・物の引渡し請求権のような非金銭債権(「金払え」じゃない債権)
・将来発生する金銭債権(未来の「金払え」)
上記2つのうち、重要なのは「将来発生する金銭債権」です。
これには次のようなものがあります。
【金銭消費貸借予約上の債権】
まさに先述の金融機関の例がこれです。
A金融機関がB所有の不動産に抵当権を設定する時、まだ実際の融資は行われていません。
抵当権の設定をしてから実際の融資が行われます。
これは付従性が緩和されているからこそできることなのです。
【保証人の求償債権】
これは、保証人が保証債務を履行した場合の、主債務者への求償債権のことです。
つまり、将来、保証人が保証債務を履行した場合の主債務者への求償債権に抵当権を設定できるということです。
【賃貸借契約による保証金の返還請求権】
これは、賃借人が入居時に差し入れた保証金についての、賃借人(借主)の賃貸人(貸主・オーナー)に対する「将来の退去時の(保証金)返還請求権」に抵当権を設定できるということです。
補足
付従性の緩和は、約定担保物権(抵当権と質権)に特有の話です。
法定担保物権には、付従性の緩和というものはありません。
法定担保物権とは、その担保物権の発生原因が法律によって定められていて、その原因が発生すると法律の定めによって自動的に成立する担保物権です。
法定担保物権には留置権や先取特権があります。留置権や先取特権につきましては、また別途改めて解説します。
抵当権の随伴性
被担保債権(その抵当権を設定する原因となっている債権)を担保するための抵当権は、被担保債権の存在を前提に成り立っています。
これは抵当権の付従性という性質によるものです。
そして、抵当権には付従性とともに、随伴性という性質もあります。
まずは事例をご覧ください。
事例1
AはBに500万円を融資し、その債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定した。その後、AはCにその500万円の貸金債権(被担保債権)を譲渡した。
まず、この事例1の状況を確認します。
AはBに500万円を貸し付けました。
そして、AはBに対する「500万円返せ」という債権を担保するために、B所有の不動産に抵当権を設定しました。
このときの、AのBに対する「500万円返せ」という債権が被担保債権になります。
そして、AはBに対する「500万円返せ」という債権、すなわち被担保債権をCに譲渡しました。(債権譲渡)
これが事例1の状況です。
さて、ここからが本題です。
この事例1で、AがCに被担保債権を譲渡したことにより、B所有の不動産に設定した抵当権の行方はどうなるのでしょうか?
結論。
抵当権は被担保債権に伴ってCに移転します。
したがいまして、B所有の不動産の抵当権者はCになります。(Bは抵当権設定者)
[被担保債権譲渡前]
債権者
(抵当権者)
A
抵当権⇨↙︎ ↘︎⇦被担保債権
B所有 B
不動産 債務者
(抵当権設定者)
[被担保債権譲渡後]
債権者
(抵当権者)
C
抵当権⇨↙︎ ↘︎⇦被担保債権
B所有 B
不動産 債務者
(抵当権設定者)
抵当権は、被担保債権が移転すると、それに伴って移転します。
つまり、抵当権は被担保債権にくっ付いていくということです。
これが随伴性です。
これは、言ってみればコナミのシューティングゲーム『グラディウス』の「オプション」みたいな感じですかね(笑)。
つまり、ビックバイパーが被担保債権、オプションが抵当権で、ビックバイパー(被担保債権)にくっ付いていくオプション(抵当権)には随伴性がある、みたいな。
グラディウスを知らない方は訳わからないですよね(笑)。
失礼しました。
登記に勝る強力な随伴性
抵当権の随伴性という性質は、グラディウスよりもっとわかりやすく言えば「被担保債権という王様に家来の抵当権がくっ付いていく」ようなものです。
そして、この抵当権の随伴性は、非常に強力な性質となっています。
どういうことかと言いますと、なんと!
随伴性が登記に勝るのです。

抵当権は不動産と同じように、登記というルールでその権利の有無を公示・証明し、対抗力を備えます。
つまり、抵当権も登記をすることにより法律で保護されるということです。
登記の力は強力です。
それは不動産の二重譲渡の問題などを見れば一目瞭然です。
(これについての詳しい解説は「【不動産登記の基本】二重譲渡~登記は早い者勝ち/3つの登記請求権と登記引取請求権とは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
ところが、抵当権の場合、抵当権の登記よりも、抵当権の随伴性が勝ってしまう!のです。
それでは、ここからは抵当権の随伴性について、事例と共に解説して参ります。
事例2
AはBに500万円を融資し、その債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、AはCにその500万円の貸金債権(被担保債権)を譲渡し、AからCへ抵当権移転の登記をしたが、債権譲渡についての通知は行なっていなかった。それからAは、その500万円の貸金債権をDへ二重譲渡し、その債権譲渡についての通知を行なったが、抵当権移転の登記はしていなかった。
登場人物が増えて状況が少し複雑になってきましたので、まずはこの事例2の状況を整理します。
この事例2では、まずAがBに500万円を融資して、その貸金債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定しました。
それからAは、その被担保債権をCとDの2人に二重譲渡し、Cの方は抵当権の登記はあるが確定日付のある債権譲渡の通知はなし、Dの方は抵当権はないが確定日付のある債権譲渡の通知はある、という状況です。
(500万返せ)
被担保債権
↓
A➡︎B
↙︎ ↘︎二重譲渡
C D
C D
抵当権登記〇 抵当権登記✖︎
債権譲渡の通知✖︎ 債権譲渡の通知〇
さて、ではこの事例2で、抵当権はCとD、どちらの手に渡るのでしょうか?
結論。
抵当権はDのものになります。
登記をしてないDが勝つの?
Dが勝ちます。
なぜなら、Dの方は債権譲渡の通知が行われているからです。
債権が二重譲渡された場合に、債権譲渡の通知がある者とない者とがいたとき、その債権は債権譲渡の通知がある者が取得します。
したがって、事例2で、被担保債権を取得するのはDになります。
そして、抵当権には随伴性があるので、被担保債権を取得したのがDになれば、抵当権の登記がどうなっていようが、被担保債権に伴って抵当権もDが取得します。
このように、抵当権の随伴性は強力なものとなっています。
その効果は登記にも勝ってしまいます。
抵当権は被担保債権の家来です。
抵当権にとっては被担保債権が王様であり、王様には登記も勝てないということです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・抵当権の超基本
・被担保債権とは
・抵当権の付従性の緩和とは
・抵当権の随伴性とは
・登記に勝る強力な随伴性
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

抵当権の基本とその性質
抵当権とは、担保物権の一種で、目的物である不動産の引渡しを受けずに優先弁済権を確保する約定担保物権です。(約定担保物権とは契約等で設定する担保物権のこと)
これだとカタすぎてわかりづらいですよね。
もう少しわかりやすく解説するとこうなります。
抵当権とは、金融機関などが融資(お金を貸すこと)を行う際、その融資したお金が回収できない場合の担保(要するにリスクの担保)として不動産を確保して、実際にお金が回収できないような事態になったときは、強制的にその不動産を競売に出して(売っぱらって)、他の債権者に優先して(優先的に)その売却金からお金を回収できる権利です。
つまり、その権利(抵当権)を、お金を貸す側(金融機関など)とお金を借りる側が契約等で約束(約定)して設定する、ということです。
そして、お金を貸した側が抵当権者、お金を借りた側が抵当権設定者となります。
抵当権者 抵当権設定者
↓ 融資 ↓
金を貸す側 → 金を借りる側
(銀行等) (個人・法人等)
民法の条文はこちらです。
(抵当権の内容)
民法369条
1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
この民法369条の条文だと表現がカタいので理解しづらいですが、抵当権のポイントは「占有を移転しないで」と「他の債権者に先立って」です。
この2点が債権者にとって非常に都合が良く、現実の金融の世界でもっとも頻繁に利用される担保物権が抵当権である理由です。
(この点については「【抵当権の超基本】その特徴と意味とは?抵当権の強さの理由とは?一般財産って何?初学者にもわかりやすく解説!」でわかりやすく解説していますのでご参照ください)
また、抵当権は目的物の占有を伴わないので、登記という形でその権利を公示することになります。
これはどういう意味なのか、わかりやすく具体的に解説するとこうです。
例えば、Bさんに融資したA金融機関がB所有の不動産に抵当権を設定します。
するとA金融機関は抵当権者になります。
しかし、抵当権者であるA金融機関は、B所有の不動産を担保として確保していますが、B所有の不動産を実際に占有して利用するのはBさんです。
じゃあ「B所有の不動産に抵当権が付いていて、その抵当権者はA金融機関だ」ということをどうやって証明するのか?というと、それが抵当権の登記になります。
したがって、抵当権は登記という形でその権利の有無を公示(公に証明)しているのです。
また、抵当権が登記という形でその権利の有無を公示(公に証明)しているということは、登記(または登録)という形で公示している物でないと抵当権は設定できないということです。
原則として、抵当権は不動産に対して設定するものです。
民法上「動産」「債権」に設定することはできません。
この点はご注意ください。
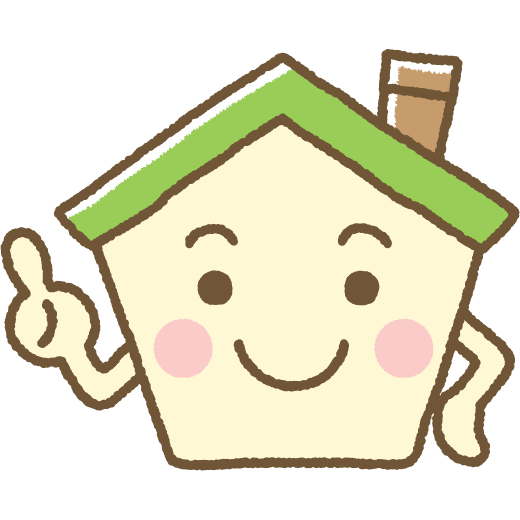
なお、民法369条2項にあるように、地上権・永小作権に抵当権を設定することはできます。
しかし、賃借権には抵当権を設定することはできません。
なぜなら、地上権・永小作権は物権ですが、賃借権は債権だからです。
被担保債権
抵当権は、被担保債権を担保するための物権です。
被担保債権とは、先述の金融機関の例で言うと、A金融機関が融資した相手方Bに対する「貸した金返せ」という貸金債権のことです。
つまり、その抵当権(担保物権)を設定する原因となっている債権のことです。
抵当権者 抵当権設定者
↓ 融資 ↓
A金融機関 → B
(貸す側) ↑ (借りる側)
被担保債権
また「抵当権(担保物権)を設定する原因となっている債権」が被担保債権ということは、抵当権は被担保債権の存在を前提としているということになります。
これを付従性といいます。
付従性の緩和
抵当権は被担保債権の存在が前提です。(付従性)
したがって、被担保債権が現に存在して初めて抵当権は成り立ちます。
しかし、抵当権は契約等で設定する(約定)担保物権ということもあり、実務上の要請から、抵当権成立時の付従性はかなり緩和されています。
付従性がかなり緩和されているということは、抵当権成立時には現に被担保債権が存在していなくとも、抵当権を設定できるということです。
具体例を挙げると、次のような債権を被担保債権として、抵当権を設定することができます。
・物の引渡し請求権のような非金銭債権(「金払え」じゃない債権)
・将来発生する金銭債権(未来の「金払え」)
上記2つのうち、重要なのは「将来発生する金銭債権」です。
これには次のようなものがあります。
【金銭消費貸借予約上の債権】
まさに先述の金融機関の例がこれです。
A金融機関がB所有の不動産に抵当権を設定する時、まだ実際の融資は行われていません。
抵当権の設定をしてから実際の融資が行われます。
これは付従性が緩和されているからこそできることなのです。
【保証人の求償債権】
これは、保証人が保証債務を履行した場合の、主債務者への求償債権のことです。
つまり、将来、保証人が保証債務を履行した場合の主債務者への求償債権に抵当権を設定できるということです。
【賃貸借契約による保証金の返還請求権】
これは、賃借人が入居時に差し入れた保証金についての、賃借人(借主)の賃貸人(貸主・オーナー)に対する「将来の退去時の(保証金)返還請求権」に抵当権を設定できるということです。
補足
付従性の緩和は、約定担保物権(抵当権と質権)に特有の話です。
法定担保物権には、付従性の緩和というものはありません。
法定担保物権とは、その担保物権の発生原因が法律によって定められていて、その原因が発生すると法律の定めによって自動的に成立する担保物権です。
法定担保物権には留置権や先取特権があります。留置権や先取特権につきましては、また別途改めて解説します。
抵当権の随伴性
被担保債権(その抵当権を設定する原因となっている債権)を担保するための抵当権は、被担保債権の存在を前提に成り立っています。
これは抵当権の付従性という性質によるものです。
そして、抵当権には付従性とともに、随伴性という性質もあります。
まずは事例をご覧ください。
事例1
AはBに500万円を融資し、その債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定した。その後、AはCにその500万円の貸金債権(被担保債権)を譲渡した。
まず、この事例1の状況を確認します。
AはBに500万円を貸し付けました。
そして、AはBに対する「500万円返せ」という債権を担保するために、B所有の不動産に抵当権を設定しました。
このときの、AのBに対する「500万円返せ」という債権が被担保債権になります。
そして、AはBに対する「500万円返せ」という債権、すなわち被担保債権をCに譲渡しました。(債権譲渡)
これが事例1の状況です。
さて、ここからが本題です。
この事例1で、AがCに被担保債権を譲渡したことにより、B所有の不動産に設定した抵当権の行方はどうなるのでしょうか?
結論。
抵当権は被担保債権に伴ってCに移転します。
したがいまして、B所有の不動産の抵当権者はCになります。(Bは抵当権設定者)
[被担保債権譲渡前]
債権者
(抵当権者)
A
抵当権⇨↙︎ ↘︎⇦被担保債権
B所有 B
不動産 債務者
(抵当権設定者)
[被担保債権譲渡後]
債権者
(抵当権者)
C
抵当権⇨↙︎ ↘︎⇦被担保債権
B所有 B
不動産 債務者
(抵当権設定者)
抵当権は、被担保債権が移転すると、それに伴って移転します。
つまり、抵当権は被担保債権にくっ付いていくということです。
これが随伴性です。
これは、言ってみればコナミのシューティングゲーム『グラディウス』の「オプション」みたいな感じですかね(笑)。
つまり、ビックバイパーが被担保債権、オプションが抵当権で、ビックバイパー(被担保債権)にくっ付いていくオプション(抵当権)には随伴性がある、みたいな。
グラディウスを知らない方は訳わからないですよね(笑)。
失礼しました。
登記に勝る強力な随伴性
抵当権の随伴性という性質は、グラディウスよりもっとわかりやすく言えば「被担保債権という王様に家来の抵当権がくっ付いていく」ようなものです。
そして、この抵当権の随伴性は、非常に強力な性質となっています。
どういうことかと言いますと、なんと!
随伴性が登記に勝るのです。

抵当権は不動産と同じように、登記というルールでその権利の有無を公示・証明し、対抗力を備えます。
つまり、抵当権も登記をすることにより法律で保護されるということです。
登記の力は強力です。
それは不動産の二重譲渡の問題などを見れば一目瞭然です。
(これについての詳しい解説は「【不動産登記の基本】二重譲渡~登記は早い者勝ち/3つの登記請求権と登記引取請求権とは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
ところが、抵当権の場合、抵当権の登記よりも、抵当権の随伴性が勝ってしまう!のです。
それでは、ここからは抵当権の随伴性について、事例と共に解説して参ります。
事例2
AはBに500万円を融資し、その債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、AはCにその500万円の貸金債権(被担保債権)を譲渡し、AからCへ抵当権移転の登記をしたが、債権譲渡についての通知は行なっていなかった。それからAは、その500万円の貸金債権をDへ二重譲渡し、その債権譲渡についての通知を行なったが、抵当権移転の登記はしていなかった。
登場人物が増えて状況が少し複雑になってきましたので、まずはこの事例2の状況を整理します。
この事例2では、まずAがBに500万円を融資して、その貸金債権を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定しました。
それからAは、その被担保債権をCとDの2人に二重譲渡し、Cの方は抵当権の登記はあるが確定日付のある債権譲渡の通知はなし、Dの方は抵当権はないが確定日付のある債権譲渡の通知はある、という状況です。
(500万返せ)
被担保債権
↓
A➡︎B
↙︎ ↘︎二重譲渡
C D
C D
抵当権登記〇 抵当権登記✖︎
債権譲渡の通知✖︎ 債権譲渡の通知〇
さて、ではこの事例2で、抵当権はCとD、どちらの手に渡るのでしょうか?
結論。
抵当権はDのものになります。
登記をしてないDが勝つの?
Dが勝ちます。
なぜなら、Dの方は債権譲渡の通知が行われているからです。
債権が二重譲渡された場合に、債権譲渡の通知がある者とない者とがいたとき、その債権は債権譲渡の通知がある者が取得します。
したがって、事例2で、被担保債権を取得するのはDになります。
そして、抵当権には随伴性があるので、被担保債権を取得したのがDになれば、抵当権の登記がどうなっていようが、被担保債権に伴って抵当権もDが取得します。
このように、抵当権の随伴性は強力なものとなっています。
その効果は登記にも勝ってしまいます。
抵当権は被担保債権の家来です。
抵当権にとっては被担保債権が王様であり、王様には登記も勝てないということです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【抵当権の基本】被担保債権と付従性の緩和とは?登記にも勝る強力な随伴性とは?わかりやすく解説!
【抵当権の基本】被担保債権と付従性の緩和とは?登記にも勝る強力な随伴性とは?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の効力の及ぶ範囲】エアコン等の付加一体物(付合物・従物)には?借地権は?果実は?わかりやすく解説!
【抵当権の効力の及ぶ範囲】エアコン等の付加一体物(付合物・従物)には?借地権は?果実は?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!
【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!
-
 【賃料債権の譲渡vs物上代位】抵当権者(物上代位)が勝たないと競売の値段に影響する?わかりやすく解説!
【賃料債権の譲渡vs物上代位】抵当権者(物上代位)が勝たないと競売の値段に影響する?わかりやすく解説!
-
 【抵当権に基づく妨害排除請求権と損害賠償請求権】【抵当不動産の賃貸と取り壊し】をわかりやすく解説!
【抵当権に基づく妨害排除請求権と損害賠償請求権】【抵当不動産の賃貸と取り壊し】をわかりやすく解説!
-
 【抵当権に遅れる賃貸借】競売の買受人と賃貸人の地位/後順位賃借権者と抵当権者の同意なしでは対抗力もなし?わかりやすく解説!
【抵当権に遅れる賃貸借】競売の買受人と賃貸人の地位/後順位賃借権者と抵当権者の同意なしでは対抗力もなし?わかりやすく解説!
-
 【共同抵当】同時配当と異時配当とは/抵当不動産の一部が債務者所有(物上保証)の場合は?わかりやすく解説!
【共同抵当】同時配当と異時配当とは/抵当不動産の一部が債務者所有(物上保証)の場合は?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の順位の変更】登記は対抗力でなく効力発生要件?/抵当権の優先弁済の範囲を具体的にわかりやすく解説!
【抵当権の順位の変更】登記は対抗力でなく効力発生要件?/抵当権の優先弁済の範囲を具体的にわかりやすく解説!
-
 抵当権の処分~【転抵当】【順位譲渡】【順位放棄】【譲渡と放棄】をわかりやすく解説!
抵当権の処分~【転抵当】【順位譲渡】【順位放棄】【譲渡と放棄】をわかりやすく解説!
-
 【抵当権の消滅請求と代価弁済】どう違う?第三取得者が抵当不動産について費用を支出すると?わかりやすく解説!
【抵当権の消滅請求と代価弁済】どう違う?第三取得者が抵当不動産について費用を支出すると?わかりやすく解説!
-
 【登記の流用】迷惑を被る第三者とは誰?なぜ登記の流用は行われる?わかりやすく解説!
【登記の流用】迷惑を被る第三者とは誰?なぜ登記の流用は行われる?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の消滅時効】抵当権は時効消滅するのか?抵当不動産の時効取得をわかりやすく解説!
【抵当権の消滅時効】抵当権は時効消滅するのか?抵当不動産の時効取得をわかりやすく解説!
-
 抵当権者は抵当権を行使せず一般財産を差し押さえられる?抵当権者と一般債権者の利害の調整をわかりやすく解説!
抵当権者は抵当権を行使せず一般財産を差し押さえられる?抵当権者と一般債権者の利害の調整をわかりやすく解説!
-