
▼この記事でわかること
・転抵当
・抵当権の順位譲渡、順位放棄
・抵当権の譲渡、放棄
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

抵当権の処分
抵当権は財産権の1つです。
したがって、これを処分することができます。
抵当権の処分には、次の3つがあります。
・転抵当
・抵当権の順位譲渡、順位放棄
・抵当権の譲渡、放棄
それでは、わかりやすく順番に解説して参ります。
転抵当
転抵当とは、抵当権自体を担保にすることです。
どんなケースで転抵当が利用されるかというと、金に困った抵当権者がその抵当権そのものを担保として金を借りるような場合です。
この場合、その抵当権を担保として抵当権者にお金を貸した者は「転抵当権者」となります。
それでは、わかりやすく具体的な事例とともに解説して参りましょう。
事例
BはCに融資し(これをb債権とする)、その担保としてD所有の不動産に抵当権を設定した。その後、金に困ったBは、その抵当権を担保にしてAから融資を受けた(これをa債権とする)。
まずは事例の状況を確認します。
まず、D所有の不動産を担保にCにお金を貸している(融資している)Bは抵当権者です。
一方、D所有の不動産を担保にBからお金を借りているCは債務者です。
Dは物上保証人です。
そして、抵当権者Bにその抵当権を担保としてお金を貸している(融資している)Aが転抵当権者です。
転抵当権者A
a債権⇨↓融資
抵当権権者B
b債権⇨↓融資 ↘︎⇦抵当権(転抵当の担保)
債務者C 物上保証人D
物上保証人もいるので複雑に感じてしまうかもしれませんが、まずは各者の立場と関係性を押さえてください。
では、本題の解説に入ります。
このケースで、転抵当権者Aは、いつ抵当権を実行できるのでしょうか?
結論。
転抵当権者Aは、a債権とb債権の両方の弁済期が到来すれば、抵当権を実行することができます。
ポイントは、転抵当権者AのBに対する債権の弁済期の到来だけではダメなことです。
AのBに対するa債権と、BのCに対するb債権の両方の債権の弁済期が到来して初めて、転抵当権者Aは抵当権を実行できるのです。
なお、転抵当権者Aが抵当権を実行した場合の配当金ですが、まず転抵当権者Aが取り、余りがあれば抵当権者B、さらに余れば物上保証人D、となります。
抵当権者Bは抵当権を実行できないのか?
これについては、b債権の額がa債権の額を上回る場合のみ、原抵当権(Bの抵当権)の実行が認められます。(判例)
なぜ、b債権の額がa債権の額を上回る場合だけなのかというと、原抵当権(Bの抵当権)を実行しても、配当金はまず転抵当権者Aから取ります。それで余りがあれば抵当権者Bが取ります。
ですので、b債権の額がa債権の額を上回らなければ、Bが余りの配当金を受ける可能性はナイのです。
つまり、Bが余りの配当金を受ける可能性がナイ場合にBが抵当権を実行しても、Bにとって何の意味もナイですよね。
Bにとってはただの無駄骨です。
したがって、b債権の額がa債権の額を上回る場合のみ、原抵当権(Bの抵当権)の実行が認められるのです。
債務者Cは誰に弁済すればいいのか
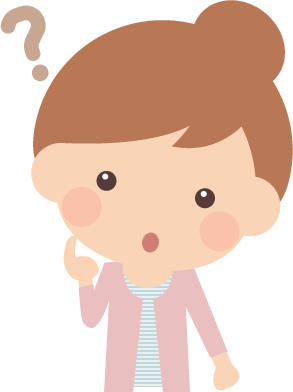
実は、転抵当は当事者同士の合意だけで効力が発生します。
つまり、事例1の場合、AB間の合意だけでイイのです。
ですので、AB間の転抵当について債務者Cが知らないということも十分ありえます。
そこで民法は、債権譲渡の対抗要件の規定に従い、Bが債務者Cに(AB間の転抵当について)通知するか、債務者Cが(AB間の転抵当について)承諾しなければ、転抵当を債務者Cや物上保証人Dに対抗できないとしています。
ポイントは、通知すべきはあくまで債務者Cで物上保証人Dではない、ということです。
物上保証人Dに通知しても、それは意味を成しません。
なぜなら、あくまで債務を弁済すべきなのは債務者Cだからです。
なお、転抵当の第三者に対する対抗要件は登記です。
しかし、事例1のAB間の転抵当については、債務者Cは第三者ではないありません。
では(第三者ではない)債務者Cに対する対抗要件は何になるのかというと、前述の債権譲渡の対抗要件の規定に従った通知・承諾になるのです。
この点はお気をつけください。
さて、前置きが長くなりましたが、では債務者Cは誰に弁済すればいいのでしょうか?
債務者Cが弁済すべき相手は転抵当権者Aです。
AB間の転抵当について債務者Cに対する対抗要件を備えた後は、債務者Cは転抵当権者Aに弁済しなければ免責されません(借りた金を返す責任を果たしたことにならない)。
転抵当権者Aの承諾を得れば抵当権者Bに弁済してもいいのですが、逆に言えば、転抵当権者Aの承諾を得ずにした抵当権者Bへの弁済は、転抵当権者Aに対抗することができません。
転抵当権者Aに対抗することができないということは、債務者Cは二重払いを強いられることになってしまいかねないということです。
なお、対抗要件を備える前であれば、抵当権者Bに対する弁済でも債務者Cは免責されます。(金を返す責任を果たしたことになる)
抵当権の順位譲渡・順位放棄
抵当権の順位譲渡・順位放棄とは、先順位の抵当権者が後順位の担保権者(抵当権者)に対してする処分です。
順位譲渡の場合は、順位譲渡した先順位の抵当権者より後順位の担保権者(抵当権者)が配当において優先されます。
単純な話ですね。
順位放棄の場合は、先順位の抵当権者と後順位の担保権者(抵当権者)が同順位となり、それぞれの債権額に応じて配当金を配分します。
それではここから、その配当額が実際にどのようになるのか、わかりやすく以下の設定にて、具体的に解説して参ります。
[抵当不動産]
甲土地
競売代金→1500万円
[甲土地の抵当権者]
1番抵当権者A:被担保債権額→500万円
2番抵当権者B:被担保債権額→500万円
3番抵当権者C:被担保債権額→1500万円
以上、上記の設定で、わかりやすくいくつかのケースについて解説します。
ケース1》AがCに順位譲渡した場合

抵当権の処分は、当事者同士の合意だけで効力が発生します。
つまり、AがCに抵当権の順位譲渡することは、AC間の合意だけでよく、Bの承諾は不要です。
なぜなら、Bの配当額にはまったく影響がないからです。
したがって、このケース1で配当額について考える場合、まずBの配当額から計算するのが早いです。
ということで、Bへの配当額から計算します。
先ほど「AC間の順位譲渡はAC間の合意だけで良い、なぜならBの配当額には影響がないから」と申しました。
ということは、AC間の順位譲渡がなかった場合のBの配当額が、そのまま、このケース1でのBの配当額になるという事です。
したがって、単純に順位譲渡がなかった場合の各配当額を考えれば、おのずとBの配当額はわかります。
[順位譲渡がなかった場合の各配当額]
A←500万円
B←500万円
C←500万円
ということで、ケース1でのBの配当額も500万円になります。
つづいて、AとCへの配当額ですが、Bの配当額が500万ということは
1500万(競売代金)ー500万(B配当分)=1000万=A配当分+C配当分
になります。
つまり、A配当分+C配当分=1000万円です。
そして、AがCに順位譲渡したことにより、Cへの配当が優先されます。
すると、Cの被担保債権額は1500万円なので、Cが1000万円の配当を受け、Aへの配当はゼロで終了です。
したがいまして、ケース1の各配当額は
A←0円
B←500万円
C←1000万円
となります。
ケース2》AがCに順位放棄した場合

AがCに順位放棄をすると、AとCは同順位となります。
同順位ということは、どちらが優先するということもありません。
したがって、AとCは、各債権額に応じた割合でそれぞれ配当を受けることになります。
また、Bへの配当額はケース1と一緒です。
ですので、A配当分+C配当分=1000万円まではケース1と同じ手順で計算します。
その後は、1000万円をACそれぞれの債権額に応じた割合で按分します。
[A配当額]
1000万×(500万÷2000万)=250万円
(A債権額÷ABC総債権額)
[C配当額]
1000万×(1500万÷2000万)=750万
(C債権額÷ABC総債権額)
ということで、ケース2の各配当額はこうなります。
A←250万円
B←500万円
C←750万円
抵当権の譲渡、放棄
抵当権の譲渡、放棄とは、無担保債権者に対する抵当権の処分です。
つまり、抵当権者が抵当権者以外に対して、その抵当権を譲渡・放棄するということです。
まず気を付けていただきたいのが、こちらは「順位の譲渡・放棄」ではなく「抵当権自体の譲渡・放棄」です。
では、その配当額が実際にどのようになるのか、わかりやすく以下の設定にて、具体的に解説して参ります。
[抵当不動産]
甲土地
競売代金→1500万円
[甲土地の抵当権者」
1番抵当権者A:被担保債権額→500万円
2番抵当権者B:被担保債権額→500万円
3番抵当権者C:被担保債権額→1500万円
無担保債権者D:(無担保)債権額→1500万円
(抵当権なし)
以上、上記の設定で、わかりやすくいくつかのケースについて解説します。
ケース3》AがDに抵当権を譲渡した場合

まず、抵当権の譲渡がなかった場合の配当額を確認します。
A←500万円
B←500万円
C←500万円
D←0円
これが抵当権の譲渡がなかった場合の配当額です。
ではここから、具体的に配当額を計算していきます。
まず、抵当権があっても、BとCへの配当額は変わりません。
B配当分+C配当分=1000万円なので、A配当分+D配当分は500万円になります。
ということは、500万円をAとDで取り合うことになる訳ですが、AがDに抵当権を譲渡したということは、DはAに優先して配当を受けます。
したがって、まずDが500万円の配当を受けて、Aは配当ゼロです。
よって、このケース3での配当額の結果はこうなります。
A←0万円
B←500万円
C←500万円
D←500万円
ケース4》AがDに抵当権を放棄した場合

まず、抵当権の放棄がなかった場合の配当額はこうです。
A←500万円
B←500万円
C←500万円
D←0円
そして、このケース4でも、抵当権の放棄があってもBとCへの配当額は変わりません。
ですので、A配当分+D配当分=500万円まではケース3と同じ手順で計算します。
ではAとDへの配当額ですが、AがDに抵当権の放棄をしたことにより、AとDは同順位という扱いになります。
したがって、500万円をA・Dそれぞれの債権額に応じた割合で按分します。
[A配当額]
500万×(500万÷2000万)=125万円
(A債権額÷ABC総債権額)※
※総債権額にはDの債権は含まない。なぜならD債権は無担保債権だから。甲土地の競売はあくまで被担保債権回収のための抵当権の実行によるものだから。
よって、ケース4の配当額の結果はこうなります。
A←125万円
B←500万円
C←500万円
D←375万
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・転抵当
・抵当権の順位譲渡、順位放棄
・抵当権の譲渡、放棄
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

抵当権の処分
抵当権は財産権の1つです。
したがって、これを処分することができます。
抵当権の処分には、次の3つがあります。
・転抵当
・抵当権の順位譲渡、順位放棄
・抵当権の譲渡、放棄
それでは、わかりやすく順番に解説して参ります。
転抵当
転抵当とは、抵当権自体を担保にすることです。
どんなケースで転抵当が利用されるかというと、金に困った抵当権者がその抵当権そのものを担保として金を借りるような場合です。
この場合、その抵当権を担保として抵当権者にお金を貸した者は「転抵当権者」となります。
それでは、わかりやすく具体的な事例とともに解説して参りましょう。
事例
BはCに融資し(これをb債権とする)、その担保としてD所有の不動産に抵当権を設定した。その後、金に困ったBは、その抵当権を担保にしてAから融資を受けた(これをa債権とする)。
まずは事例の状況を確認します。
まず、D所有の不動産を担保にCにお金を貸している(融資している)Bは抵当権者です。
一方、D所有の不動産を担保にBからお金を借りているCは債務者です。
Dは物上保証人です。
そして、抵当権者Bにその抵当権を担保としてお金を貸している(融資している)Aが転抵当権者です。
転抵当権者A
a債権⇨↓融資
抵当権権者B
b債権⇨↓融資 ↘︎⇦抵当権(転抵当の担保)
債務者C 物上保証人D
物上保証人もいるので複雑に感じてしまうかもしれませんが、まずは各者の立場と関係性を押さえてください。
では、本題の解説に入ります。
このケースで、転抵当権者Aは、いつ抵当権を実行できるのでしょうか?
結論。
転抵当権者Aは、a債権とb債権の両方の弁済期が到来すれば、抵当権を実行することができます。
ポイントは、転抵当権者AのBに対する債権の弁済期の到来だけではダメなことです。
AのBに対するa債権と、BのCに対するb債権の両方の債権の弁済期が到来して初めて、転抵当権者Aは抵当権を実行できるのです。
なお、転抵当権者Aが抵当権を実行した場合の配当金ですが、まず転抵当権者Aが取り、余りがあれば抵当権者B、さらに余れば物上保証人D、となります。
抵当権者Bは抵当権を実行できないのか?
これについては、b債権の額がa債権の額を上回る場合のみ、原抵当権(Bの抵当権)の実行が認められます。(判例)
なぜ、b債権の額がa債権の額を上回る場合だけなのかというと、原抵当権(Bの抵当権)を実行しても、配当金はまず転抵当権者Aから取ります。それで余りがあれば抵当権者Bが取ります。
ですので、b債権の額がa債権の額を上回らなければ、Bが余りの配当金を受ける可能性はナイのです。
つまり、Bが余りの配当金を受ける可能性がナイ場合にBが抵当権を実行しても、Bにとって何の意味もナイですよね。
Bにとってはただの無駄骨です。
したがって、b債権の額がa債権の額を上回る場合のみ、原抵当権(Bの抵当権)の実行が認められるのです。
債務者Cは誰に弁済すればいいのか
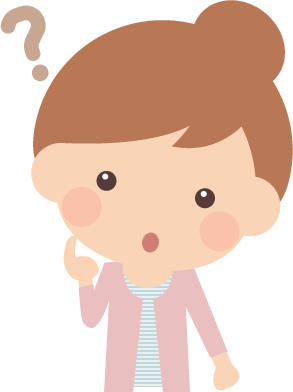
実は、転抵当は当事者同士の合意だけで効力が発生します。
つまり、事例1の場合、AB間の合意だけでイイのです。
ですので、AB間の転抵当について債務者Cが知らないということも十分ありえます。
そこで民法は、債権譲渡の対抗要件の規定に従い、Bが債務者Cに(AB間の転抵当について)通知するか、債務者Cが(AB間の転抵当について)承諾しなければ、転抵当を債務者Cや物上保証人Dに対抗できないとしています。
ポイントは、通知すべきはあくまで債務者Cで物上保証人Dではない、ということです。
物上保証人Dに通知しても、それは意味を成しません。
なぜなら、あくまで債務を弁済すべきなのは債務者Cだからです。
なお、転抵当の第三者に対する対抗要件は登記です。
しかし、事例1のAB間の転抵当については、債務者Cは第三者ではないありません。
では(第三者ではない)債務者Cに対する対抗要件は何になるのかというと、前述の債権譲渡の対抗要件の規定に従った通知・承諾になるのです。
この点はお気をつけください。
さて、前置きが長くなりましたが、では債務者Cは誰に弁済すればいいのでしょうか?
債務者Cが弁済すべき相手は転抵当権者Aです。
AB間の転抵当について債務者Cに対する対抗要件を備えた後は、債務者Cは転抵当権者Aに弁済しなければ免責されません(借りた金を返す責任を果たしたことにならない)。
転抵当権者Aの承諾を得れば抵当権者Bに弁済してもいいのですが、逆に言えば、転抵当権者Aの承諾を得ずにした抵当権者Bへの弁済は、転抵当権者Aに対抗することができません。
転抵当権者Aに対抗することができないということは、債務者Cは二重払いを強いられることになってしまいかねないということです。
なお、対抗要件を備える前であれば、抵当権者Bに対する弁済でも債務者Cは免責されます。(金を返す責任を果たしたことになる)
抵当権の順位譲渡・順位放棄
抵当権の順位譲渡・順位放棄とは、先順位の抵当権者が後順位の担保権者(抵当権者)に対してする処分です。
順位譲渡の場合は、順位譲渡した先順位の抵当権者より後順位の担保権者(抵当権者)が配当において優先されます。
単純な話ですね。
順位放棄の場合は、先順位の抵当権者と後順位の担保権者(抵当権者)が同順位となり、それぞれの債権額に応じて配当金を配分します。
それではここから、その配当額が実際にどのようになるのか、わかりやすく以下の設定にて、具体的に解説して参ります。
[抵当不動産]
甲土地
競売代金→1500万円
[甲土地の抵当権者]
1番抵当権者A:被担保債権額→500万円
2番抵当権者B:被担保債権額→500万円
3番抵当権者C:被担保債権額→1500万円
以上、上記の設定で、わかりやすくいくつかのケースについて解説します。
ケース1》AがCに順位譲渡した場合

抵当権の処分は、当事者同士の合意だけで効力が発生します。
つまり、AがCに抵当権の順位譲渡することは、AC間の合意だけでよく、Bの承諾は不要です。
なぜなら、Bの配当額にはまったく影響がないからです。
したがって、このケース1で配当額について考える場合、まずBの配当額から計算するのが早いです。
ということで、Bへの配当額から計算します。
先ほど「AC間の順位譲渡はAC間の合意だけで良い、なぜならBの配当額には影響がないから」と申しました。
ということは、AC間の順位譲渡がなかった場合のBの配当額が、そのまま、このケース1でのBの配当額になるという事です。
したがって、単純に順位譲渡がなかった場合の各配当額を考えれば、おのずとBの配当額はわかります。
[順位譲渡がなかった場合の各配当額]
A←500万円
B←500万円
C←500万円
ということで、ケース1でのBの配当額も500万円になります。
つづいて、AとCへの配当額ですが、Bの配当額が500万ということは
1500万(競売代金)ー500万(B配当分)=1000万=A配当分+C配当分
になります。
つまり、A配当分+C配当分=1000万円です。
そして、AがCに順位譲渡したことにより、Cへの配当が優先されます。
すると、Cの被担保債権額は1500万円なので、Cが1000万円の配当を受け、Aへの配当はゼロで終了です。
したがいまして、ケース1の各配当額は
A←0円
B←500万円
C←1000万円
となります。
ケース2》AがCに順位放棄した場合

AがCに順位放棄をすると、AとCは同順位となります。
同順位ということは、どちらが優先するということもありません。
したがって、AとCは、各債権額に応じた割合でそれぞれ配当を受けることになります。
また、Bへの配当額はケース1と一緒です。
ですので、A配当分+C配当分=1000万円まではケース1と同じ手順で計算します。
その後は、1000万円をACそれぞれの債権額に応じた割合で按分します。
[A配当額]
1000万×(500万÷2000万)=250万円
(A債権額÷ABC総債権額)
[C配当額]
1000万×(1500万÷2000万)=750万
(C債権額÷ABC総債権額)
ということで、ケース2の各配当額はこうなります。
A←250万円
B←500万円
C←750万円
抵当権の譲渡、放棄
抵当権の譲渡、放棄とは、無担保債権者に対する抵当権の処分です。
つまり、抵当権者が抵当権者以外に対して、その抵当権を譲渡・放棄するということです。
まず気を付けていただきたいのが、こちらは「順位の譲渡・放棄」ではなく「抵当権自体の譲渡・放棄」です。
では、その配当額が実際にどのようになるのか、わかりやすく以下の設定にて、具体的に解説して参ります。
[抵当不動産]
甲土地
競売代金→1500万円
[甲土地の抵当権者」
1番抵当権者A:被担保債権額→500万円
2番抵当権者B:被担保債権額→500万円
3番抵当権者C:被担保債権額→1500万円
無担保債権者D:(無担保)債権額→1500万円
(抵当権なし)
以上、上記の設定で、わかりやすくいくつかのケースについて解説します。
ケース3》AがDに抵当権を譲渡した場合

まず、抵当権の譲渡がなかった場合の配当額を確認します。
A←500万円
B←500万円
C←500万円
D←0円
これが抵当権の譲渡がなかった場合の配当額です。
ではここから、具体的に配当額を計算していきます。
まず、抵当権があっても、BとCへの配当額は変わりません。
B配当分+C配当分=1000万円なので、A配当分+D配当分は500万円になります。
ということは、500万円をAとDで取り合うことになる訳ですが、AがDに抵当権を譲渡したということは、DはAに優先して配当を受けます。
したがって、まずDが500万円の配当を受けて、Aは配当ゼロです。
よって、このケース3での配当額の結果はこうなります。
A←0万円
B←500万円
C←500万円
D←500万円
ケース4》AがDに抵当権を放棄した場合

まず、抵当権の放棄がなかった場合の配当額はこうです。
A←500万円
B←500万円
C←500万円
D←0円
そして、このケース4でも、抵当権の放棄があってもBとCへの配当額は変わりません。
ですので、A配当分+D配当分=500万円まではケース3と同じ手順で計算します。
ではAとDへの配当額ですが、AがDに抵当権の放棄をしたことにより、AとDは同順位という扱いになります。
したがって、500万円をA・Dそれぞれの債権額に応じた割合で按分します。
[A配当額]
500万×(500万÷2000万)=125万円
(A債権額÷ABC総債権額)※
※総債権額にはDの債権は含まない。なぜならD債権は無担保債権だから。甲土地の競売はあくまで被担保債権回収のための抵当権の実行によるものだから。
よって、ケース4の配当額の結果はこうなります。
A←125万円
B←500万円
C←500万円
D←375万
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【抵当権の基本】被担保債権と付従性の緩和とは?登記にも勝る強力な随伴性とは?わかりやすく解説!
【抵当権の基本】被担保債権と付従性の緩和とは?登記にも勝る強力な随伴性とは?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の効力の及ぶ範囲】エアコン等の付加一体物(付合物・従物)には?借地権は?果実は?わかりやすく解説!
【抵当権の効力の及ぶ範囲】エアコン等の付加一体物(付合物・従物)には?借地権は?果実は?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!
【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!
-
 【賃料債権の譲渡vs物上代位】抵当権者(物上代位)が勝たないと競売の値段に影響する?わかりやすく解説!
【賃料債権の譲渡vs物上代位】抵当権者(物上代位)が勝たないと競売の値段に影響する?わかりやすく解説!
-
 【抵当権に基づく妨害排除請求権と損害賠償請求権】【抵当不動産の賃貸と取り壊し】をわかりやすく解説!
【抵当権に基づく妨害排除請求権と損害賠償請求権】【抵当不動産の賃貸と取り壊し】をわかりやすく解説!
-
 【抵当権に遅れる賃貸借】競売の買受人と賃貸人の地位/後順位賃借権者と抵当権者の同意なしでは対抗力もなし?わかりやすく解説!
【抵当権に遅れる賃貸借】競売の買受人と賃貸人の地位/後順位賃借権者と抵当権者の同意なしでは対抗力もなし?わかりやすく解説!
-
 【共同抵当】同時配当と異時配当とは/抵当不動産の一部が債務者所有(物上保証)の場合は?わかりやすく解説!
【共同抵当】同時配当と異時配当とは/抵当不動産の一部が債務者所有(物上保証)の場合は?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の順位の変更】登記は対抗力でなく効力発生要件?/抵当権の優先弁済の範囲を具体的にわかりやすく解説!
【抵当権の順位の変更】登記は対抗力でなく効力発生要件?/抵当権の優先弁済の範囲を具体的にわかりやすく解説!
-
 抵当権の処分~【転抵当】【順位譲渡】【順位放棄】【譲渡と放棄】をわかりやすく解説!
抵当権の処分~【転抵当】【順位譲渡】【順位放棄】【譲渡と放棄】をわかりやすく解説!
-
 【抵当権の消滅請求と代価弁済】どう違う?第三取得者が抵当不動産について費用を支出すると?わかりやすく解説!
【抵当権の消滅請求と代価弁済】どう違う?第三取得者が抵当不動産について費用を支出すると?わかりやすく解説!
-
 【登記の流用】迷惑を被る第三者とは誰?なぜ登記の流用は行われる?わかりやすく解説!
【登記の流用】迷惑を被る第三者とは誰?なぜ登記の流用は行われる?わかりやすく解説!
-
 【抵当権の消滅時効】抵当権は時効消滅するのか?抵当不動産の時効取得をわかりやすく解説!
【抵当権の消滅時効】抵当権は時効消滅するのか?抵当不動産の時効取得をわかりやすく解説!
-
 抵当権者は抵当権を行使せず一般財産を差し押さえられる?抵当権者と一般債権者の利害の調整をわかりやすく解説!
抵当権者は抵当権を行使せず一般財産を差し押さえられる?抵当権者と一般債権者の利害の調整をわかりやすく解説!
-