
▼この記事でわかること
・代理人の(制限)行為能力の基本
・未成年者の委任契約の取消し
・表現&無権代理人が配偶者の場合
・夫婦の場合には別の規定がある?
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

代理人の(制限)行為能力
実は、代理人になるには行為能力者である必要はありません。
民法では次のように規定します。
(代理人の行為能力)
民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
この民法102条の条文は、制限行為能力者が代理人としてした行為についての規定です。
つまり、未成年者などの制限行為能力者でも代理人になれるということです。
え?マジで?
はい。マジです。
ではなぜ、制限行為能力者でも代理人になれるのでしょうか?
事例1
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。
さて、この事例1で、未成年者である代理人Bは、制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消せるでしょうか?
結論。
未成年者Bは制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消すことはできません。
なぜなら、先述の民法102条の規定は「制限行為能力者でも代理人になれますよ。そのかわり代理人になったら制限行為能力者として扱わないですよ!」という意味なのです。
え?でもそれじゃ制限行為能力者がキケンじゃね?
そんなことはありません。
なぜなら、代理行為の法律効果が帰属するのは(代理行為で結んだ契約の、契約上の責任が生じるのは)本人です。
代理人ではありません。
ですので問題ないのです。
それに、事例1で、本人Aはわざわざ未成年者Bに代理を依頼したということですよね?
それはつまり、それだけ未成年者Bがその辺の大人よりしっかりしてるとか、代理を頼むに相応しい理由があるはずです。
それで本人Aが納得して「Bに頼むわ!」としているのであれば、それならそれでイイんじゃね?ということになるわけです。
また、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人になった場合に代理人としてした行為は、例外的に行為能力の制限を理由に取り消すことができます。
この点でも安全は担保されているというわけです。
未成年者の委任契約の取消し
事例2
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。しかしその後、未成年者BがAと結んでいた委任契約は親権者の同意を得ないでしたものであることが発覚した。
さて、この事例2で、未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができるでしょうか?
結論。
未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができます。
ここでひとつ問題があります。
というのは、取消しの効果は遡及します。
したがって、AとBの委任契約を取り消すとその効果は遡って発するので、BはハナっからAの代理人では無かったことになります。
すると、BがやったCとの甲別荘の売買契約は無権代理行為ということになってしまうのです。
これが問題なんです。
だってこれでは、相手方Cが困ってしまいまよね。
せっかくお金持ちのAに売れたと思ったのに、甲別荘の売買契約が有効になるには、表見代理が成立するか本人Aが追認するかしなければなりません。
もし表見代理が成立せず本人Aが追認しなかった場合は最悪です。
Bは未成年者、すなわち制限行為能力者ということなので、民法117条2項の規定により、Bに無権代理行為の責任を追及することもできません。
これでは相手方Cがあまりにも気の毒です。
ですので、このようなケースにおいては、委任契約を取り消した際の遡及効(さかのぼって発する効力)を制限し、その取消しの効果は将来に向かってだけ有効とし、代理人の契約当時の代理権は消滅しないという結論を取ります。
つまり、事例2で、未成年者BとAの委任契約が取り消されたとしても、取り消す前にCと交わした甲別荘の売買契約時のBの代理権は消滅しないということです。
よって、甲別荘の売買契約も有効に成立します。
なんだかややこしい結論に感じたかもしれませんが、このようにすることによって、相手方Cの権利と制限行為能力者Bの保護のバランスを取っているのです。(こういったところが民法を難しく感じさせる部分であり、民法の特徴でもあります)
法律は決して万能ではありません。
だからこそ、このような様々なケースに対応しながら、そこに絡んでくる人達の権利の保護とバランスをなんとかはかっているのです。
このあたりの理屈は、最初は中々掴みづらいかもしれません。
しかし、民法の学習を繰り返していって次第に慣れてくると、自然とスーッと頭に入って来るようにもなります。
なので民法くんには、根気よく接してやってください(笑)。
表現&無権代理人が配偶者の場合
事例3
A男とB子は夫婦である。B子はA男に無断で、Aの代理人と称してA所有の甲不動産をCに売却した。
さて、続いてこの事例3ですが、ここでのポイントは、無権代理人Bと本人Aが夫婦だという点です。
まずはそこを押さえた上で、、これがAとBが夫婦ではなかった場合、表見代理の成立はありません。
それは完全に無権代理の問題です。
なぜなら、無権代理人Bは本人Aに「無断で」無権代理行為を行っているからです。
表見代理の可能性があるケースは、以下の3類系※にあてはまる場合です。
・代理権授与の表示による表見代理
・権限外の行為の表見代理
・代理権の消滅事由
(※表見代理の3類型についての詳しい解説は「【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!」をご覧ください)
事例3では「無断で」とあるので、上記の3類系にあてはまらず、表見代理の問題にはならないのです。
つまり、本人Aに責任が及ぶことはなく、責任が及ぶのは無権代理人B自身です。
夫婦の場合には別の条文がある
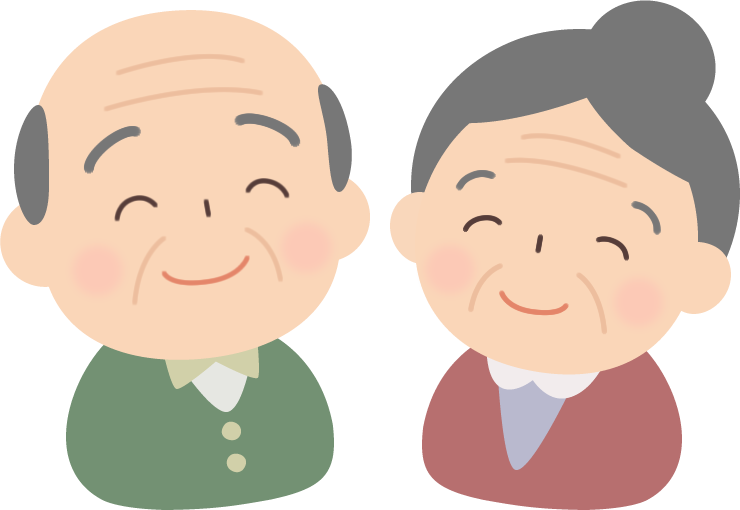
最初に事例のポイントと申し上げましたが、今度の事例3のAとBは夫婦です。
実は、これが少々やっかいなんです。
先ほど述べたとおり、AとBが夫婦でなければ「無断で」とある限り表見代理の問題にならず、単純に「Bの無権代理の問題ですね。以上」と終われるところなのですが、夫婦の場合には、以下のような民法の条文が存在します。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
つまり、民法761条の規定により、夫婦の一方が行った法律行為は、夫婦として連帯責任を持つということです。
ただ、条文にあるとおり、その対象となる法律行為とは「日常の家事に関して」です。
では、果たして事例3のような不動産の売却行為が日常の家事に関する法律行為にあたるでしょうか?
あたるか!セレブか!と思わずツッコミたくなるところですが、ツッコむまでもなく、普通に考えて、不動産の売却が日常の家事に関する法律行為にあたるわけないですよね。
したがいまして、事例3では表見代理の成立はなく、民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)の適用もありませんので、相手方Cは甲不動産を取得することはできません。
【補足】
実は判例では、事例3のようなケースにおいて、表見代理が成立され得る可能性を開いています。
え?なんで?
判例の理屈としてはざっくりこうです。
「先述の民法761条は「夫婦間の相互の代理権」を規定していて、それは法定代理権の一種である。法定代理権を基本代理権とした「権限外の行為の表見代理」は成立し得る。そして民法761条の「夫婦間の相互の代理権」を基本代理権として民法110条(権限外の行為の表見代理)の規定を類推適用し、相手方が無権代理人に代理権ありと信じるにつき正当な理由があれば表見代理は成立し得る」
自分で書いておいてなんですが、おそらくこれを読んでもよくわからないですよね(笑)。
さらに身も蓋もない事を申しますと、この理屈を理解する必要もないです。
大事なのは、事例3のようなケースでも「表見代理が成立し得る可能性はある」ということです。
ですので、ここで覚えておいていただきたいのは、事例3のようなケースでも、取引の内容やその他の具体的な事情によっては表見代理の成立もあり得ると判例は言っていることです。
理屈の理解は置いてといて、この結論の部分だけ覚えておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・代理人の(制限)行為能力の基本
・未成年者の委任契約の取消し
・表現&無権代理人が配偶者の場合
・夫婦の場合には別の規定がある?
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

代理人の(制限)行為能力
実は、代理人になるには行為能力者である必要はありません。
民法では次のように規定します。
(代理人の行為能力)
民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
この民法102条の条文は、制限行為能力者が代理人としてした行為についての規定です。
つまり、未成年者などの制限行為能力者でも代理人になれるということです。
え?マジで?
はい。マジです。
ではなぜ、制限行為能力者でも代理人になれるのでしょうか?
事例1
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。
さて、この事例1で、未成年者である代理人Bは、制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消せるでしょうか?
結論。
未成年者Bは制限行為能力者であることを理由に甲別荘の売買契約を取り消すことはできません。
なぜなら、先述の民法102条の規定は「制限行為能力者でも代理人になれますよ。そのかわり代理人になったら制限行為能力者として扱わないですよ!」という意味なのです。
え?でもそれじゃ制限行為能力者がキケンじゃね?
そんなことはありません。
なぜなら、代理行為の法律効果が帰属するのは(代理行為で結んだ契約の、契約上の責任が生じるのは)本人です。
代理人ではありません。
ですので問題ないのです。
それに、事例1で、本人Aはわざわざ未成年者Bに代理を依頼したということですよね?
それはつまり、それだけ未成年者Bがその辺の大人よりしっかりしてるとか、代理を頼むに相応しい理由があるはずです。
それで本人Aが納得して「Bに頼むわ!」としているのであれば、それならそれでイイんじゃね?ということになるわけです。
また、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人になった場合に代理人としてした行為は、例外的に行為能力の制限を理由に取り消すことができます。
この点でも安全は担保されているというわけです。
未成年者の委任契約の取消し
事例2
未成年者のBはお金持ちのAの代理人として、軽井沢にあるC所有の甲別荘の売買契約を締結した。しかしその後、未成年者BがAと結んでいた委任契約は親権者の同意を得ないでしたものであることが発覚した。
さて、この事例2で、未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができるでしょうか?
結論。
未成年者BはAとの委任契約を取り消すことができます。
ここでひとつ問題があります。
というのは、取消しの効果は遡及します。
したがって、AとBの委任契約を取り消すとその効果は遡って発するので、BはハナっからAの代理人では無かったことになります。
すると、BがやったCとの甲別荘の売買契約は無権代理行為ということになってしまうのです。
これが問題なんです。
だってこれでは、相手方Cが困ってしまいまよね。
せっかくお金持ちのAに売れたと思ったのに、甲別荘の売買契約が有効になるには、表見代理が成立するか本人Aが追認するかしなければなりません。
もし表見代理が成立せず本人Aが追認しなかった場合は最悪です。
Bは未成年者、すなわち制限行為能力者ということなので、民法117条2項の規定により、Bに無権代理行為の責任を追及することもできません。
これでは相手方Cがあまりにも気の毒です。
ですので、このようなケースにおいては、委任契約を取り消した際の遡及効(さかのぼって発する効力)を制限し、その取消しの効果は将来に向かってだけ有効とし、代理人の契約当時の代理権は消滅しないという結論を取ります。
つまり、事例2で、未成年者BとAの委任契約が取り消されたとしても、取り消す前にCと交わした甲別荘の売買契約時のBの代理権は消滅しないということです。
よって、甲別荘の売買契約も有効に成立します。
なんだかややこしい結論に感じたかもしれませんが、このようにすることによって、相手方Cの権利と制限行為能力者Bの保護のバランスを取っているのです。(こういったところが民法を難しく感じさせる部分であり、民法の特徴でもあります)
法律は決して万能ではありません。
だからこそ、このような様々なケースに対応しながら、そこに絡んでくる人達の権利の保護とバランスをなんとかはかっているのです。
このあたりの理屈は、最初は中々掴みづらいかもしれません。
しかし、民法の学習を繰り返していって次第に慣れてくると、自然とスーッと頭に入って来るようにもなります。
なので民法くんには、根気よく接してやってください(笑)。
表現&無権代理人が配偶者の場合
事例3
A男とB子は夫婦である。B子はA男に無断で、Aの代理人と称してA所有の甲不動産をCに売却した。
さて、続いてこの事例3ですが、ここでのポイントは、無権代理人Bと本人Aが夫婦だという点です。
まずはそこを押さえた上で、、これがAとBが夫婦ではなかった場合、表見代理の成立はありません。
それは完全に無権代理の問題です。
なぜなら、無権代理人Bは本人Aに「無断で」無権代理行為を行っているからです。
表見代理の可能性があるケースは、以下の3類系※にあてはまる場合です。
・代理権授与の表示による表見代理
・権限外の行為の表見代理
・代理権の消滅事由
(※表見代理の3類型についての詳しい解説は「【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!」をご覧ください)
事例3では「無断で」とあるので、上記の3類系にあてはまらず、表見代理の問題にはならないのです。
つまり、本人Aに責任が及ぶことはなく、責任が及ぶのは無権代理人B自身です。
夫婦の場合には別の条文がある
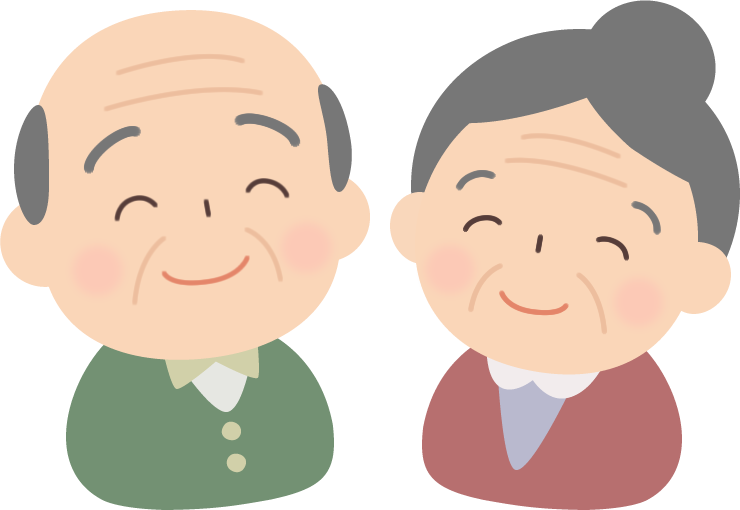
最初に事例のポイントと申し上げましたが、今度の事例3のAとBは夫婦です。
実は、これが少々やっかいなんです。
先ほど述べたとおり、AとBが夫婦でなければ「無断で」とある限り表見代理の問題にならず、単純に「Bの無権代理の問題ですね。以上」と終われるところなのですが、夫婦の場合には、以下のような民法の条文が存在します。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
つまり、民法761条の規定により、夫婦の一方が行った法律行為は、夫婦として連帯責任を持つということです。
ただ、条文にあるとおり、その対象となる法律行為とは「日常の家事に関して」です。
では、果たして事例3のような不動産の売却行為が日常の家事に関する法律行為にあたるでしょうか?
あたるか!セレブか!と思わずツッコミたくなるところですが、ツッコむまでもなく、普通に考えて、不動産の売却が日常の家事に関する法律行為にあたるわけないですよね。
したがいまして、事例3では表見代理の成立はなく、民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)の適用もありませんので、相手方Cは甲不動産を取得することはできません。
【補足】
実は判例では、事例3のようなケースにおいて、表見代理が成立され得る可能性を開いています。
え?なんで?
判例の理屈としてはざっくりこうです。
「先述の民法761条は「夫婦間の相互の代理権」を規定していて、それは法定代理権の一種である。法定代理権を基本代理権とした「権限外の行為の表見代理」は成立し得る。そして民法761条の「夫婦間の相互の代理権」を基本代理権として民法110条(権限外の行為の表見代理)の規定を類推適用し、相手方が無権代理人に代理権ありと信じるにつき正当な理由があれば表見代理は成立し得る」
自分で書いておいてなんですが、おそらくこれを読んでもよくわからないですよね(笑)。
さらに身も蓋もない事を申しますと、この理屈を理解する必要もないです。
大事なのは、事例3のようなケースでも「表見代理が成立し得る可能性はある」ということです。
ですので、ここで覚えておいていただきたいのは、事例3のようなケースでも、取引の内容やその他の具体的な事情によっては表見代理の成立もあり得ると判例は言っていることです。
理屈の理解は置いてといて、この結論の部分だけ覚えておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!
【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!
-
 【無権代理行為の追認】催告権と取消権とは?その違いとは?/法定追認をわかりやすく解説!
【無権代理行為の追認】催告権と取消権とは?その違いとは?/法定追認をわかりやすく解説!
-
 【無権代理人の責任はかなり重い】無権代理人に救いの道はないのか?わかりやすく解説!
【無権代理人の責任はかなり重い】無権代理人に救いの道はないのか?わかりやすく解説!
-
 【代理行為の瑕疵】代理人&本人の善意・悪意について/特定の法律行為の委託とは?わかりやすく解説!
【代理行為の瑕疵】代理人&本人の善意・悪意について/特定の法律行為の委託とは?わかりやすく解説!
-
 【代理人の権限濫用】それでも代理は成立している?裁判所の使う類推適用という荒技をわかりやすく解説!
【代理人の権限濫用】それでも代理は成立している?裁判所の使う類推適用という荒技をわかりやすく解説!
-
 【代理人の行為能力】表現代理人・無権代理人が配偶者の場合をわかりやすく解説!
【代理人の行為能力】表現代理人・無権代理人が配偶者の場合をわかりやすく解説!
-
 【任意代理と法定代理】法定代理に表見代理はあり得るのか?わかりやすく解説!
【任意代理と法定代理】法定代理に表見代理はあり得るのか?わかりやすく解説!
-
 【復代理】任意代理人と法定代理人の場合では責任の度合いが違う/代理を丸投げできるケースとは?わかりやすく解説!
【復代理】任意代理人と法定代理人の場合では責任の度合いが違う/代理を丸投げできるケースとは?わかりやすく解説!
-
 【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!
【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!
-