
▼この記事でわかること
・任意代理と法定代理とその違い
・法定代理に表見代理は成立するのか?
・法定代理人に基本代理権は存在するのか?
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

任意代理と法定代理
代理は大きく分けて2種類あります。
それは任意代理と法定代理です。
【任意代理】
これは、委任による代理です。
つまり、本人が「あなたに代理を頼みます」といってお願いする代理です。
おそらく、一般的にイメージする代理は、こちらの任意代理になるかと思います。
「委任による代理=任意代理」
まずはここを押さえておいてください。
【法定代理】
これは、法律によって定められた代理です。
本人が「あなたに代理を頼みます」といってお願いする訳ではありません。
本人がお願いするまでもなく、法律によって定まる代理です。
最もわかりやすい法定代理は未成年者の親権者です。
通常、子供の親は子供の法定代理人になります。
でもこれって、子供が親に「代理頼みます」とお願いして成立するものではありませんよね?
「法律がそう決めた」からそうなるのです。
委任による代理=任意代理
法律によって定められた代理=法定代理
この基本はまず、確実に覚えておいていただければと存じます。
法定代理に表見代理は成立するのか
さて、ここでこんな疑問が湧きませんか?
それは、法定代理にも表見代理が成立するのか?です。
まず、表見代理が成立するには、前提として無権代理行為の存在がなければなりません。
となると、そもそも法定代理人の無権代理行為があり得るのか?となりますよね。
というのは、法定代理人は本人にお願いされてなるものではありません。
法律の定めによってなるものです。
つまり、普通に考えて「法定代理人に代理権がない状態」はありえないことになります。
すると、法定代理人の無権代理行為があり得るケースとして考えられるものがあるとすれば「代理権限を超えた」場合です。
代理権限を超えた場合とは、例えば「軽井沢の別荘の購入」という代理権を付与された代理人(任意代理人)が、那須の別荘を購入してしまうようなケースです。
このときの「軽井沢の別荘の購入」は基本代理権になります。
その基本代理権を超えた代理行為「那須の別荘の購入」が、代理権限を超えた無権代理行為となります。
つまり「代理権限を超えた無権代理行為」とは、前提となる基本代理権があって初めて成り立つものです。
このように考えていくと、法定代理に表見代理があり得るのか?という問題は、法定代理人に基本代理権というものが存在するのか?という問いへの結論次第ということになります。
法定代理人に基本代理権は存在するのか?
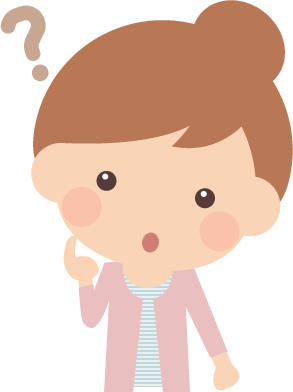
これは、実はハッキリと明確に結論づけられている訳ではありません。
なんじゃそれ?じゃあ結局どーなのよ!?
ですよね(笑)。
ただ一応、法定代理にも下記の規定、表見代理の3類系のうちの2つの適用はあるとされています。
民法110条(権限外の行為の表見代理)
民法112条(代理権消滅後の表見代理)
先ほどまで解説して参りました内容は、法定代理における「権限外の行為の表見代理」です。
しかし、どうやら民法112条「代理権消滅後の表見代理」の方についても、法定代理での適用はあるようです。
また、判例では「法定代理においても、表見代理の成立はなくはない」というように結論づけています。
結局どっちやねん!
ツッコミたくなりますよね(笑)。
しかし、このような曖昧な結論というのは、民法の学習をしていると結構よく出てきます。
ですので強引に慣れていってください(笑)。
まあ、なぜこのような曖昧な結論になってしまうかの理由を考えると、それは「法定代理には本人の帰責性がありえない」ということが言えます。
法定代理人は本人が選んでお願いしている訳ではないので「そんなヤツを代理人に選んでしまった本人も悪い」という理屈が成り立たないのです。
表見代理は、そのような本人の帰責事由を成立要件として、相手方を保護し、取引の安全性を確保する制度です。
ですので、本来の理屈としては、法定代理には表見代理は成立しないとなるところですが、まったく表見代理はありえないとなると、相手方としては法定代理人と取引する場合はちょっとリスクが増しますよね。
そして、現実にはあらかじめ想定できないような様々なケースがありえます。
このような事情から、やむをえず「なくはない」というような曖昧な結論になってしまうと考えられます。
ということなので、試験対策としては「法定代理において表見代理の成立はない」という選択肢が出てきたら、それは誤りとして選択することになります。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・任意代理と法定代理とその違い
・法定代理に表見代理は成立するのか?
・法定代理人に基本代理権は存在するのか?
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

任意代理と法定代理
代理は大きく分けて2種類あります。
それは任意代理と法定代理です。
【任意代理】
これは、委任による代理です。
つまり、本人が「あなたに代理を頼みます」といってお願いする代理です。
おそらく、一般的にイメージする代理は、こちらの任意代理になるかと思います。
「委任による代理=任意代理」
まずはここを押さえておいてください。
【法定代理】
これは、法律によって定められた代理です。
本人が「あなたに代理を頼みます」といってお願いする訳ではありません。
本人がお願いするまでもなく、法律によって定まる代理です。
最もわかりやすい法定代理は未成年者の親権者です。
通常、子供の親は子供の法定代理人になります。
でもこれって、子供が親に「代理頼みます」とお願いして成立するものではありませんよね?
「法律がそう決めた」からそうなるのです。
委任による代理=任意代理
法律によって定められた代理=法定代理
この基本はまず、確実に覚えておいていただければと存じます。
法定代理に表見代理は成立するのか
さて、ここでこんな疑問が湧きませんか?
それは、法定代理にも表見代理が成立するのか?です。
まず、表見代理が成立するには、前提として無権代理行為の存在がなければなりません。
となると、そもそも法定代理人の無権代理行為があり得るのか?となりますよね。
というのは、法定代理人は本人にお願いされてなるものではありません。
法律の定めによってなるものです。
つまり、普通に考えて「法定代理人に代理権がない状態」はありえないことになります。
すると、法定代理人の無権代理行為があり得るケースとして考えられるものがあるとすれば「代理権限を超えた」場合です。
代理権限を超えた場合とは、例えば「軽井沢の別荘の購入」という代理権を付与された代理人(任意代理人)が、那須の別荘を購入してしまうようなケースです。
このときの「軽井沢の別荘の購入」は基本代理権になります。
その基本代理権を超えた代理行為「那須の別荘の購入」が、代理権限を超えた無権代理行為となります。
つまり「代理権限を超えた無権代理行為」とは、前提となる基本代理権があって初めて成り立つものです。
このように考えていくと、法定代理に表見代理があり得るのか?という問題は、法定代理人に基本代理権というものが存在するのか?という問いへの結論次第ということになります。
法定代理人に基本代理権は存在するのか?
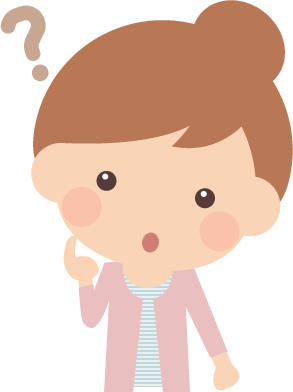
これは、実はハッキリと明確に結論づけられている訳ではありません。
なんじゃそれ?じゃあ結局どーなのよ!?
ですよね(笑)。
ただ一応、法定代理にも下記の規定、表見代理の3類系のうちの2つの適用はあるとされています。
民法110条(権限外の行為の表見代理)
民法112条(代理権消滅後の表見代理)
先ほどまで解説して参りました内容は、法定代理における「権限外の行為の表見代理」です。
しかし、どうやら民法112条「代理権消滅後の表見代理」の方についても、法定代理での適用はあるようです。
また、判例では「法定代理においても、表見代理の成立はなくはない」というように結論づけています。
結局どっちやねん!
ツッコミたくなりますよね(笑)。
しかし、このような曖昧な結論というのは、民法の学習をしていると結構よく出てきます。
ですので強引に慣れていってください(笑)。
まあ、なぜこのような曖昧な結論になってしまうかの理由を考えると、それは「法定代理には本人の帰責性がありえない」ということが言えます。
法定代理人は本人が選んでお願いしている訳ではないので「そんなヤツを代理人に選んでしまった本人も悪い」という理屈が成り立たないのです。
表見代理は、そのような本人の帰責事由を成立要件として、相手方を保護し、取引の安全性を確保する制度です。
ですので、本来の理屈としては、法定代理には表見代理は成立しないとなるところですが、まったく表見代理はありえないとなると、相手方としては法定代理人と取引する場合はちょっとリスクが増しますよね。
そして、現実にはあらかじめ想定できないような様々なケースがありえます。
このような事情から、やむをえず「なくはない」というような曖昧な結論になってしまうと考えられます。
ということなので、試験対策としては「法定代理において表見代理の成立はない」という選択肢が出てきたら、それは誤りとして選択することになります。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!
【代理の超基本】表見&無権代理とは/3つの表見代理とは/表見代理に転得者が絡んだ場合をわかりやすく解説!
-
 【無権代理行為の追認】催告権と取消権とは?その違いとは?/法定追認をわかりやすく解説!
【無権代理行為の追認】催告権と取消権とは?その違いとは?/法定追認をわかりやすく解説!
-
 【無権代理人の責任はかなり重い】無権代理人に救いの道はないのか?わかりやすく解説!
【無権代理人の責任はかなり重い】無権代理人に救いの道はないのか?わかりやすく解説!
-
 【代理行為の瑕疵】代理人&本人の善意・悪意について/特定の法律行為の委託とは?わかりやすく解説!
【代理行為の瑕疵】代理人&本人の善意・悪意について/特定の法律行為の委託とは?わかりやすく解説!
-
 【代理人の権限濫用】それでも代理は成立している?裁判所の使う類推適用という荒技をわかりやすく解説!
【代理人の権限濫用】それでも代理は成立している?裁判所の使う類推適用という荒技をわかりやすく解説!
-
 【代理人の行為能力】表現代理人・無権代理人が配偶者の場合をわかりやすく解説!
【代理人の行為能力】表現代理人・無権代理人が配偶者の場合をわかりやすく解説!
-
 【任意代理と法定代理】法定代理に表見代理はあり得るのか?わかりやすく解説!
【任意代理と法定代理】法定代理に表見代理はあり得るのか?わかりやすく解説!
-
 【復代理】任意代理人と法定代理人の場合では責任の度合いが違う/代理を丸投げできるケースとは?わかりやすく解説!
【復代理】任意代理人と法定代理人の場合では責任の度合いが違う/代理を丸投げできるケースとは?わかりやすく解説!
-
 【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!
【無権代理と相続】無権代理人が本人を&本人が無権代理人を相続した場合/本人が追認拒絶後に死亡した場合/相続人が複数の場合/相手方ができることをわかりやすく解説!
-