
▼この記事でわかること
・留置権の基本と成立要件と対抗力
・留置権の性質
・不動産での留置権
・他人物売買のケース
・目的物の賃貸と留置権の消滅
・盗っ人に留置権はあるのか
・物と債権の額が違う場合
・不動産賃貸借の場合の留置権
・建物買取請求権と留置権
・消滅時効と果実と費用償還請求権
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

留置権の基本
留置権は、法定担保物権です。
法定担保物権とは、当事者の意思とは関係なしに、法律の定めによって自動的に成立します。
ですので、約定担保物権である抵当権や質権のように「設定契約」というものはありません。※
※この場合の「法定」とは「法律の定めによって」ということ。「約定」とは「契約の定めによって」ということ。
また、物上保証もなく、将来債権につき留置権が成立することもありません。(弁済期の到来が成立要件)
以上の事を前提として、ここからは事例と共に、わかりやすく具体的に、留置権について解説して参ります。
事例1
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、AはBに時計の引渡しを求めたが、修理代金がまだ未払いだった。
さて、この事例1で、まだ修理代金の支払い受けていない時計屋BはAからの時計の引渡し請求を拒めるでしょうか?
結論。
時計屋BはAからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
そして時計屋Bは「修理代金の支払いを受けるまでこの時計は返さん!」と主張することができます。
これが留置権です。
このように、留置権は、担保目的物(時計)を占有することにより、被担保債権(修理代金債権)の弁済を心理的に強制することに意義があります。
なお、留置権についての基本的な民法の条文はこちらになります。
(留置権の内容)
民法295条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
留置権の要件
留置権は、次の3要件が揃ったとき、法律の規定により出現します。
1・他人の物の占有
2・物に関して生じた債権
3・弁済期
以上の3要件、つまり、これらの3つの事実状態が揃ったとき、留置権はその姿を現します。
では、事例1に当てはめてみましょう。
1・時計屋BによるA所有時計の占有
2・時計の修理代金債権
3・修理代金の弁済期
1と2は読んだとおりで、3の修理代金の弁済期は、通常、修理完了と同時に弁済期にあるということで、3要件すべて揃っています。
よって、時計屋Bは留置権を主張できるのです。
留置権と対抗力
事例2
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、修理代金がまだ未払いのまま、AはCにその時計を売却すると、CはBにその時計の引渡しを求めた。
続いてはこちらです。
これは、時計屋Bに修理に出していた時計を、そのままAはCに売却した、という話です。
さて、ではこの事例2で、時計屋BはCからの時計の引渡しを拒めるでしょうか?
結論。
時計屋BはCからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
時計屋Bは、事例1の場合と同様に「修理代金の支払いを受けるまでこの時計は返さん!」と主張することができます。
そしてこれには「第三者への対抗要件」というものは必要ありません。
なぜなら、そもそも対抗力のない留置権など存在しないからです。
留置権の場合、占有が「存続要件」です。
つまり、目的物の占有があれば留置権は存続し、留置権が存続する限り対抗力も失われません。
逆に、占有を失ってしまうと、留置権そのものが消滅してしまいます。
なので、事例1と2のどちらでも、時計屋BがAなりCなりに時計を返還してしまうと、留置権は消滅してしまいます。
こうなってしまうと、BからAorCへの返還は「侵奪」ではないので、占有回収の訴えの提起もできませんし、Bは時計を取り戻すことができなくなります。
となると、修理代金の回収はより難しいものとなってしまいます。
【補足1】
留置権は不動産にも成立します。
この場合も、第三者への対抗は「占有」であり「留置権の登記」なるものは存在しません。
【補足2】留置権と同時履行の抗弁権
ところで、留置権は、同時履行の抗弁権と似ていますよね。
例えば、事例1の時計屋Bは、時計の引渡しを求めるAに対し同時履行の抗弁権を主張することもできます。
AB間には時計の修理契約があるからです。
しかし、当然のことながら、留置権と同時履行の抗弁権には違いがあります。
事例2のケースでは、時計屋Bは時計の引渡しを求めるCに対し同時履行の抗弁権は主張できません。
BC間には契約関係がないからです(Cと契約関係にあるのはA)。
ですが、留置権の主張はできますよね。
留置権は物権です。
物権とは物に対する支配権であり、物権である留置権には対世効があります。
対世効があるということは、日本中のすべての人に主張できるのです。
このように、留置権と同時履行の抗弁権は似て非なるもので「その専用分野が少し違う」ということです。
留置権の性質
留置権は担保物権の一種ですが、担保物権としては特異な存在です。
というのは、担保物権の性質として挙げられる次の5つ
1・付従性
2・随伴性
3・不可分性
4・物上代位性
5・優先弁済権
この内の4と5が留置権の場合は存在しません。
この5つは、他の担保物権である「抵当権」「質権」「先取特権」にはもれなくすべて備わっているのにです。(確定前根抵当権には1と2は存在しない)
以上のことから、留置権は、目的物(占有する物)をずっと持っているだけの担保物権と言えます。
目的物の競売は可能ですが(形式競売)、5の優先弁済権はありません。
また、4の目的物の価値変形物への代位もできないのです。
(価値変形物についての詳しい解説は「【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!」をご覧ください)
したがいまして、留置権者の利益のためには、目的物をずっと持っているのが一般論としては正解です。
【補足】留置権はチート!?担保物権最強説
実は、留置権は「事実上の優先弁済権がある」と評価されるほどのツワモノです。
その評価の理由はこうです。
目的物が動産の場合、留置権を行使すると、なんと他の債権者の競売手続が頓挫します。
また、不動産の場合は、競売手続は進みますが、なんと買受人に留置権を対抗することができます。
留置権には優先弁済権はありませんが、それは留置権者が目的物を競売した場合にその代価(競売代金)に対する優先権がない、という意味に過ぎません。
留置権者は弁済を受けるまではいつまでも目的物を「留置」できます。
つまり、留置権者のもとに留め置き続けられるのです。
他者による競売手続の中で消えることもありません。
このように、留置権は目的物を持っているかぎりは最強の担保権と言えるかもしれません。
民事執行法における最強の物権と言われることもあるぐらいですから。
まさに、チート物権。(「チート物権」は筆者による呼称なのであしからず)
不動産での留置権

事例3
Aは自己所有の甲建物をBに売却し引き渡した。さらに、AはCに甲建物を二重譲渡し、その旨の登記をした。その後、CはYに対し所有権に基づき目的建物の明け渡しを請求した。
さて、この事例3は不動産の二重譲渡のケースになります。
Aが甲建物をBに売却し引渡しもしたが、さらにCにも甲建物を譲渡し(二重譲渡)、その登記もしてしまい、甲建物はBのもとにあるが登記はCにある、という状況で、CがBに対して甲建物の明け渡しを請求した、という話です。
売主
A
売却 ↙ ↘ 二重譲渡
甲建物 登記
B ← C
明渡し請求
ではこの事例3で、Bは売主Aに対するに損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を根拠に、Cからの明渡し請求を拒めるでしょうか?
わかりやすく言うと、BはCに対し「Aから損害賠償金をもらうまで甲建物は明け渡さん!」と主張できるのか?ということです。
この問題を考える上で、まず確認しなければならない事があります。
それは、留置権が出現するための3要件が揃っているのかどうか、です。
留置権が出現するための3要件はこちらですよね。
1・他人の物の占有
2・物に関して生じた債権
3・弁済期
では、1から順に確認しながら解説して参ります。
まず1の「他人の物の占有」は、Bは甲建物を占有しているので問題なく満たしています。
続いて2の「物に関して生じた債権」ですが、損害賠償請求権は「甲建物に関して」の発生したものと言えそうです。
最後に3の「弁済期」は、事例3の二重譲渡の場合、Cに登記が入った瞬間にAのBへの履行不能が確定し、そこで民法415条に基づく損害賠償請求権が発生します。それに伴い弁済期も発生します。
以上、3要件を満たしたことにより、最強のチート物権「留置権」の降臨となり、Bの主張も通りそうですが...
結論。
なんと、BはCからの明渡し請求を拒むことはできません。理由は、留置権の出現を認められないからです。
これは判例でこのように結論付けられています。
判例は、BのAに対する損賠賠償請求権を、2の「物に関して生じた債権」と認めませんでした。
小難しい言い方で「物と債権に牽連性がない」ということです。
牽連性とは、簡単に言えば「繋がり」という意味です。
要するに判例では「損賠賠償金を支払うべきは者はAなのだから、それを盾にBがC相手に甲建物を引き渡さないのは違くね?」と言っているのです。
したがいまして、事例3では留置権出現の3要件が満たされず、結果、Bが留置権を主張することはできません。
この結論は、よくよく考えればもっともです。
というのも、Bが甲建物を「明け渡さん!」と留置したところで、それが「心理的に売主Aの損害賠償金の支払いを強制する効果」を発揮することに関係しませんよね。
また、そもそもこの事例3は、民法177条による「登記したモン勝ち!」のリングなんです。
なので、もしここで、このようなBの留置権の主張を認めてしまうと、民法177条の意味がなくなってしまいかねません。
他人物売買のケース
事例4
AはB所有の甲建物を自己のものと偽りCに売却し引き渡した。その後、BはCに対し甲建物の明け渡しを請求した。
さて、今度は他人物売買のケースです。
ではこの事例4で、Cは売主Aの債務不履行による損害賠償請求権をもって、留置権を主張してBからの甲建物の明渡し請求を拒めるでしょうか?
売主
A
(甲建物) ↘ 他人物売買
真の所有者 甲建物
B → C
明渡し請求
↑拒める?
結論。
CはBからの甲建物の明渡し請求を拒むことはできません。
今度の事例4も、前述の事例3と理屈は一緒です。
これも判例で「物と債権に牽連性がない」という理由で、Cの留置権を認めなかったのです。
そもそも、Cの「損害賠償しろ」という請求の矢印はAに向けたもので、Bの「甲建物を引き渡せ!」という請求の矢印はCに向けたものなので、請求の矢印が方向が向き合っていません。
要するに、留置権を適用させる局面ではないということです。
【補足】
もし、「A→B→C」と甲建物が転売され、Bはまだ売買代金未払い、甲建物はまだAのもとにある、というケースで、CがAに対し建物の引渡し請求をした場合は、AはBの売買代金未払いを理由に甲建物を留置することができます。
この場合は、AのBへの売買代金請求の矢印と、CのBへの引渡請求の矢印が、ちゃんと向き合っているので「物と債権に牽連性あり」ということで、Aの留置権が認められます。
オマケ
賃貸借契約の目的物である土地が譲渡された場合に、対抗力のない賃借人が留置権を主張して建物を留置することはできません。
そもそも賃借権は、留置権の成立要件である「物=土地に関する債権」ではなく「土地を目的とする債権」なのです。
目的物の賃貸と留置権の消滅
事例5
Aはその所有する時計を時計屋Bに引き渡し修理してもらった。その後、無断でBはCにその時計を賃貸した。
さて、今度の事例は、所有者Aに無断で時計屋Bがその時計を第三者Cに賃貸してしまった、という話です。
ではこの事例5で、時計屋Bの留置権は消滅するでしょうか?
まず、留置権者には善管注意義務があります。
つまり、留置権者は留め置く他人の物を大事に扱わなければならないという事です。
したがって、時計屋Bが無断で時計をCに賃貸することは、認められることではありません。
この点について、民法では次のように規定されています。
(留置権者による留置物の保管等)
民法298条2項
債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
上記、民法298条2項条文にハッキリと「承諾を得なければ~できない」と書いてありますよね。(上記条文中の「債務者」は事例5のA)
となると、時計屋BがAに無断で時計を賃貸して、Bの留置権は消滅したのでしょうか?
実はこれが、それによって自動的に消滅するという訳ではないのです。
少々ややこしいのですが、民法でこのような場合「債務者は留置権の消滅を請求できる」と規定しています。
したがいまして、結論。
時計屋BがAに無断でCに時計を賃貸しても、それでBの留置権は自動的に消滅はしません。
AがBに留置権の消滅を請求すれば消滅します。
少しややこしく感じるかと思いますが、これが正確な結論になります。
もし、試験等で事例5のようなケースで「民法298条2項違反で留置権は自動的に消滅する」という肢があれば、それは誤りになります。
あくまで、債務者(事例5のA)が消滅請求をして留置権は消滅します。
なお、債務者に実害が生じたかどうかは消滅請求の要件にはなりません。
実害がなくとも「無断賃貸」という留置権者の義務違反のペナルティとして、債務者は留置権者に留置権の消滅請求ができます。
盗っ人に留置権はあるのか

続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例6
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。その後、Cがその時計を盗んで修理した。
今度は、時計屋BがAから修理のために預かった時計がCによって盗まれ、その時計を盗っ人Cが修理した、というちょっとオモシロいケースです。
さて、この事例6で、盗っ人Cは「修理代金を払うまで時計を渡さない!」と留置権を主張できるでしょうか?
結論。
盗っ人Cは留置権を主張することができません。
これは普通に考えて当然の結論ですよね。
ただ、時計の修理代金は必要費にあたるので、悪意占有者である盗っ人Cにも「回復者への償還請求権」すなわち「修理代金を払え!という債権はあります。
それに、留置権成立の3要件を満たしているようにも見えます。
したがって、Cの主張にも一定の合理性があり、お門違いという訳でもないんです。
しかし、民法では次のように規定しています。
(留置権の内容)
民法295条
前項の(3要件が揃えば留置権が成立するという)規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
盗みは民法295条条文中の「不法行為」に含まれます。
したがいまして、盗っ人Cの留置権は成立しません。結果、留置権の主張もできないのです。
盗っ人に留置権はないということです。
【補足】
賃料不払により賃貸借契約を解除された建物賃借人が、占有権限のないことを知りつつ、解除後に費やした有益費の償還請求権に基づいて、建物の留置権を主張する事はできません。
これは、そうなった場合の賃借人が自らを不法占拠者と知っている以上、その占有が不法行為によって始まったのと同視されるからです。
一方で、解除前に費やした有益費の償還請求権に基づく留置権の主張は可能です。
これは、占有のはじめに適法な賃貸借契約があったからです。
物と修理代金が違う場合
事例7
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、AはBに時計の引渡しを求めたが、修理代金がまだ未払いだった。なお、時計は30万円で、修理代金は1万円である。
さて、今度の事例では考えるべき問題が今までとは違います。
まず前提として、時計屋Bは留置権を主張してAからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
これは本記事の最初の事例1とまったく一緒です。
本題はここからです。
時計の価格は30万円です。
しかし、修理代は1万円です。
はたして、時計屋Bは「1万円の修理代金」の債権をもって「30万円の時計」の全部を留置できるのでしょうか?
結論。
時計屋Bは時計の全部を留置できます。
これは、担保権の不可分性によるものです。
民法の規定はこちらです。
(留置権の不可分性)
民法296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
不可分とは「分けられない」という意味で、不可分性という性質は抵当権や質権などすべての担保権に共通する性質です。
その担保権である留置権も例外ではなく、分けることはできません。
なので、たとえAが1万円の修理代のうち8000円を支払った段階であっても、時計屋Bは30万円の時計全部の留置ができます。
しかし、留置権は法定担保物権であるために特有の問題が生じます。
例えば、時計に質権を設定するのであれば「30万円の時計なので20万円まで融資しましょう」というように、担保目的物(質物)の価格と被担保債権の額(融資する額)が釣り合うのが普通です。
ところが、留置権は法律の規定により、要件を満たせば当事者の意思とは無関係に自動的に成立してしまいます。
なので、事例7のような、担保権成立の当初から、担保目的物の価格と被担保債権の額がまったく釣り合わないことがよくあるのです。
でもこうなると、債務者に酷な感じがしますよね。
そこで民法では、留置権については次の特別な規定を置いて対処しています。
(担保の供与による留置権の消滅)
民法301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
この民法301条の意味は、事例7にあてはめるとこうです。
債務者Aは1万円の修理費に相応の、別の担保を差し出すことで、時計の方は返してもらうことができます。
例えば、Aが別の1万円の時計を担保として時計屋Bに差し出せば、30万円の時計の方は返してもらうことができます。
ただし、この民法301条の留置権の消滅請求は、債権者の承諾を要します。
その理由は、債務者が差し出す別の担保が、本当に相応のものかが一概には分からないからです。
つまり、Aが別の1万円の時計を担保として差し出しても、それが本当に修理費1万円に釣り合うかどうか一概には判断できないということです。
また、その担保に相応性があるにもかかわらず債権者が承諾しない場合は、承諾に代わる判決をもらい留置権を消滅させることることができます。
【補足】
留置物の一部返還
例えば、宅地造成業者Aが地主Bの依頼を受けて10区画の宅地を造成して、その総工費が1億円(1区画あたり1000万円)だったとします。
そして、業者Aが工事代金が支払われる前に4区画を地主Bに引き渡したが、その後、地主Bの代金の支払いが滞った場合、Aは工事費全額分の「1億円払え!」の債権をもって残りの6区画を留置できるのでしょうか?
それとも6区画分の工事費「6000万円払え!」の債権をもって6区画を留置するのでしょうか?
結論。
このケースでは、留置権の不可分性の問題として、業者Aは総代金債権「1億円払え!」をもって残りの6区画に留置権の行使ができます。(判例)
不動産賃貸借の場合の留置権
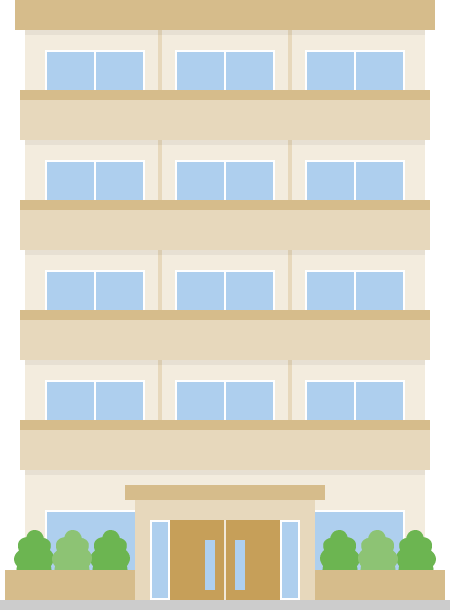
ここからは、不動産賃貸借における留置権の問題について解説して参ります。
まずは事例をご覧ください。
事例8
AはBから建物を賃借した。賃貸借契約終了後、Aは建物について支出した有益費の償還請求に基づき建物を留置している。
これは、賃借人Aが賃貸人Bに対し「有益費払うまで明け渡さん!」と建物を留置している、という話です。(有益費について詳しい解説は「【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
さて、ではこの事例8で、AはBに無断で建物に住んでいて良いものなのでしょうか?
まず、賃借人Aは賃貸借契約終了前に支出した有益費について建物を留置しています。そして、建物に住むということは、建物を使用することです。
あれ?確か留置物を債務者に無断で使用することはできないんじゃ...
そうなんです。
しかし、民法298条2項ただし書きには「その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない」とあります。
これはつまり、留置権者は、留置する物の保存に必要な使用なら債務者に承諾なしでもOKということです。
例えば、何かの機械が留置物の場合、放置しておくとサビついてダメになったりします。
なので、物の保存としてもはむしろ使用した方が良いですよね。
建物の場合も一緒です。
空き家にした方がむしろ痛みが激しいのです。
以上のことから、判例では、留置物である建物に「居住すること」は保存に必要な行為だとしています。
したがいまして、結論。AはBに無断で留置物の建物に住むことができます。
留置物の賃料の問題
賃借人Aは建物を留置している間、賃貸人Bに無断で留置物の建物に住むことができるわけですが、家賃を払わず無料で住んでしまって良いものなのでしょうか?
それはもちろん、そんな訳にはいきません。
賃貸借契約が終了したからといって、元々家賃を払って住んでいた建物にタダで居座ることはできません。
ただ、この点については次のような法律構成をとります。
「Aには賃料相当額の使用利益という不当利得がある」
つまり、それまでに毎月支払っていた賃料と同額の不当利得が月々で発生し、その返還義務をAはBに対して負う、ということです。
もっと簡単に言えば「契約終了後も建物を留置して住むのであれば家賃相当額を払い続けてください」となりますが、あくまでAB間の賃貸借契約は終了しているので「不当利得」という法律構成をとることになるのです。
あれ?でもAがそのまま住み続けて家賃相当額を払い続けると、その金額が、そもそもの「建物を留置する発端」となった「有益費の償還請求額」を超えてしまうんじゃ...?
そうなんです。
なので、その金額が追いついた時点で、建物所有者Bからの相殺の主張があれば、有益費の償還請求権が消滅し、(被担保債権の存在が前提である担保権の付従性により)それにともなって留置権の消滅、という流れになります。
【補足】
造作買取請求権による建物の留置はできる?
造作とは、家主の承諾の下に建物に付加した畳や建具のことです。
賃貸借契約終了時に、賃借人はオーナー(家主)にこれを買い取れと迫ることができます。
これが造作買取請求権です。
さて、ではこの造作買取請求権に基づき建物を留置することはできるのでしょうか?
ここでの問題は、造作自体だけでなく、建物も留置できるのか?です。
結論。
判例により「建物と造作は別物だ」ということで、建物の留置はできません。
造作に関する債権で建物を留置するのは「物(建物)と債権(造作買取請求権)に牽連性がない」ので無理だ、ということです。
理屈として、造作自体の留置はできますが、建物に付加してしまっているので、現実にはそれも難しいでしょう。
建物買取請求権と留置権

続いてはこちらの事例をご覧ください。
事例9
Aの所有地に借地権の設定を受けたBは、そこに建物を建て所有していた。その後、借地権の期間満了に基づき、AはBに土地の明け渡しを求めた。
これは、地主Aから借りた土地に建物を建てて所有しているBが、借地契約の期間満了によりAから土地の明け渡しを求められた、という話です。
さて、この事例9で、Bが建物買取請求権を行使した場合、Bはその土地を留置できるでしょうか?
もっと簡単に言えば、借地人Bは「オマエが建物を買い取るまで土地を明け渡さん!」と地主Aに対し留置権の主張ができるのか?ということです。
結論。
借地人Aは地主Bに対し、建物買取請求権に基づき土地の留置ができます。
つまり、Bは「オマエが建物を買い取るまで土地を明け渡さん!」と地主Aに対し留置権の主張ができます。
建物買取請求権は建物に関する債権なのになぜ土地を留置できるのか?
まず、建物買取請求権自体は借地借家法13条1項に定められた借地人の権利です。
したがって、「建物を買い取れ!」と迫って建物を留置することは何も問題ないですよね?
しかし、建物買取請求権は建物に関する債権なので「物(土地)と債権(建物買取請求権)に牽連性がない」はずです。
なので、土地の留置はできないはずです。
ただ、建物だけ切り離して引っ越した上で土地だけ留置することなど不可能ですよね?
なので、もし原理原則に従い建物は留置できて土地は留置できないとなると、建物買取請求権の行使が事実上不可能な権利として何の意味もないものとなってしまいます。
元々、建物買取請求権は借地借家法による借り手保護政策の一環です。
これでは何の借り手の保護にもなりません。
そこで、判例では、建物を留置できる反射的効果として、土地の留置もできるとしました。
ただし、タダでという訳にはいきません。
借地人は地代相当額を不当利得として地主に返還することになります。
ここの理屈は、事例8の有益費の償還請求権のケースと一緒です。
留置権と消滅時効と果実
【消滅時効の問題】
民法300条では、留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を妨げないと規定しています。
どういう意味かというと、留置権を行使したからといって被担保債権の時効の進行は止められない、ということです。
つまり、「金払うまで物は渡さん!」と留置権を行使しても「金払え!」という債権の時効の進行には影響はないのです。
なので、いつまでも物を留置しているからといってボヤボヤしていると、肝心の「金払え!」という被担保債権が時効で消滅してしまえば、それに伴い留置権も消滅してしまいます。
なお、留置権は占有を伴う権利なので、留置権それ自体が時効により消滅することはあり得ません。
では、訴訟上、留置権を行使した場合はどうなるでしょう?
例えば、所有者からの目的物の返還請求訴訟で、被告側が留置権を主張して返還を拒んだ場合です。
この場合は、訴訟上、留置権を主張しているので、被担保債権の行使と認められ消滅時効はストップします。
ただ、これは催告としての効果であり、訴訟の終結後6ヶ月以内に、被担保債権に基づき支払請求訴訟を提起するなどの手段をとらなければ、時効の更新にはなりません。
【果実の問題】
民法297条では、留置権者は留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができると規定しています。
どういう意味かというと、留置物から生じる果実については、留置権者に優先弁済権があるということです。
留置物を競売した場合、留置権者に優先弁済権はありませんが、留置物から生じる果実に対する優先弁済権はあるのです。
この点はご注意ください。
補足:留置権者による費用の償還請求権
最後に、留置権者による費用の償還請求権について、簡単に解説します。
占有と償還請求については民法196条に一般則があり、民法299条には留置権についての特則があります。
これをまとめると、留置権については次のようになります。
必要費→償還請求できる
有益費→価格の増加が現存する限り所有者の選択に従い、その金額または増加額を償還させることができる(所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる))
通常の占有のケースでは、占有者が果実を取得した場合に通常の必要費を占有者が負担します。
しかし、留置権の場合、果実は弁済にあてられるので、通常の必要費も所有者の負担となります。
また、通常の占有のケースでは、有益費につき裁判所による期限の許与は悪意の占有者のみ認められていますが、留置権の場合は、そもそも他人の物を占有しているのは明らかなので、そのような制限はなく一律に認められています。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・留置権の基本と成立要件と対抗力
・留置権の性質
・不動産での留置権
・他人物売買のケース
・目的物の賃貸と留置権の消滅
・盗っ人に留置権はあるのか
・物と債権の額が違う場合
・不動産賃貸借の場合の留置権
・建物買取請求権と留置権
・消滅時効と果実と費用償還請求権
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

留置権の基本
留置権は、法定担保物権です。
法定担保物権とは、当事者の意思とは関係なしに、法律の定めによって自動的に成立します。
ですので、約定担保物権である抵当権や質権のように「設定契約」というものはありません。※
※この場合の「法定」とは「法律の定めによって」ということ。「約定」とは「契約の定めによって」ということ。
また、物上保証もなく、将来債権につき留置権が成立することもありません。(弁済期の到来が成立要件)
以上の事を前提として、ここからは事例と共に、わかりやすく具体的に、留置権について解説して参ります。
事例1
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、AはBに時計の引渡しを求めたが、修理代金がまだ未払いだった。
さて、この事例1で、まだ修理代金の支払い受けていない時計屋BはAからの時計の引渡し請求を拒めるでしょうか?
結論。
時計屋BはAからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
そして時計屋Bは「修理代金の支払いを受けるまでこの時計は返さん!」と主張することができます。
これが留置権です。
このように、留置権は、担保目的物(時計)を占有することにより、被担保債権(修理代金債権)の弁済を心理的に強制することに意義があります。
なお、留置権についての基本的な民法の条文はこちらになります。
(留置権の内容)
民法295条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
留置権の要件
留置権は、次の3要件が揃ったとき、法律の規定により出現します。
1・他人の物の占有
2・物に関して生じた債権
3・弁済期
以上の3要件、つまり、これらの3つの事実状態が揃ったとき、留置権はその姿を現します。
では、事例1に当てはめてみましょう。
1・時計屋BによるA所有時計の占有
2・時計の修理代金債権
3・修理代金の弁済期
1と2は読んだとおりで、3の修理代金の弁済期は、通常、修理完了と同時に弁済期にあるということで、3要件すべて揃っています。
よって、時計屋Bは留置権を主張できるのです。
留置権と対抗力
事例2
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、修理代金がまだ未払いのまま、AはCにその時計を売却すると、CはBにその時計の引渡しを求めた。
続いてはこちらです。
これは、時計屋Bに修理に出していた時計を、そのままAはCに売却した、という話です。
さて、ではこの事例2で、時計屋BはCからの時計の引渡しを拒めるでしょうか?
結論。
時計屋BはCからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
時計屋Bは、事例1の場合と同様に「修理代金の支払いを受けるまでこの時計は返さん!」と主張することができます。
そしてこれには「第三者への対抗要件」というものは必要ありません。
なぜなら、そもそも対抗力のない留置権など存在しないからです。
留置権の場合、占有が「存続要件」です。
つまり、目的物の占有があれば留置権は存続し、留置権が存続する限り対抗力も失われません。
逆に、占有を失ってしまうと、留置権そのものが消滅してしまいます。
なので、事例1と2のどちらでも、時計屋BがAなりCなりに時計を返還してしまうと、留置権は消滅してしまいます。
こうなってしまうと、BからAorCへの返還は「侵奪」ではないので、占有回収の訴えの提起もできませんし、Bは時計を取り戻すことができなくなります。
となると、修理代金の回収はより難しいものとなってしまいます。
【補足1】
留置権は不動産にも成立します。
この場合も、第三者への対抗は「占有」であり「留置権の登記」なるものは存在しません。
【補足2】留置権と同時履行の抗弁権
ところで、留置権は、同時履行の抗弁権と似ていますよね。
例えば、事例1の時計屋Bは、時計の引渡しを求めるAに対し同時履行の抗弁権を主張することもできます。
AB間には時計の修理契約があるからです。
しかし、当然のことながら、留置権と同時履行の抗弁権には違いがあります。
事例2のケースでは、時計屋Bは時計の引渡しを求めるCに対し同時履行の抗弁権は主張できません。
BC間には契約関係がないからです(Cと契約関係にあるのはA)。
ですが、留置権の主張はできますよね。
留置権は物権です。
物権とは物に対する支配権であり、物権である留置権には対世効があります。
対世効があるということは、日本中のすべての人に主張できるのです。
このように、留置権と同時履行の抗弁権は似て非なるもので「その専用分野が少し違う」ということです。
留置権の性質
留置権は担保物権の一種ですが、担保物権としては特異な存在です。
というのは、担保物権の性質として挙げられる次の5つ
1・付従性
2・随伴性
3・不可分性
4・物上代位性
5・優先弁済権
この内の4と5が留置権の場合は存在しません。
この5つは、他の担保物権である「抵当権」「質権」「先取特権」にはもれなくすべて備わっているのにです。(確定前根抵当権には1と2は存在しない)
以上のことから、留置権は、目的物(占有する物)をずっと持っているだけの担保物権と言えます。
目的物の競売は可能ですが(形式競売)、5の優先弁済権はありません。
また、4の目的物の価値変形物への代位もできないのです。
(価値変形物についての詳しい解説は「【抵当権の効力と物上代位の基本と要件】法定果実(家賃)や転貸賃料債権へ物上代位できるのか?わかりやすく解説!」をご覧ください)
したがいまして、留置権者の利益のためには、目的物をずっと持っているのが一般論としては正解です。
【補足】留置権はチート!?担保物権最強説
実は、留置権は「事実上の優先弁済権がある」と評価されるほどのツワモノです。
その評価の理由はこうです。
目的物が動産の場合、留置権を行使すると、なんと他の債権者の競売手続が頓挫します。
また、不動産の場合は、競売手続は進みますが、なんと買受人に留置権を対抗することができます。
留置権には優先弁済権はありませんが、それは留置権者が目的物を競売した場合にその代価(競売代金)に対する優先権がない、という意味に過ぎません。
留置権者は弁済を受けるまではいつまでも目的物を「留置」できます。
つまり、留置権者のもとに留め置き続けられるのです。
他者による競売手続の中で消えることもありません。
このように、留置権は目的物を持っているかぎりは最強の担保権と言えるかもしれません。
民事執行法における最強の物権と言われることもあるぐらいですから。
まさに、チート物権。(「チート物権」は筆者による呼称なのであしからず)
不動産での留置権

事例3
Aは自己所有の甲建物をBに売却し引き渡した。さらに、AはCに甲建物を二重譲渡し、その旨の登記をした。その後、CはYに対し所有権に基づき目的建物の明け渡しを請求した。
さて、この事例3は不動産の二重譲渡のケースになります。
Aが甲建物をBに売却し引渡しもしたが、さらにCにも甲建物を譲渡し(二重譲渡)、その登記もしてしまい、甲建物はBのもとにあるが登記はCにある、という状況で、CがBに対して甲建物の明け渡しを請求した、という話です。
売主
A
売却 ↙ ↘ 二重譲渡
甲建物 登記
B ← C
明渡し請求
ではこの事例3で、Bは売主Aに対するに損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を根拠に、Cからの明渡し請求を拒めるでしょうか?
わかりやすく言うと、BはCに対し「Aから損害賠償金をもらうまで甲建物は明け渡さん!」と主張できるのか?ということです。
この問題を考える上で、まず確認しなければならない事があります。
それは、留置権が出現するための3要件が揃っているのかどうか、です。
留置権が出現するための3要件はこちらですよね。
1・他人の物の占有
2・物に関して生じた債権
3・弁済期
では、1から順に確認しながら解説して参ります。
まず1の「他人の物の占有」は、Bは甲建物を占有しているので問題なく満たしています。
続いて2の「物に関して生じた債権」ですが、損害賠償請求権は「甲建物に関して」の発生したものと言えそうです。
最後に3の「弁済期」は、事例3の二重譲渡の場合、Cに登記が入った瞬間にAのBへの履行不能が確定し、そこで民法415条に基づく損害賠償請求権が発生します。それに伴い弁済期も発生します。
以上、3要件を満たしたことにより、最強のチート物権「留置権」の降臨となり、Bの主張も通りそうですが...
結論。
なんと、BはCからの明渡し請求を拒むことはできません。理由は、留置権の出現を認められないからです。
これは判例でこのように結論付けられています。
判例は、BのAに対する損賠賠償請求権を、2の「物に関して生じた債権」と認めませんでした。
小難しい言い方で「物と債権に牽連性がない」ということです。
牽連性とは、簡単に言えば「繋がり」という意味です。
要するに判例では「損賠賠償金を支払うべきは者はAなのだから、それを盾にBがC相手に甲建物を引き渡さないのは違くね?」と言っているのです。
したがいまして、事例3では留置権出現の3要件が満たされず、結果、Bが留置権を主張することはできません。
この結論は、よくよく考えればもっともです。
というのも、Bが甲建物を「明け渡さん!」と留置したところで、それが「心理的に売主Aの損害賠償金の支払いを強制する効果」を発揮することに関係しませんよね。
また、そもそもこの事例3は、民法177条による「登記したモン勝ち!」のリングなんです。
なので、もしここで、このようなBの留置権の主張を認めてしまうと、民法177条の意味がなくなってしまいかねません。
他人物売買のケース
事例4
AはB所有の甲建物を自己のものと偽りCに売却し引き渡した。その後、BはCに対し甲建物の明け渡しを請求した。
さて、今度は他人物売買のケースです。
ではこの事例4で、Cは売主Aの債務不履行による損害賠償請求権をもって、留置権を主張してBからの甲建物の明渡し請求を拒めるでしょうか?
売主
A
(甲建物) ↘ 他人物売買
真の所有者 甲建物
B → C
明渡し請求
↑拒める?
結論。
CはBからの甲建物の明渡し請求を拒むことはできません。
今度の事例4も、前述の事例3と理屈は一緒です。
これも判例で「物と債権に牽連性がない」という理由で、Cの留置権を認めなかったのです。
そもそも、Cの「損害賠償しろ」という請求の矢印はAに向けたもので、Bの「甲建物を引き渡せ!」という請求の矢印はCに向けたものなので、請求の矢印が方向が向き合っていません。
要するに、留置権を適用させる局面ではないということです。
【補足】
もし、「A→B→C」と甲建物が転売され、Bはまだ売買代金未払い、甲建物はまだAのもとにある、というケースで、CがAに対し建物の引渡し請求をした場合は、AはBの売買代金未払いを理由に甲建物を留置することができます。
この場合は、AのBへの売買代金請求の矢印と、CのBへの引渡請求の矢印が、ちゃんと向き合っているので「物と債権に牽連性あり」ということで、Aの留置権が認められます。
オマケ
賃貸借契約の目的物である土地が譲渡された場合に、対抗力のない賃借人が留置権を主張して建物を留置することはできません。
そもそも賃借権は、留置権の成立要件である「物=土地に関する債権」ではなく「土地を目的とする債権」なのです。
目的物の賃貸と留置権の消滅
事例5
Aはその所有する時計を時計屋Bに引き渡し修理してもらった。その後、無断でBはCにその時計を賃貸した。
さて、今度の事例は、所有者Aに無断で時計屋Bがその時計を第三者Cに賃貸してしまった、という話です。
ではこの事例5で、時計屋Bの留置権は消滅するでしょうか?
まず、留置権者には善管注意義務があります。
つまり、留置権者は留め置く他人の物を大事に扱わなければならないという事です。
したがって、時計屋Bが無断で時計をCに賃貸することは、認められることではありません。
この点について、民法では次のように規定されています。
(留置権者による留置物の保管等)
民法298条2項
債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
上記、民法298条2項条文にハッキリと「承諾を得なければ~できない」と書いてありますよね。(上記条文中の「債務者」は事例5のA)
となると、時計屋BがAに無断で時計を賃貸して、Bの留置権は消滅したのでしょうか?
実はこれが、それによって自動的に消滅するという訳ではないのです。
少々ややこしいのですが、民法でこのような場合「債務者は留置権の消滅を請求できる」と規定しています。
したがいまして、結論。
時計屋BがAに無断でCに時計を賃貸しても、それでBの留置権は自動的に消滅はしません。
AがBに留置権の消滅を請求すれば消滅します。
少しややこしく感じるかと思いますが、これが正確な結論になります。
もし、試験等で事例5のようなケースで「民法298条2項違反で留置権は自動的に消滅する」という肢があれば、それは誤りになります。
あくまで、債務者(事例5のA)が消滅請求をして留置権は消滅します。
なお、債務者に実害が生じたかどうかは消滅請求の要件にはなりません。
実害がなくとも「無断賃貸」という留置権者の義務違反のペナルティとして、債務者は留置権者に留置権の消滅請求ができます。
盗っ人に留置権はあるのか

続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例6
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。その後、Cがその時計を盗んで修理した。
今度は、時計屋BがAから修理のために預かった時計がCによって盗まれ、その時計を盗っ人Cが修理した、というちょっとオモシロいケースです。
さて、この事例6で、盗っ人Cは「修理代金を払うまで時計を渡さない!」と留置権を主張できるでしょうか?
結論。
盗っ人Cは留置権を主張することができません。
これは普通に考えて当然の結論ですよね。
ただ、時計の修理代金は必要費にあたるので、悪意占有者である盗っ人Cにも「回復者への償還請求権」すなわち「修理代金を払え!という債権はあります。
それに、留置権成立の3要件を満たしているようにも見えます。
したがって、Cの主張にも一定の合理性があり、お門違いという訳でもないんです。
しかし、民法では次のように規定しています。
(留置権の内容)
民法295条
前項の(3要件が揃えば留置権が成立するという)規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
盗みは民法295条条文中の「不法行為」に含まれます。
したがいまして、盗っ人Cの留置権は成立しません。結果、留置権の主張もできないのです。
盗っ人に留置権はないということです。
【補足】
賃料不払により賃貸借契約を解除された建物賃借人が、占有権限のないことを知りつつ、解除後に費やした有益費の償還請求権に基づいて、建物の留置権を主張する事はできません。
これは、そうなった場合の賃借人が自らを不法占拠者と知っている以上、その占有が不法行為によって始まったのと同視されるからです。
一方で、解除前に費やした有益費の償還請求権に基づく留置権の主張は可能です。
これは、占有のはじめに適法な賃貸借契約があったからです。
物と修理代金が違う場合
事例7
Aはその所有する時計を修理してもらうため時計屋Bに引き渡した。修理終了後、AはBに時計の引渡しを求めたが、修理代金がまだ未払いだった。なお、時計は30万円で、修理代金は1万円である。
さて、今度の事例では考えるべき問題が今までとは違います。
まず前提として、時計屋Bは留置権を主張してAからの時計の引渡し請求を拒むことができます。
これは本記事の最初の事例1とまったく一緒です。
本題はここからです。
時計の価格は30万円です。
しかし、修理代は1万円です。
はたして、時計屋Bは「1万円の修理代金」の債権をもって「30万円の時計」の全部を留置できるのでしょうか?
結論。
時計屋Bは時計の全部を留置できます。
これは、担保権の不可分性によるものです。
民法の規定はこちらです。
(留置権の不可分性)
民法296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
不可分とは「分けられない」という意味で、不可分性という性質は抵当権や質権などすべての担保権に共通する性質です。
その担保権である留置権も例外ではなく、分けることはできません。
なので、たとえAが1万円の修理代のうち8000円を支払った段階であっても、時計屋Bは30万円の時計全部の留置ができます。
しかし、留置権は法定担保物権であるために特有の問題が生じます。
例えば、時計に質権を設定するのであれば「30万円の時計なので20万円まで融資しましょう」というように、担保目的物(質物)の価格と被担保債権の額(融資する額)が釣り合うのが普通です。
ところが、留置権は法律の規定により、要件を満たせば当事者の意思とは無関係に自動的に成立してしまいます。
なので、事例7のような、担保権成立の当初から、担保目的物の価格と被担保債権の額がまったく釣り合わないことがよくあるのです。
でもこうなると、債務者に酷な感じがしますよね。
そこで民法では、留置権については次の特別な規定を置いて対処しています。
(担保の供与による留置権の消滅)
民法301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
この民法301条の意味は、事例7にあてはめるとこうです。
債務者Aは1万円の修理費に相応の、別の担保を差し出すことで、時計の方は返してもらうことができます。
例えば、Aが別の1万円の時計を担保として時計屋Bに差し出せば、30万円の時計の方は返してもらうことができます。
ただし、この民法301条の留置権の消滅請求は、債権者の承諾を要します。
その理由は、債務者が差し出す別の担保が、本当に相応のものかが一概には分からないからです。
つまり、Aが別の1万円の時計を担保として差し出しても、それが本当に修理費1万円に釣り合うかどうか一概には判断できないということです。
また、その担保に相応性があるにもかかわらず債権者が承諾しない場合は、承諾に代わる判決をもらい留置権を消滅させることることができます。
【補足】
留置物の一部返還
例えば、宅地造成業者Aが地主Bの依頼を受けて10区画の宅地を造成して、その総工費が1億円(1区画あたり1000万円)だったとします。
そして、業者Aが工事代金が支払われる前に4区画を地主Bに引き渡したが、その後、地主Bの代金の支払いが滞った場合、Aは工事費全額分の「1億円払え!」の債権をもって残りの6区画を留置できるのでしょうか?
それとも6区画分の工事費「6000万円払え!」の債権をもって6区画を留置するのでしょうか?
結論。
このケースでは、留置権の不可分性の問題として、業者Aは総代金債権「1億円払え!」をもって残りの6区画に留置権の行使ができます。(判例)
不動産賃貸借の場合の留置権
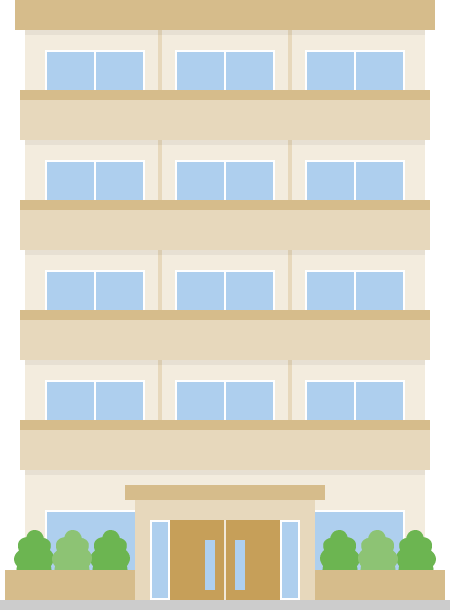
ここからは、不動産賃貸借における留置権の問題について解説して参ります。
まずは事例をご覧ください。
事例8
AはBから建物を賃借した。賃貸借契約終了後、Aは建物について支出した有益費の償還請求に基づき建物を留置している。
これは、賃借人Aが賃貸人Bに対し「有益費払うまで明け渡さん!」と建物を留置している、という話です。(有益費について詳しい解説は「【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
さて、ではこの事例8で、AはBに無断で建物に住んでいて良いものなのでしょうか?
まず、賃借人Aは賃貸借契約終了前に支出した有益費について建物を留置しています。そして、建物に住むということは、建物を使用することです。
あれ?確か留置物を債務者に無断で使用することはできないんじゃ...
そうなんです。
しかし、民法298条2項ただし書きには「その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない」とあります。
これはつまり、留置権者は、留置する物の保存に必要な使用なら債務者に承諾なしでもOKということです。
例えば、何かの機械が留置物の場合、放置しておくとサビついてダメになったりします。
なので、物の保存としてもはむしろ使用した方が良いですよね。
建物の場合も一緒です。
空き家にした方がむしろ痛みが激しいのです。
以上のことから、判例では、留置物である建物に「居住すること」は保存に必要な行為だとしています。
したがいまして、結論。AはBに無断で留置物の建物に住むことができます。
留置物の賃料の問題
賃借人Aは建物を留置している間、賃貸人Bに無断で留置物の建物に住むことができるわけですが、家賃を払わず無料で住んでしまって良いものなのでしょうか?
それはもちろん、そんな訳にはいきません。
賃貸借契約が終了したからといって、元々家賃を払って住んでいた建物にタダで居座ることはできません。
ただ、この点については次のような法律構成をとります。
「Aには賃料相当額の使用利益という不当利得がある」
つまり、それまでに毎月支払っていた賃料と同額の不当利得が月々で発生し、その返還義務をAはBに対して負う、ということです。
もっと簡単に言えば「契約終了後も建物を留置して住むのであれば家賃相当額を払い続けてください」となりますが、あくまでAB間の賃貸借契約は終了しているので「不当利得」という法律構成をとることになるのです。
あれ?でもAがそのまま住み続けて家賃相当額を払い続けると、その金額が、そもそもの「建物を留置する発端」となった「有益費の償還請求額」を超えてしまうんじゃ...?
そうなんです。
なので、その金額が追いついた時点で、建物所有者Bからの相殺の主張があれば、有益費の償還請求権が消滅し、(被担保債権の存在が前提である担保権の付従性により)それにともなって留置権の消滅、という流れになります。
【補足】
造作買取請求権による建物の留置はできる?
造作とは、家主の承諾の下に建物に付加した畳や建具のことです。
賃貸借契約終了時に、賃借人はオーナー(家主)にこれを買い取れと迫ることができます。
これが造作買取請求権です。
さて、ではこの造作買取請求権に基づき建物を留置することはできるのでしょうか?
ここでの問題は、造作自体だけでなく、建物も留置できるのか?です。
結論。
判例により「建物と造作は別物だ」ということで、建物の留置はできません。
造作に関する債権で建物を留置するのは「物(建物)と債権(造作買取請求権)に牽連性がない」ので無理だ、ということです。
理屈として、造作自体の留置はできますが、建物に付加してしまっているので、現実にはそれも難しいでしょう。
建物買取請求権と留置権

続いてはこちらの事例をご覧ください。
事例9
Aの所有地に借地権の設定を受けたBは、そこに建物を建て所有していた。その後、借地権の期間満了に基づき、AはBに土地の明け渡しを求めた。
これは、地主Aから借りた土地に建物を建てて所有しているBが、借地契約の期間満了によりAから土地の明け渡しを求められた、という話です。
さて、この事例9で、Bが建物買取請求権を行使した場合、Bはその土地を留置できるでしょうか?
もっと簡単に言えば、借地人Bは「オマエが建物を買い取るまで土地を明け渡さん!」と地主Aに対し留置権の主張ができるのか?ということです。
結論。
借地人Aは地主Bに対し、建物買取請求権に基づき土地の留置ができます。
つまり、Bは「オマエが建物を買い取るまで土地を明け渡さん!」と地主Aに対し留置権の主張ができます。
建物買取請求権は建物に関する債権なのになぜ土地を留置できるのか?
まず、建物買取請求権自体は借地借家法13条1項に定められた借地人の権利です。
したがって、「建物を買い取れ!」と迫って建物を留置することは何も問題ないですよね?
しかし、建物買取請求権は建物に関する債権なので「物(土地)と債権(建物買取請求権)に牽連性がない」はずです。
なので、土地の留置はできないはずです。
ただ、建物だけ切り離して引っ越した上で土地だけ留置することなど不可能ですよね?
なので、もし原理原則に従い建物は留置できて土地は留置できないとなると、建物買取請求権の行使が事実上不可能な権利として何の意味もないものとなってしまいます。
元々、建物買取請求権は借地借家法による借り手保護政策の一環です。
これでは何の借り手の保護にもなりません。
そこで、判例では、建物を留置できる反射的効果として、土地の留置もできるとしました。
ただし、タダでという訳にはいきません。
借地人は地代相当額を不当利得として地主に返還することになります。
ここの理屈は、事例8の有益費の償還請求権のケースと一緒です。
留置権と消滅時効と果実
【消滅時効の問題】
民法300条では、留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を妨げないと規定しています。
どういう意味かというと、留置権を行使したからといって被担保債権の時効の進行は止められない、ということです。
つまり、「金払うまで物は渡さん!」と留置権を行使しても「金払え!」という債権の時効の進行には影響はないのです。
なので、いつまでも物を留置しているからといってボヤボヤしていると、肝心の「金払え!」という被担保債権が時効で消滅してしまえば、それに伴い留置権も消滅してしまいます。
なお、留置権は占有を伴う権利なので、留置権それ自体が時効により消滅することはあり得ません。
では、訴訟上、留置権を行使した場合はどうなるでしょう?
例えば、所有者からの目的物の返還請求訴訟で、被告側が留置権を主張して返還を拒んだ場合です。
この場合は、訴訟上、留置権を主張しているので、被担保債権の行使と認められ消滅時効はストップします。
ただ、これは催告としての効果であり、訴訟の終結後6ヶ月以内に、被担保債権に基づき支払請求訴訟を提起するなどの手段をとらなければ、時効の更新にはなりません。
【果実の問題】
民法297条では、留置権者は留置物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができると規定しています。
どういう意味かというと、留置物から生じる果実については、留置権者に優先弁済権があるということです。
留置物を競売した場合、留置権者に優先弁済権はありませんが、留置物から生じる果実に対する優先弁済権はあるのです。
この点はご注意ください。
補足:留置権者による費用の償還請求権
最後に、留置権者による費用の償還請求権について、簡単に解説します。
占有と償還請求については民法196条に一般則があり、民法299条には留置権についての特則があります。
これをまとめると、留置権については次のようになります。
必要費→償還請求できる
有益費→価格の増加が現存する限り所有者の選択に従い、その金額または増加額を償還させることができる(所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる))
通常の占有のケースでは、占有者が果実を取得した場合に通常の必要費を占有者が負担します。
しかし、留置権の場合、果実は弁済にあてられるので、通常の必要費も所有者の負担となります。
また、通常の占有のケースでは、有益費につき裁判所による期限の許与は悪意の占有者のみ認められていますが、留置権の場合は、そもそも他人の物を占有しているのは明らかなので、そのような制限はなく一律に認められています。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【質権】動産質・債権質(権利質)・不動産質/質物の返還請求と対抗要件と賃貸について/転質とは?わかりやすく解説!
【質権】動産質・債権質(権利質)・不動産質/質物の返還請求と対抗要件と賃貸について/転質とは?わかりやすく解説!
-
 【留置権】最強の担保物権?成立要件と対抗力/不動産の場合/留置物の賃貸と留置権の消滅をわかりやすく解説!
【留置権】最強の担保物権?成立要件と対抗力/不動産の場合/留置物の賃貸と留置権の消滅をわかりやすく解説!
-
 【先取特権】民法の原則を曲げる?/一般の先取特権/動産の先取特権/不動産の先取特権/第三取得者とは?わかりやすく解説!
【先取特権】民法の原則を曲げる?/一般の先取特権/動産の先取特権/不動産の先取特権/第三取得者とは?わかりやすく解説!
-
 【譲渡担保】民法の条文にない?【代理受領】債権の担保化とは?わかりやすく解説!
【譲渡担保】民法の条文にない?【代理受領】債権の担保化とは?わかりやすく解説!
-