
【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
▼この記事でわかること
・相殺の超基本
・自働債権と受働債権
・互いの債権額が違う場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

相殺の超基本
相殺とは、互いの債権を打ち消し合う仕組みです。
といってもこれだけでは中々ピンと来ませんので、事例とともに解説します。
事例1
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから10万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。
この事例1では、AはBに対してギター代金「10万円支払え」という債権を持っているのと同時に、BもAに対してベース代金「10万円支払え」という債権を持っています。
つまり、お互いがお互いに対して「金払え」という同種の債権を持っています。
さて、このような場合に、Aが相殺をすると、AのBに対する「10万円支払え」という債権は消滅し、BのAに対する「10万円支払え」という債権も消滅します。
これが相殺です。
ギター代債権10万円
↓
A⇆B
↑
ベース代債権10万円
Aが相殺をすると
A→債権消滅←B
相殺とは、互いが互いに同種の債務を負っていて、互いが互いに対して同種の債権(ほとんどの場合が金銭債権と思ってOK)を持つ場合に、一方の意思表示で互いの債権を打ち消し合う仕組みです。
ここで「あれ?」と思った方もいらっしゃるかと思います。
そうです。
相殺は、あくまで一方の意思表示で行います。
つまり、AはBの意思に関係なく、Aの意思だけで相殺ができます。
同様に、Bから相殺する場合も、BはAの意思に関係なく、Bの意思だけで相殺ができます。
自働債権と受働債権
Aから相殺する場合、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権を自動債権、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権を受動債権といいます。
[Aから相殺する場合]
ギター代金債権10万円←受動債権
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権10万円←自働債権
また、Bから相殺する事ももちろん可能です(結果はAからする場合と同じ)。
その場合は、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権が自動債権、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権が受動債権となります。
[Bから相殺する場合]
ギター代金債権10万円←自動債権
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権10万円←受動債権
つまり、相殺する側(相殺の意思表示をする側)の債権が自動債権、相殺される側の債権が受動債権、ということです。
互いの債権額が違う場合
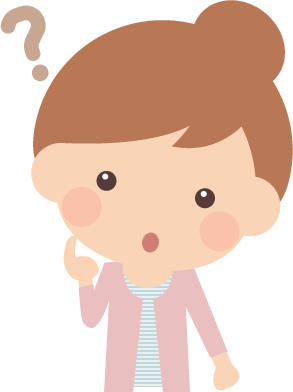
続いて、次のようなケースではどうなるでしょう?
事例2
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから15万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。
この事例2でも、AとBは互いに債権を持っています。
しかし、今回は互いの債権の額が違います。
BのAに対する債権が「10万円支払え」なのに対し、AのBに対する債権は「15万円支払え」となっています。
それではこの事例2で、Aが相殺すると、AとBの債権はどうなるのでしょうか?
相殺すると、各債務者はその対等額についてその債務を免れます(民法505条)。
つまり、相殺すると、互いの債権額のうち対等額分(同額分)が消滅します。
したがいまして、事例2でAが相殺をすると、AとBの互いの債権の対等額10万円分が消滅します。
よって、AのBに対する債権は「5万円支払え」となり、BのAに対する債権は消滅します。
ギター代金債権10万円
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権15万円
Aが相殺すると
(ギター代債権は消滅)
A→B
↑
ベース代金債権5万円
以上、相殺についての超基本になります。
なお、相殺については「「【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!」」の中でも具体的な事例とともに解説していますので、よろしければそちらも併せてお読みいただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・相殺の超基本
・自働債権と受働債権
・互いの債権額が違う場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

相殺の超基本
相殺とは、互いの債権を打ち消し合う仕組みです。
といってもこれだけでは中々ピンと来ませんので、事例とともに解説します。
事例1
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから10万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。
この事例1では、AはBに対してギター代金「10万円支払え」という債権を持っているのと同時に、BもAに対してベース代金「10万円支払え」という債権を持っています。
つまり、お互いがお互いに対して「金払え」という同種の債権を持っています。
さて、このような場合に、Aが相殺をすると、AのBに対する「10万円支払え」という債権は消滅し、BのAに対する「10万円支払え」という債権も消滅します。
これが相殺です。
ギター代債権10万円
↓
A⇆B
↑
ベース代債権10万円
Aが相殺をすると
A→債権消滅←B
相殺とは、互いが互いに同種の債務を負っていて、互いが互いに対して同種の債権(ほとんどの場合が金銭債権と思ってOK)を持つ場合に、一方の意思表示で互いの債権を打ち消し合う仕組みです。
ここで「あれ?」と思った方もいらっしゃるかと思います。
そうです。
相殺は、あくまで一方の意思表示で行います。
つまり、AはBの意思に関係なく、Aの意思だけで相殺ができます。
同様に、Bから相殺する場合も、BはAの意思に関係なく、Bの意思だけで相殺ができます。
自働債権と受働債権
Aから相殺する場合、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権を自動債権、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権を受動債権といいます。
[Aから相殺する場合]
ギター代金債権10万円←受動債権
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権10万円←自働債権
また、Bから相殺する事ももちろん可能です(結果はAからする場合と同じ)。
その場合は、BのAに対する「ギター代金10万円支払え」という債権が自動債権、AのBに対する「ベース代金10万円支払え」という債権が受動債権となります。
[Bから相殺する場合]
ギター代金債権10万円←自動債権
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権10万円←受動債権
つまり、相殺する側(相殺の意思表示をする側)の債権が自動債権、相殺される側の債権が受動債権、ということです。
互いの債権額が違う場合
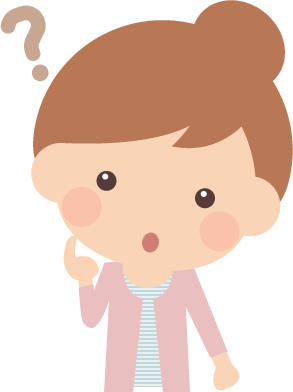
続いて、次のようなケースではどうなるでしょう?
事例2
AはBから10万円のギターを買い受け、その代金はまだ支払っていない。また、BはAから15万円のベースを買い受け、その代金はまだ支払っていない。
この事例2でも、AとBは互いに債権を持っています。
しかし、今回は互いの債権の額が違います。
BのAに対する債権が「10万円支払え」なのに対し、AのBに対する債権は「15万円支払え」となっています。
それではこの事例2で、Aが相殺すると、AとBの債権はどうなるのでしょうか?
相殺すると、各債務者はその対等額についてその債務を免れます(民法505条)。
つまり、相殺すると、互いの債権額のうち対等額分(同額分)が消滅します。
したがいまして、事例2でAが相殺をすると、AとBの互いの債権の対等額10万円分が消滅します。
よって、AのBに対する債権は「5万円支払え」となり、BのAに対する債権は消滅します。
ギター代金債権10万円
↓
A⇆B
↑
ベース代金債権15万円
Aが相殺すると
(ギター代債権は消滅)
A→B
↑
ベース代金債権5万円
以上、相殺についての超基本になります。
なお、相殺については「「【連帯債務の相殺と求償】相殺を援用する&しないとどうなる?/無資力者がいるときの求償問題など様々なケースと注意点をわかりやすく解説!」」の中でも具体的な事例とともに解説していますので、よろしければそちらも併せてお読みいただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【債務不履行&損害賠償&過失責任の原則】債権債務の超基本を初学者にもわかりやすく解説!
【債務不履行&損害賠償&過失責任の原則】債権債務の超基本を初学者にもわかりやすく解説!
-
 【差押え&強制執行&破産の超基本】借金で考える債権の世界~債務者に財産が無いとどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
【差押え&強制執行&破産の超基本】借金で考える債権の世界~債務者に財産が無いとどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【抵当権の超基本】その特徴と意味とは?抵当権の強さの理由とは?一般財産って何?初学者にもわかりやすく解説!
【抵当権の超基本】その特徴と意味とは?抵当権の強さの理由とは?一般財産って何?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【保証債務の超基本】人が担保の保証人&物が担保の物上保証~そして代位弁済とは?初学者にもわかりやすく解説!
【保証債務の超基本】人が担保の保証人&物が担保の物上保証~そして代位弁済とは?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
【相殺の超基本】自働債権と受働債権って何?互いの債権額が違うときはどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!
【債権譲渡の超基本】債権を譲ると?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【履行遅滞と受領遅滞】遅延損害金の発生時期は?契約の解除は?遅滞中の善管注意義務は?わかりやすく解説!
【履行遅滞と受領遅滞】遅延損害金の発生時期は?契約の解除は?遅滞中の善管注意義務は?わかりやすく解説!
-
 【損害賠償の範囲】どこまでの損害を賠償するのか?損害賠償額の予定とは?初学者にもわかりやすく解説!
【損害賠償の範囲】どこまでの損害を賠償するのか?損害賠償額の予定とは?初学者にもわかりやすく解説!
-