
【共同相続と登記】遺産分割協議と相続人&相続放棄者の勝手な不動産譲渡問題/遺言による相続と登記をわかりやすく解説!
▼この記事でわかること
・相続と登記の超基本
・共同相続と登記
・遺産分割協議とは
・共同相続人の勝手な不動産譲渡?と登記
・相続放棄者が相続財産を譲渡?と登記
・遺言による相続と登記
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

相続と登記
登記の問題に相続が絡んでくる場合とは、一体どのようなケースでしょう?
事例1
BはAに甲不動産を譲渡した後、死亡した。その後、Bの唯一の相続人であるCは、甲不動産をDに譲渡した。
これがまず、不動産登記に相続が絡んだ場合の基本的なケースでしょう。
この事例の流れはこうです。
BがAに甲不動産を譲渡
↓
Bが死亡
↓
BをCが相続
↓
CがDに甲不動産を譲渡
この事例1について考えるときのポイントは、BとCは同一人物だと考えることです。
CはBを相続しています。
そして、相続は包括承継です。
わかりやすく言うと、CはBそのものを引き継いでいるのです。
したがって、事例1は、C(=B)が、AとDに甲不動産を譲渡している、という不動産の二重譲渡のケースになります。
さて、ではこの事例1で、甲不動産を取得できるのは、Aでしょうか?それともDでしょうか?
答えは簡単です。
これは不動産の二重譲渡のケースなので、単純に早く登記した方が甲不動産を取得します。
共同相続と登記
事例2
Aが死亡し、A所有の甲土地をBとCが共同相続した。相続分は同一(半々)である。その後、BC間で、甲土地はBが単独で所有するという遺産分割協議が成立した。ところが、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
さて、ここからが「相続と登記」の本格的な内容になります。
状況の整理をしないとややこしいので、まず、この事例2の流れを確認しましょう。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
BC間の遺産分割協議により
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
Cが自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
事例2の流れと状況はこのとおりです。
さて、ではこの事例2で、そもそもCに、甲土地の所有権全部について自己名義の登記(甲土地の所有権全部をC名義で登記)をして、そこからさらに甲土地をDに譲渡する権利があるのでしょうか?
遺産分割協議とは

相続財産を、相続人間の話し合いで分けることを遺産分割といいます。
例えば、長男は土地、次男は株、三男は預金、といった具合です。
そして、遺産分割の効力についての、民法の規定はこちらです。
(遺産の分割の効力)
民放909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
この民法909条の条文を見ると、遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼるとあります。
ということは、事例2は、BC間の遺産分割協議が成立して、その効力はAの死亡時(相続が開始した時)にさかのぼります。
となると、甲土地の所有権は、Aが死亡して相続が開始した時からBのものだったことになります。
こう考えていくと、そもそも、Cには甲土地についてどうこうする権利などない、ということになります。
しかし!
判例の考えは、民法909条の遺産分割の遡及効(遡って生じる効力)を制限します。
これはどういう事かといいますと、甲土地について、Cの権利を全く認めない訳ではないのです。
共同相続人の勝手な不動産譲渡
ここで今一度、事例2の流れと状況を確認しましょう。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
BC間の遺産分割協議により
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
C単独で自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
さて、ではこの事例2で、無権利者のように思われるCから甲土地を譲渡されたDに対し、Bは「遺産分割により甲土地の所有権全部が私のものとなった!なので返せ!」と、甲土地の所有権を主張できるでしょうか?
~Dの救いの道~
本来、遺産分割されると、その効力は相続開始の時まで遡ります。
つまり、BC間の遺産分割協議により遺産分割されると、Aが死亡して相続が開始した時から甲土地の全部はBのものだったことになります。
しかし、判例はこの原則を曲げて、遺産分割の遡及効(遡って生じる効力)を制限します。
そして、遺産分割の遡及効を制限することにより、Dには救いの道が開かれます。
Dに救いの道が開かれるということは、Aが泣くことになる可能性を意味します。
Aの主張の雲行きが怪しくなってきましたね。
甲土地をBの持ち分と
Cの持ち分とに分けて考える

まず、Aが死亡すると、甲土地はBとCへ相続されます。
その際、甲土地の持ち分は半々となっています。
ここで、Bの持ち分をb土地、Cの持ち分をc土地とします。
そして、Cは甲土地の所有権全部について自己名義の登記をしてDに譲渡します。
つまり、Cは、b土地とc土地の両方を合わせた甲土地に自己名義の登記をした上でDに譲渡した、ということになります。
さて、ここからは甲土地の行方を、b土地とc土地に分けて考えていきます。
・Bの持ち分:b土地
こちらは、相続により直接Bに帰属します。
つまり、b土地の所有権は、相続によりダイレクトにBのものになります。
ですので、b土地については、Cは一回もその権利を取得したことはなく、全くの無権利者です。
したがいまして、b土地について全くの無権利者のCから譲渡されたDがb土地を取得することはあり得ません。
〈Bの持ち分:b土地〉
A
↓直接
B
(Cの入る余地なし)
なので、CD間のb土地(Bの持ち分)の譲渡は無効であり、Dの登記も無効です。
よってBは、b土地については登記がなくともDに対抗できます。
したがって、Bはb土地については登記をしていなくとも、(無効な)登記をしているDに対して「b土地を返せ!」と主張することができます。
・Cの持ち分:c土地
こちらは、相続によりいったんCに帰属します(判例により遺産分割の遡及効が制限されるので)。
つまり、c土地の所有権は相続によりいったんCのものとなり、その後、遺産分割により、Bのものとなります。
そして、ここからがポイントです。
c土地は相続によりいったんCのものとなり、その後、遺産分割によりBのものとなる訳ですが、Cがc土地をDに譲渡したことにより、c土地がBとDに二重譲渡されたと考えます。
〈C持ち分:c土地〉
A
↓
C→D
↓二重譲渡
B
不動産の二重譲渡は、民法177条の規定により、第三者(事例だとD)の善意・悪意も関係なく、単純に早く登記をした方が勝ちます。
したがいまして、事例2のDは登記をしていますので、c土地については、その所有権はDが取得します。
以上のように、判例では、C持ち分:c土地に関しましては、Dに救いの道を示したということです。
逆にBは、B持ち分:b土地については登記がなくともDに対抗できますが、C持ち分:c土地に関しましては、先に登記をされてしまったDに対しては、もはや泣くしかありません。
ということで結論。
BはDに対して「甲土地の所有権の全部を私に返せ!」と主張しても、c土地に関しましては「私(D)が登記したから私のモノだ!」というDに対抗することができません。
したがいまして、BがDから取り戻せるのは「B持ち分:b土地のみ」となります。
相続放棄者が相続財産を譲渡?
続いては、共同相続人の相続放棄が絡んだケースを解説します。
事例3
Aが死亡し、A所有の甲土地をBとCが共同相続した。相続分は同一(半々)である。しかし、Cはすぐに相続放棄した。その後、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
事例の前に、まず「相続放棄」について、簡単に解説いたします。
相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄することです。
相続人としての地位そのものを放棄するということは、そもそも最初から相続人ではなかったとみなされます。
そして一度、相続放棄をして相続人ではなかったとみなされると、もう二度と相続人に戻ることはありません(「みなす」という言葉はそれぐらい強力なのだ。その後の反論も一切許さないのである)。
したがって、相続放棄をした者は、もはや相続人ではないので、当然、相続人としてカウントされなくなります。
なぜそんな制度があるの?
相続は、死亡した人間の財産上の地位をまるごと引き継ぎます(包括承継)。
財産上の地位をまるごと引き継ぐということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も、まとめて引き継ぐということを意味します。
ですので、もし親が大借金を抱えて亡くなると、相続人となる子供は、親の作った大借金をそのまま丸ごと引き継ぐことになります。
しかし、それでは相続人が困ってしまいますよね。
それどころか、その借金があまりにも莫大なものだったとしたら、子々孫々まで延々とその借金を背負わされてしまい兼ねません。
そこで「相続放棄」という制度があるのです。
なお、プラスの財産しかない場合でも相続放棄することは可能です。
実際、相続争いに巻き込まれるのは勘弁ということで、プラスの財産でも相続放棄するケースは多々あります。
さて、それではここから、事例3についての解説に入って参りますが、今一度、事例の流れと状況を確認します。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
Cが相続放棄
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
C単独で自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
以上が事例の流れと状況です。
それでは事例について本格的に見ていきましょう。
Aの相続人はBとCです。
甲土地はBとCに共同相続されます。
しかし、すぐにCは相続放棄します。
すると、Cは最初から相続人ではなかったとみなされ、甲土地は最初からBが一人で相続したことになります。
そして、相続放棄の効果は絶対です。
ですので、一度、相続放棄をしたCには、もはや甲土地の何もかもについてどうこうする余地は1ミリもありません。
相続放棄をしたCは完全な無権利者です。
したがって、Cが相続放棄をするとこうなります。
〈甲土地〉
A
↓直接
B
(相続人としてのCの存在は最初からいなかったことになる)
したがいまして、相続放棄をして、甲土地について最初から完全な無権利者となるCに、甲土地をDに譲渡することなどは当然できず、CD間の甲土地の譲渡は完全に無効なもので、Dの登記も無効です。
よってBは、登記を備えたDに対して、登記なくとも甲土地の所有権の全部について対抗できます。
つまり、Bは甲土地について登記をしていなくても、登記をしたDに対して「甲土地の所有権全部、私に返せ!」と主張できます。
事例3の場合、Dが甲土地の所有権争いに勝つ可能性は全くありません。
遺言による相続の場合
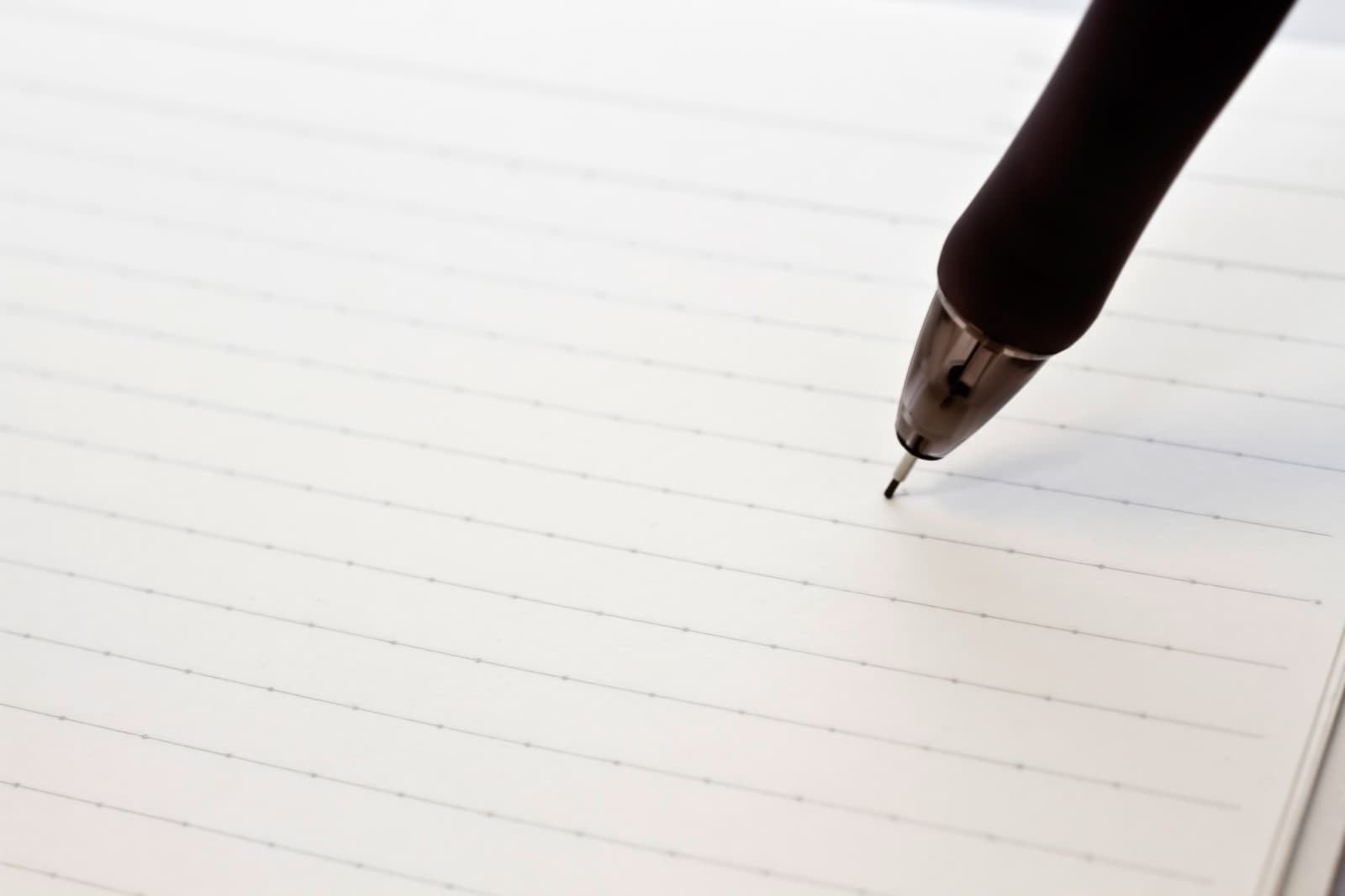
最後に、遺言による相続のケースを解説します。
事例4
Aが死亡した。そしてAの遺言により、A所有の甲土地をBが持ち分3分の1、Cが持ち分3分の2で相続した。その後、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
これは、遺言により相続分が指定されたケースです。
そして、Cが遺言による指定を無視して、甲土地の所有権全部について自己名義の登記をした上、Dに譲渡して移転登記もした、というものです。
さて、この事例で、Dは甲土地を取得できるのでしょうか?
結論。
Dは甲土地を取得できます。
ただし、Dが取得できる甲土地は、3分の2のC持ち分のみです。(論理・考え方は遺産分割の事例2と一緒です)
Bの持ち分は?
甲土地の3分の1のB持ち分については、Dが取得することはあり得ません。
なぜなら、B持ち分については、Cがそもそも完全な無権利者だからです。
完全な無権利者のCから、B持ち分がDへ譲渡されることがあり得ないんです。
つまり、CD間のB持ち分の譲渡は無効です。
〈B持ち分〉
A
↓相続
B
(Cの入る余地なし/Dの登記は無効)
なお、Bは登記がなくとも、B持ち分については、Dに対抗できます。
よってDは、B持ち分については、登記のないBから「返せ!」と迫られたら、大人しく返還しなければなりません。
事例5
Aが死亡した。そしてAの遺言により、A所有の甲土地をBが持ち分3分の1、Cが持ち分3分の2で相続した。その後、Cは相続放棄した。ところが、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
これも、遺言により相続分が指定されたケースで、相続放棄をしたCが、甲土地の所有権全部につき自己名義の登記をした上、Dに譲渡しその移転登記もした、というものです。
さて、ではこの事例5で、Dは甲土地を取得できるでしょうか?
結論。
Dは甲土地を取得することはできません。
論理・考え方は相続放棄の事例3と一緒です。
Cの持ち分は?
はい。DはCの持ち分すら取得することはできません。
なぜなら、Cが相続放棄したということは、Cは最初から相続人ではなかったとみなされます。
Cが相続人ではなかったとみなされると、最初から甲土地はB1人で相続したことになります。
それは遺言による相続分の指定があろうと関係ありません。
〈甲土地〉
A
↓相続
B
(相続人としてのCの存在は最初からいなかったことになる)
相続放棄の効果は絶対です。
一度、相続放棄をしたCが、再び相続人に戻ることもありません。
相続放棄したけどやっぱナシ!とはできないのです。
したがいまして、相続放棄をしたCは、もはや相続人ではないので、甲土地に関しては全くの無権利者です。
全くの無権利者CからDに甲土地が譲渡されることはあり得ません。
よってCD間の甲土地の譲渡は無効であり、Dの登記も無効です。
ということなので、Bは登記がなくとも、Dに対し甲土地の全部について対抗できます。
つまり、Bは登記をしていなくとも、(無効な)登記をしたDに対し「甲土地の所有権全部返せコラ!」と主張することができます。
事例5でDが勝つ可能性はゼロです。
それだけ、Cの相続放棄の効果が絶対ということなのです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・相続と登記の超基本
・共同相続と登記
・遺産分割協議とは
・共同相続人の勝手な不動産譲渡?と登記
・相続放棄者が相続財産を譲渡?と登記
・遺言による相続と登記
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

相続と登記
登記の問題に相続が絡んでくる場合とは、一体どのようなケースでしょう?
事例1
BはAに甲不動産を譲渡した後、死亡した。その後、Bの唯一の相続人であるCは、甲不動産をDに譲渡した。
これがまず、不動産登記に相続が絡んだ場合の基本的なケースでしょう。
この事例の流れはこうです。
BがAに甲不動産を譲渡
↓
Bが死亡
↓
BをCが相続
↓
CがDに甲不動産を譲渡
この事例1について考えるときのポイントは、BとCは同一人物だと考えることです。
CはBを相続しています。
そして、相続は包括承継です。
わかりやすく言うと、CはBそのものを引き継いでいるのです。
したがって、事例1は、C(=B)が、AとDに甲不動産を譲渡している、という不動産の二重譲渡のケースになります。
さて、ではこの事例1で、甲不動産を取得できるのは、Aでしょうか?それともDでしょうか?
答えは簡単です。
これは不動産の二重譲渡のケースなので、単純に早く登記した方が甲不動産を取得します。
共同相続と登記
事例2
Aが死亡し、A所有の甲土地をBとCが共同相続した。相続分は同一(半々)である。その後、BC間で、甲土地はBが単独で所有するという遺産分割協議が成立した。ところが、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
さて、ここからが「相続と登記」の本格的な内容になります。
状況の整理をしないとややこしいので、まず、この事例2の流れを確認しましょう。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
BC間の遺産分割協議により
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
Cが自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
事例2の流れと状況はこのとおりです。
さて、ではこの事例2で、そもそもCに、甲土地の所有権全部について自己名義の登記(甲土地の所有権全部をC名義で登記)をして、そこからさらに甲土地をDに譲渡する権利があるのでしょうか?
遺産分割協議とは

相続財産を、相続人間の話し合いで分けることを遺産分割といいます。
例えば、長男は土地、次男は株、三男は預金、といった具合です。
そして、遺産分割の効力についての、民法の規定はこちらです。
(遺産の分割の効力)
民放909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
この民法909条の条文を見ると、遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼるとあります。
ということは、事例2は、BC間の遺産分割協議が成立して、その効力はAの死亡時(相続が開始した時)にさかのぼります。
となると、甲土地の所有権は、Aが死亡して相続が開始した時からBのものだったことになります。
こう考えていくと、そもそも、Cには甲土地についてどうこうする権利などない、ということになります。
しかし!
判例の考えは、民法909条の遺産分割の遡及効(遡って生じる効力)を制限します。
これはどういう事かといいますと、甲土地について、Cの権利を全く認めない訳ではないのです。
共同相続人の勝手な不動産譲渡
ここで今一度、事例2の流れと状況を確認しましょう。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
BC間の遺産分割協議により
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
C単独で自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
さて、ではこの事例2で、無権利者のように思われるCから甲土地を譲渡されたDに対し、Bは「遺産分割により甲土地の所有権全部が私のものとなった!なので返せ!」と、甲土地の所有権を主張できるでしょうか?
~Dの救いの道~
本来、遺産分割されると、その効力は相続開始の時まで遡ります。
つまり、BC間の遺産分割協議により遺産分割されると、Aが死亡して相続が開始した時から甲土地の全部はBのものだったことになります。
しかし、判例はこの原則を曲げて、遺産分割の遡及効(遡って生じる効力)を制限します。
そして、遺産分割の遡及効を制限することにより、Dには救いの道が開かれます。
Dに救いの道が開かれるということは、Aが泣くことになる可能性を意味します。
Aの主張の雲行きが怪しくなってきましたね。
甲土地をBの持ち分と
Cの持ち分とに分けて考える

まず、Aが死亡すると、甲土地はBとCへ相続されます。
その際、甲土地の持ち分は半々となっています。
ここで、Bの持ち分をb土地、Cの持ち分をc土地とします。
そして、Cは甲土地の所有権全部について自己名義の登記をしてDに譲渡します。
つまり、Cは、b土地とc土地の両方を合わせた甲土地に自己名義の登記をした上でDに譲渡した、ということになります。
さて、ここからは甲土地の行方を、b土地とc土地に分けて考えていきます。
・Bの持ち分:b土地
こちらは、相続により直接Bに帰属します。
つまり、b土地の所有権は、相続によりダイレクトにBのものになります。
ですので、b土地については、Cは一回もその権利を取得したことはなく、全くの無権利者です。
したがいまして、b土地について全くの無権利者のCから譲渡されたDがb土地を取得することはあり得ません。
〈Bの持ち分:b土地〉
A
↓直接
B
(Cの入る余地なし)
なので、CD間のb土地(Bの持ち分)の譲渡は無効であり、Dの登記も無効です。
よってBは、b土地については登記がなくともDに対抗できます。
したがって、Bはb土地については登記をしていなくとも、(無効な)登記をしているDに対して「b土地を返せ!」と主張することができます。
・Cの持ち分:c土地
こちらは、相続によりいったんCに帰属します(判例により遺産分割の遡及効が制限されるので)。
つまり、c土地の所有権は相続によりいったんCのものとなり、その後、遺産分割により、Bのものとなります。
そして、ここからがポイントです。
c土地は相続によりいったんCのものとなり、その後、遺産分割によりBのものとなる訳ですが、Cがc土地をDに譲渡したことにより、c土地がBとDに二重譲渡されたと考えます。
〈C持ち分:c土地〉
A
↓
C→D
↓二重譲渡
B
不動産の二重譲渡は、民法177条の規定により、第三者(事例だとD)の善意・悪意も関係なく、単純に早く登記をした方が勝ちます。
したがいまして、事例2のDは登記をしていますので、c土地については、その所有権はDが取得します。
以上のように、判例では、C持ち分:c土地に関しましては、Dに救いの道を示したということです。
逆にBは、B持ち分:b土地については登記がなくともDに対抗できますが、C持ち分:c土地に関しましては、先に登記をされてしまったDに対しては、もはや泣くしかありません。
ということで結論。
BはDに対して「甲土地の所有権の全部を私に返せ!」と主張しても、c土地に関しましては「私(D)が登記したから私のモノだ!」というDに対抗することができません。
したがいまして、BがDから取り戻せるのは「B持ち分:b土地のみ」となります。
相続放棄者が相続財産を譲渡?
続いては、共同相続人の相続放棄が絡んだケースを解説します。
事例3
Aが死亡し、A所有の甲土地をBとCが共同相続した。相続分は同一(半々)である。しかし、Cはすぐに相続放棄した。その後、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
事例の前に、まず「相続放棄」について、簡単に解説いたします。
相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄することです。
相続人としての地位そのものを放棄するということは、そもそも最初から相続人ではなかったとみなされます。
そして一度、相続放棄をして相続人ではなかったとみなされると、もう二度と相続人に戻ることはありません(「みなす」という言葉はそれぐらい強力なのだ。その後の反論も一切許さないのである)。
したがって、相続放棄をした者は、もはや相続人ではないので、当然、相続人としてカウントされなくなります。
なぜそんな制度があるの?
相続は、死亡した人間の財産上の地位をまるごと引き継ぎます(包括承継)。
財産上の地位をまるごと引き継ぐということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も、まとめて引き継ぐということを意味します。
ですので、もし親が大借金を抱えて亡くなると、相続人となる子供は、親の作った大借金をそのまま丸ごと引き継ぐことになります。
しかし、それでは相続人が困ってしまいますよね。
それどころか、その借金があまりにも莫大なものだったとしたら、子々孫々まで延々とその借金を背負わされてしまい兼ねません。
そこで「相続放棄」という制度があるのです。
なお、プラスの財産しかない場合でも相続放棄することは可能です。
実際、相続争いに巻き込まれるのは勘弁ということで、プラスの財産でも相続放棄するケースは多々あります。
さて、それではここから、事例3についての解説に入って参りますが、今一度、事例の流れと状況を確認します。
A死亡
↓
甲土地
BC共同相続(持ち分半分ずつ)
Cが相続放棄
↓
甲土地の所有権全部
B単独所有
ところが
↓
甲土地の所有権全部
C単独で自己名義登記
↓
Dに譲渡
↓
甲土地
Dが登記
以上が事例の流れと状況です。
それでは事例について本格的に見ていきましょう。
Aの相続人はBとCです。
甲土地はBとCに共同相続されます。
しかし、すぐにCは相続放棄します。
すると、Cは最初から相続人ではなかったとみなされ、甲土地は最初からBが一人で相続したことになります。
そして、相続放棄の効果は絶対です。
ですので、一度、相続放棄をしたCには、もはや甲土地の何もかもについてどうこうする余地は1ミリもありません。
相続放棄をしたCは完全な無権利者です。
したがって、Cが相続放棄をするとこうなります。
〈甲土地〉
A
↓直接
B
(相続人としてのCの存在は最初からいなかったことになる)
したがいまして、相続放棄をして、甲土地について最初から完全な無権利者となるCに、甲土地をDに譲渡することなどは当然できず、CD間の甲土地の譲渡は完全に無効なもので、Dの登記も無効です。
よってBは、登記を備えたDに対して、登記なくとも甲土地の所有権の全部について対抗できます。
つまり、Bは甲土地について登記をしていなくても、登記をしたDに対して「甲土地の所有権全部、私に返せ!」と主張できます。
事例3の場合、Dが甲土地の所有権争いに勝つ可能性は全くありません。
遺言による相続の場合
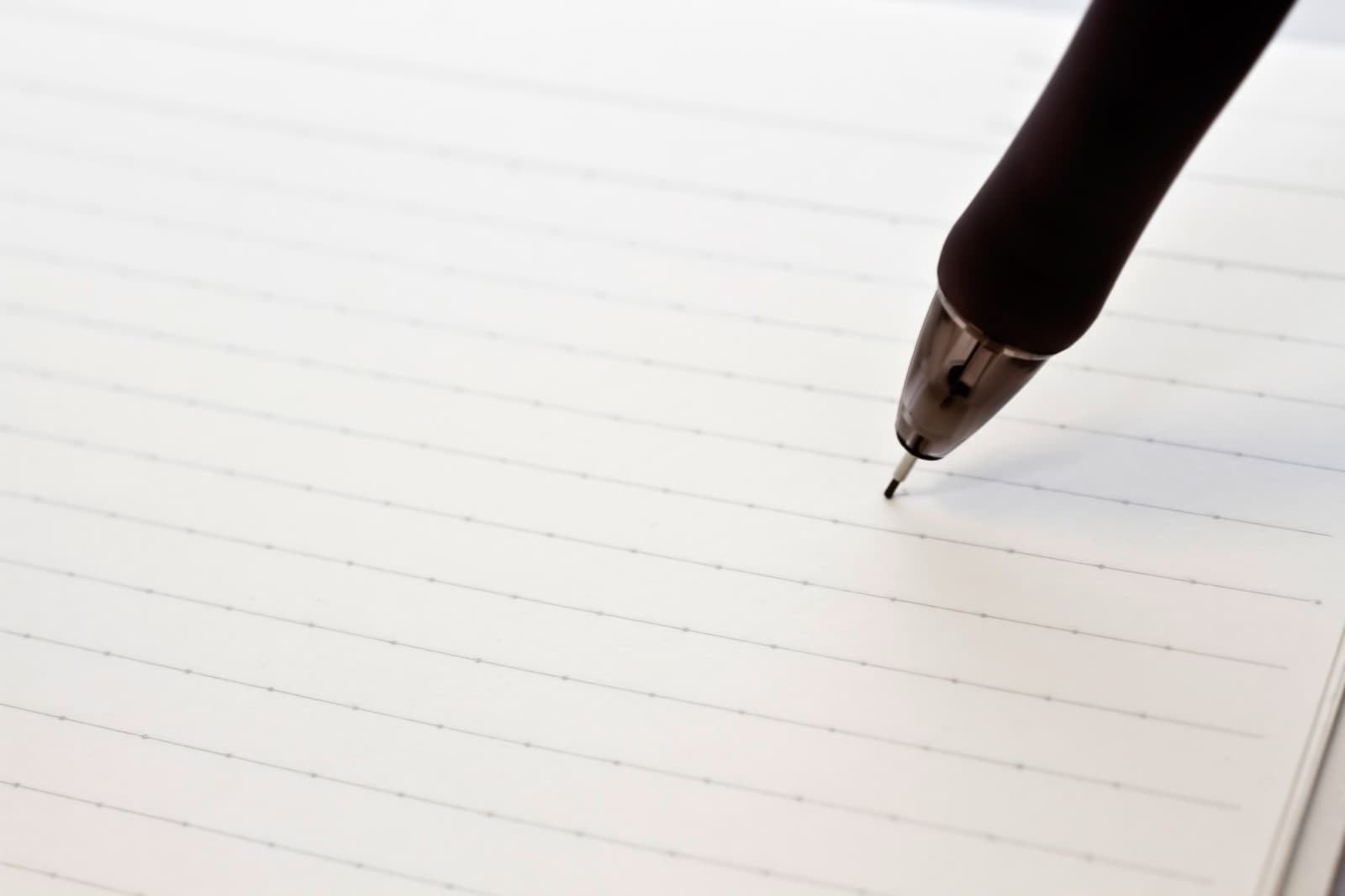
最後に、遺言による相続のケースを解説します。
事例4
Aが死亡した。そしてAの遺言により、A所有の甲土地をBが持ち分3分の1、Cが持ち分3分の2で相続した。その後、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
これは、遺言により相続分が指定されたケースです。
そして、Cが遺言による指定を無視して、甲土地の所有権全部について自己名義の登記をした上、Dに譲渡して移転登記もした、というものです。
さて、この事例で、Dは甲土地を取得できるのでしょうか?
結論。
Dは甲土地を取得できます。
ただし、Dが取得できる甲土地は、3分の2のC持ち分のみです。(論理・考え方は遺産分割の事例2と一緒です)
Bの持ち分は?
甲土地の3分の1のB持ち分については、Dが取得することはあり得ません。
なぜなら、B持ち分については、Cがそもそも完全な無権利者だからです。
完全な無権利者のCから、B持ち分がDへ譲渡されることがあり得ないんです。
つまり、CD間のB持ち分の譲渡は無効です。
〈B持ち分〉
A
↓相続
B
(Cの入る余地なし/Dの登記は無効)
なお、Bは登記がなくとも、B持ち分については、Dに対抗できます。
よってDは、B持ち分については、登記のないBから「返せ!」と迫られたら、大人しく返還しなければなりません。
事例5
Aが死亡した。そしてAの遺言により、A所有の甲土地をBが持ち分3分の1、Cが持ち分3分の2で相続した。その後、Cは相続放棄した。ところが、Cは甲土地の全部につき自己名義の登記をした上、Dに甲土地を譲渡し、その移転登記をした。
これも、遺言により相続分が指定されたケースで、相続放棄をしたCが、甲土地の所有権全部につき自己名義の登記をした上、Dに譲渡しその移転登記もした、というものです。
さて、ではこの事例5で、Dは甲土地を取得できるでしょうか?
結論。
Dは甲土地を取得することはできません。
論理・考え方は相続放棄の事例3と一緒です。
Cの持ち分は?
はい。DはCの持ち分すら取得することはできません。
なぜなら、Cが相続放棄したということは、Cは最初から相続人ではなかったとみなされます。
Cが相続人ではなかったとみなされると、最初から甲土地はB1人で相続したことになります。
それは遺言による相続分の指定があろうと関係ありません。
〈甲土地〉
A
↓相続
B
(相続人としてのCの存在は最初からいなかったことになる)
相続放棄の効果は絶対です。
一度、相続放棄をしたCが、再び相続人に戻ることもありません。
相続放棄したけどやっぱナシ!とはできないのです。
したがいまして、相続放棄をしたCは、もはや相続人ではないので、甲土地に関しては全くの無権利者です。
全くの無権利者CからDに甲土地が譲渡されることはあり得ません。
よってCD間の甲土地の譲渡は無効であり、Dの登記も無効です。
ということなので、Bは登記がなくとも、Dに対し甲土地の全部について対抗できます。
つまり、Bは登記をしていなくとも、(無効な)登記をしたDに対し「甲土地の所有権全部返せコラ!」と主張することができます。
事例5でDが勝つ可能性はゼロです。
それだけ、Cの相続放棄の効果が絶対ということなのです。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【不動産登記の基本】二重譲渡~登記は早い者勝ち/3つの登記請求権と登記引取請求権とは?初学者にもわかりやすく解説!
【不動産登記の基本】二重譲渡~登記は早い者勝ち/3つの登記請求権と登記引取請求権とは?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【時効取得と登記】所有権争い~時効完成前後に現る第三者/さらに二重譲渡と抵当権が絡んだ場合をわかりやすく解説!
【時効取得と登記】所有権争い~時効完成前後に現る第三者/さらに二重譲渡と抵当権が絡んだ場合をわかりやすく解説!
-
 【共同相続と登記】遺産分割協議と相続人&相続放棄者の勝手な不動産譲渡問題/遺言による相続と登記をわかりやすく解説!
【共同相続と登記】遺産分割協議と相続人&相続放棄者の勝手な不動産譲渡問題/遺言による相続と登記をわかりやすく解説!
-