
▼この記事でわかること
・賃借人(借主)の同居人による建物損傷ケース
・賃借人(借主)の同居人は履行補助者
・誰の過失もなく建物が損傷・滅失した場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

賃貸不動産の損傷・滅失
賃借人(借主)の同居人による不動産損傷ケース
例えば、賃貸マンションを借りて住んでいる借主(賃借人)が、不注意でそのマンションを損傷させてしまった場合、借主はその損害を賠償しなければなりません。
では、次のような場合はどうなるのでしょうか?
事例
BはA所有の甲建物を賃借して、妻Cと共に暮らしている。ある日、Cの不注意により甲建物が損傷した。
この事例で、甲建物の賃貸借契約を結んでいるのはオーナー(貸主・賃貸人)のAと借主(賃借人)のBです。
つまり、契約関係にあるのはAとBになります。AとCは契約関係にはありません。
さて、それではこの事例で、オーナー(貸主・賃貸人)Aと契約関係にない妻Cの不注意による損傷について、無過失(ミス・落ち度のない)のBは賃貸借契約上の損害賠償責任を負うことになるのでしょうか?
結論。
妻Cの不注意による損傷について、借主(賃借人)Bは損傷賠償責任を負います。
これは、一般論として当たり前に納得できる結論ですよね。
ただ、よくよく考えてみてください。
オーナー(貸主・賃貸人)Aと契約関係にない妻Cの過失について、過失のない借主(賃借人)Bが責任を負うというのは、ちょっとオカシイような気もしますよね。
賃借人(借主)の同居人は履行補助者
賃貸人(貸主)は賃借人(借主)に対して「目的物を使用収益させる義務」を負います。
一方、賃借人(借主)は賃貸人(貸主)に対して、賃料債務(家賃支払い義務)を負うとともに「目的物について善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」を負います。
善管注意義務とは「一般的に常識的に求められる注意を持って管理する義務」ということです。
つまり、甲建物の賃借人Bは、甲建物を一般的に常識的に求められる注意を持って管理しなければなりません。
イライラして壁にパンチして建物を損傷させた、なんてもってのほかです。
さて、賃借人Bが善管注意義務を負うことはわかりました。
では、同居人の妻Cの過失について、賃借人(借主)Bが責任を負うというのは、一体どういう理屈なのでしょうか?
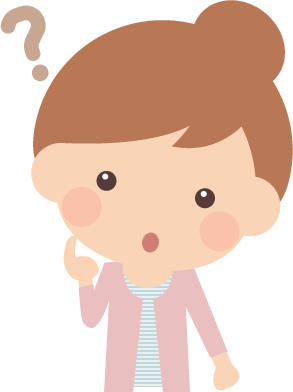
これについて判例では、同居人のCを、賃借人Bの負う「善管注意義務についての履行補助者」と考えます。
そして、信義則上「賃借人Bの善管注意義務についての履行補助者」である同居人の妻Cの過失は、賃借人Bの過失と同視され(Bの過失と同じだと扱われる)、賃借人Bはその賠償責任を負うとしています。
噛み砕いて簡単に言いますと、Bは、妻Cの過失について「嫁がやったことだし。オレじゃねーし」と主張することは許されない、ということです。
誰の過失もなく建物が損傷・滅失した場合
賃借人(借主)または同居人の過失は、賃借人(借主)が責任を負います。
反対に、賃貸人(貸主・オーナー)に過失がある場合は、賃貸人(貸主・オーナー)が責任を負います。
では、誰の過失もなく、つまり、不可抗力で建物が損傷・滅失した場合(要するに誰も悪くない場合)は、一体どうなるのでしょうか?
民法では次のように規定します。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
民法611条
1項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
結論。
民法611条の規定により、その賃借物の滅失割合に応じて、当然に借賃が減額されます。
つまり、不動産賃貸借の場合、その不動産が不可抗力で一部損傷・滅失したときは、その不動産のダメージの割合に応じて当然に家賃が減額されます。
また、損傷・滅失した賃借物が、残存部分だけでは賃借の目的を達することができなければ、契約の解除をすることができます。
つまり、居住用の不動産賃貸借の場合、その居住用不動産が不可抗力で損傷・滅失したとき、残存部分だけでは住むことができないのあれば、賃借人(借主)は、賃貸借契約を解除できるということです。
なお、賃借物の全部が滅失したときは、滅失の原因の如何を問わず、賃貸借契約は解除を待たず当然に終了します。(民法616条の2)
ここでひとつ注意点です。
「解除を待たず当然に終了する」ということは、解除はできません。
賃借物の全部滅失によりすでに消賃貸借契約は消滅しているからです。
すでにゼロになっているもの(無くなっているもの)を解除することはできません。
この点はお気をつけください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・賃借人(借主)の同居人による建物損傷ケース
・賃借人(借主)の同居人は履行補助者
・誰の過失もなく建物が損傷・滅失した場合
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

賃貸不動産の損傷・滅失
賃借人(借主)の同居人による不動産損傷ケース
例えば、賃貸マンションを借りて住んでいる借主(賃借人)が、不注意でそのマンションを損傷させてしまった場合、借主はその損害を賠償しなければなりません。
では、次のような場合はどうなるのでしょうか?
事例
BはA所有の甲建物を賃借して、妻Cと共に暮らしている。ある日、Cの不注意により甲建物が損傷した。
この事例で、甲建物の賃貸借契約を結んでいるのはオーナー(貸主・賃貸人)のAと借主(賃借人)のBです。
つまり、契約関係にあるのはAとBになります。AとCは契約関係にはありません。
さて、それではこの事例で、オーナー(貸主・賃貸人)Aと契約関係にない妻Cの不注意による損傷について、無過失(ミス・落ち度のない)のBは賃貸借契約上の損害賠償責任を負うことになるのでしょうか?
結論。
妻Cの不注意による損傷について、借主(賃借人)Bは損傷賠償責任を負います。
これは、一般論として当たり前に納得できる結論ですよね。
ただ、よくよく考えてみてください。
オーナー(貸主・賃貸人)Aと契約関係にない妻Cの過失について、過失のない借主(賃借人)Bが責任を負うというのは、ちょっとオカシイような気もしますよね。
賃借人(借主)の同居人は履行補助者
賃貸人(貸主)は賃借人(借主)に対して「目的物を使用収益させる義務」を負います。
一方、賃借人(借主)は賃貸人(貸主)に対して、賃料債務(家賃支払い義務)を負うとともに「目的物について善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」を負います。
善管注意義務とは「一般的に常識的に求められる注意を持って管理する義務」ということです。
つまり、甲建物の賃借人Bは、甲建物を一般的に常識的に求められる注意を持って管理しなければなりません。
イライラして壁にパンチして建物を損傷させた、なんてもってのほかです。
さて、賃借人Bが善管注意義務を負うことはわかりました。
では、同居人の妻Cの過失について、賃借人(借主)Bが責任を負うというのは、一体どういう理屈なのでしょうか?
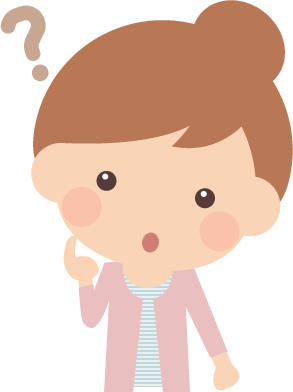
これについて判例では、同居人のCを、賃借人Bの負う「善管注意義務についての履行補助者」と考えます。
そして、信義則上「賃借人Bの善管注意義務についての履行補助者」である同居人の妻Cの過失は、賃借人Bの過失と同視され(Bの過失と同じだと扱われる)、賃借人Bはその賠償責任を負うとしています。
噛み砕いて簡単に言いますと、Bは、妻Cの過失について「嫁がやったことだし。オレじゃねーし」と主張することは許されない、ということです。
誰の過失もなく建物が損傷・滅失した場合
賃借人(借主)または同居人の過失は、賃借人(借主)が責任を負います。
反対に、賃貸人(貸主・オーナー)に過失がある場合は、賃貸人(貸主・オーナー)が責任を負います。
では、誰の過失もなく、つまり、不可抗力で建物が損傷・滅失した場合(要するに誰も悪くない場合)は、一体どうなるのでしょうか?
民法では次のように規定します。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
民法611条
1項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
結論。
民法611条の規定により、その賃借物の滅失割合に応じて、当然に借賃が減額されます。
つまり、不動産賃貸借の場合、その不動産が不可抗力で一部損傷・滅失したときは、その不動産のダメージの割合に応じて当然に家賃が減額されます。
また、損傷・滅失した賃借物が、残存部分だけでは賃借の目的を達することができなければ、契約の解除をすることができます。
つまり、居住用の不動産賃貸借の場合、その居住用不動産が不可抗力で損傷・滅失したとき、残存部分だけでは住むことができないのあれば、賃借人(借主)は、賃貸借契約を解除できるということです。
なお、賃借物の全部が滅失したときは、滅失の原因の如何を問わず、賃貸借契約は解除を待たず当然に終了します。(民法616条の2)
ここでひとつ注意点です。
「解除を待たず当然に終了する」ということは、解除はできません。
賃借物の全部滅失によりすでに消賃貸借契約は消滅しているからです。
すでにゼロになっているもの(無くなっているもの)を解除することはできません。
この点はお気をつけください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【不動産賃貸借の基本】賃貸人たる地位の移転(オーナーチェンジ)と新賃貸人&賃借人の対抗要件(登記と引渡し)を初学者にもわかりやすく解説!
【不動産賃貸借の基本】賃貸人たる地位の移転(オーナーチェンジ)と新賃貸人&賃借人の対抗要件(登記と引渡し)を初学者にもわかりやすく解説!
-
 【賃借権の無断&適法な譲渡と転貸】賃貸人の解除権と信頼関係破壊の法理とは/賃借権が譲渡されると敷金や滞納家賃や必要費&有益費はどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
【賃借権の無断&適法な譲渡と転貸】賃貸人の解除権と信頼関係破壊の法理とは/賃借権が譲渡されると敷金や滞納家賃や必要費&有益費はどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【借地権】賃借権と地上権の違い/借地人の対抗要件と対抗力とは/借地上の建物滅失問題/借地人の賃借権の譲渡(転貸)を初学者にもわかりやすく解説!
【借地権】賃借権と地上権の違い/借地人の対抗要件と対抗力とは/借地上の建物滅失問題/借地人の賃借権の譲渡(転貸)を初学者にもわかりやすく解説!
-
 【賃借権の相続】賃貸人&相続人vs内縁の妻の対抗問題/賃料債権&債務の相続と不可分債務とは?わかりやすく解説!
【賃借権の相続】賃貸人&相続人vs内縁の妻の対抗問題/賃料債権&債務の相続と不可分債務とは?わかりやすく解説!
-
 【賃貸不動産の損傷&滅失】賃借人(借主)の同居人は履行補助者とは/不可抗力の建物損傷をわかりやすく解説!
【賃貸不動産の損傷&滅失】賃借人(借主)の同居人は履行補助者とは/不可抗力の建物損傷をわかりやすく解説!
-
 【賃貸借契約の存続期間】立ち退き請求と正当事由とは/建物築造(再築)による借地期間延長と地主の承諾の有無をわかりやすく解説!
【賃貸借契約の存続期間】立ち退き請求と正当事由とは/建物築造(再築)による借地期間延長と地主の承諾の有無をわかりやすく解説!
-
 【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!
【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!
-
 【定期借地&借家契約】定期借地権と定期建物賃貸借と取壊し予定の建物賃貸借と短期賃貸借とは?わかりやすく解説!
【定期借地&借家契約】定期借地権と定期建物賃貸借と取壊し予定の建物賃貸借と短期賃貸借とは?わかりやすく解説!
-