
【賃借権の無断&適法な譲渡と転貸】賃貸人の解除権と信頼関係破壊の法理とは/賃借権が譲渡されると敷金や滞納家賃や必要費&有益費はどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
▼この記事でわかること
・賃借権の無断譲渡・転貸
・賃借権を無断に譲渡・転貸することができない理由
・例外的に無断譲渡・転貸が認められるとき
・賃貸人(貸主・オーナー)の解除権
・信頼関係破壊の法理
・賃借権の適法な譲渡
・前借主の滞納家賃の問題
・必要費(修繕費)や有益費の問題
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

賃借権の無断譲渡・転貸
早速ですが、まずは事例をご覧ください。
事例1
BはA所有の甲建物を賃借している。
これだけでは、BがAから甲建物を借りて使用している、というだけの何の変哲もない不動産賃貸借ですが、問題はここからです。
この事例1で、AとBは、A所有の甲建物の賃貸借契約を結んでいます。
そして、A所有の甲建物の賃借人(借主)となったBは、甲建物の賃借権という権利を取得します。
賃借権とは、借りて利用する権利です。
つまり、賃借人Bは、甲建物を借りて利用する賃借権を持っています。
さて、それでは賃借人Bは、その賃借権を、他の誰かに譲り渡したり、また貸ししたりすることはできるのでしょうか?
これについて、民法は次の規定を置いています。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法612条
1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
これは、この民法612条の条文を読めば一目瞭然かと思います。
賃借権を譲り渡したり転貸(また貸し)したりするには、賃貸人(貸主・オーナー)の承諾が必要です。
ということで結論。
賃借人Bは、賃貸人Aの承諾なしに、甲建物の賃借権を、他の誰かに譲り渡したり転貸したりすることはできません。
もしそれに違反して、賃貸人Aの承諾なしで、勝手に賃借権を譲り渡したり転貸したりした場合は、上記の民法612条2項の規定により、賃貸人Aは、賃借人Bとの賃貸借契約を解除することができます。
賃借権を無断に譲渡・転貸することができない理由
例えば、家を借りて住もうとするとき、申し込みを入れてから契約に至るまでに、入居審査がありますよね?
それはつまり、オーナー(賃貸人)は入居者を選んでいるということです。
なぜ選ぶの?
それは、家賃滞納や夜逃げ、その他トラブルを避けたいからです。
当たり前の話ですよね。
つまり、今、賃貸物件を借りて住んでいる人は、オーナー(貸主)が「この人だったら大丈夫だな」と思ったので、入居できた訳です。
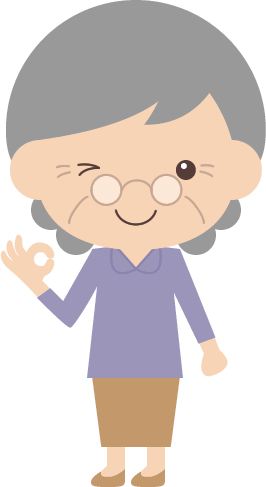
となると、せっかくオーナーが「この人だったら大丈夫だな」と入居者を選んだのに、賃借権を他の誰かに勝手に譲り渡されたり、他の誰かに勝手にまた貸し(転貸)されたりして、入居者が素性のわからない別の人に代わってしまったら、そもそも入居者審査をした意味がなくなります。
もし、賃借権を譲り渡した相手、また貸し(転貸)した相手が、ヤ◯ザだったりなど、とんでもない人だったらどうしましょう?
という訳なので、賃貸人(オーナー)の承諾なしに、賃借権の譲り渡しや転貸を勝手にすることはできないのです。
例外的に無断譲渡・転貸が認められる(賃貸人の解除権が制限される)こともある
賃貸人の承諾なしに賃借権を譲渡(譲り渡すこと)、転貸することができないのが、民法の原則です。
しかし、それが「原則」ということは、例外の場合もあります。
例外ってどんな場合?
これは民法の条文上でも借地借家法の条文上でもなく、判例で、次のような場合には、賃借権の無断譲渡・転貸も認められるとしています。
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」
これはどういう場合を指しているのかといいますと、賃貸人に実害がないであろうことが確実と言えるような場合です。
例えば、個人で事務所を借りている人が法人化して(会社になって)、結果的に賃借権が個人から法人(会社)に移っても、経営の実質は何の変わりなく事務所の使用にも何の影響もないような場合が、まさにその典型です。
「背信的行為」というのは「ルールにそむく行為」という意味です。
この場合のルールとは「無断譲渡・転貸はダメ」ですよね。
つまり「個人で事務所を借りている人が法人化して、結果的に賃借権が個人から法人に移っても、経営の実質は何の変わりなく、事務所の使用にも何の影響もないような場合」は背信的行為とまでは言えないから、例外的にこれを認め、このような場合には、賃貸人の解除権は制限されます。
賃貸人(貸主・オーナー)の解除権
事例2
BはA所有の甲建物を賃借している。BはAに無断で、Cと甲建物の転貸借契約を結んだ。なお、Bはまだ甲建物をCに引き渡していない。
これは、借り手である賃借人Bが貸し手である賃貸人Aの承諾なしに甲建物をまた貸しする契約をCと結んだ、つまり、借主の勝手なまた貸しという無断転貸のケースです。
そして、この事例2のポイントは「まだ甲建物をCに引き渡していない」ところです。
さて、この事例2で、賃貸人Aは、無断転貸をしたがまだその引渡しはしていない賃借人Bとの、甲建物の賃貸借契約を解除できるでしょうか?
結論。
賃貸人Aは、賃借人Bとの甲建物の賃貸借契約を解除することはできません。
これはちょっと意外な結果ではないでしょうか?
本来であれば、賃借人(借主)の無断転貸に対して、賃貸人(貸主・オーナー)は原則その賃貸借契約を解除できます。
しかし、事例2の場合、賃借人Bは、無断転貸をしたとはいえ、まだ甲建物をCへ引き渡していません。
そこで判例では、このような場合、無断で賃借人が転貸借契約をしたとはいえ、まだその引渡しを行なっていない以上、賃貸人と賃借人の「信頼関係は破壊されていない」ので解除できない、としています。
信頼関係破壊の法理

先ほど「信頼関係は破壊されていない」ので、その賃貸借契約は解除はできない、という旨の話をしましたが、これを信頼関係破壊の法理(理論)といいます。
ところで、不動産賃貸借契約は、実はそう簡単に解除することはできません。
不動産の「立ち退き問題」という言葉を耳にすることは割とよくあるか思いますが、この「不動産の立ち退き問題」を難しくしている原因に、実は「信頼関係破壊の法理」が影響しています。
これはどういう事かといいますと、例えば、BがA所有の甲アパートを借りて住んでいるとします。
そして、Bが1ヶ月分の家賃を滞納します。
すると、賃借人のBは債務不履行に陥ります。
債務不履行に陥るとは、簡単に言うと「約束を守らなかった(破った)」ということです。
そして、債務不履行にはペナルティがあります。
そのひとつが契約解除です。
債務不履行は契約の解除の原因になります。
債権者は債務不履行に陥った債務者に、相当の期間を定めて催告した上で、その契約を解除することができます。
しかし!
不動産賃貸借の場合は、そう簡単にはいきません。
賃貸人A(貸主・オーナー)は、賃借人B(借主)が1ヶ月分の家賃を滞納した、というだけでは、甲アパートの賃貸借契約を解除することはできません。
なぜなら、それだけでは「信頼関係が破壊されたとは言えない」と判断されるからです。
このようにして、信頼関係破壊の法理が働くのです。
じゃあ賃借人Bはいつまでも家賃を滞納できちゃうの?
当然そういう訳ではありません。
通常は、賃借人の家賃滞納については、3ヶ月分は滞納しないと、賃貸人は賃貸借契約の解除はできないとされています。
つまり、賃借人Bの家賃滞納が3ヶ月分までいけば、そこで「信頼関係が破壊された」と判断され、賃貸人Aは、賃借人Bとの甲アパートの賃貸借契約を解除できます。
もちろん、家賃滞納以外に信頼関係を破壊するような事由があれば、家賃滞納があろうがなかろうが、賃貸借契約を解除できます。
以上、ざっくりと噛み砕いて簡単にまとめますとこうです。
信頼関係破壊の法理が働くことにより、賃貸人は、家賃滞納については、少なくとも3ヶ月分の家賃滞納がなければ、その賃貸借契約を解除できない。
つまり、賃借人の滞納家賃が3ヶ月分までいって初めて、賃貸人は賃借人に対し「出てけ!」と言える、ということです。
【補足】
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」とは、言葉を変えれば「信頼関係が破壊されたとは認められないとき」ということです。
不動産賃貸借について考えるとき「信頼関係破壊の法理」は非常に重要になりますので、是非覚えておいてください。
なお、不動産の家賃滞納、立ち退きの問題は、まだまだ深い問題がございます。
ですので、その問題につきましては、また別途改めて取り上げたいと存じます。
賃借権の適法な譲渡
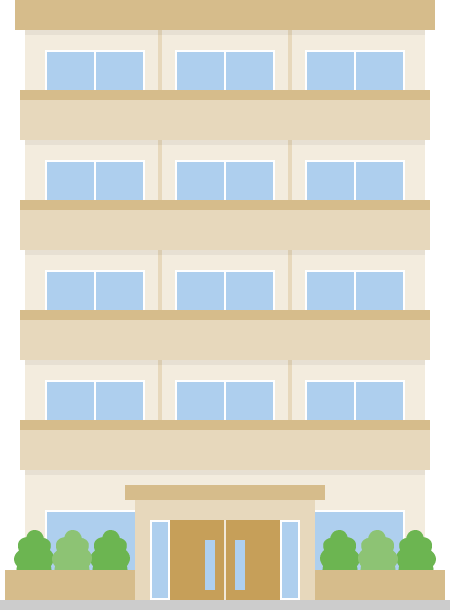
事例3
BはA所有の甲建物を賃借している。その後、BはAの承諾を得て、その賃借権をCに譲渡した。
これは、借り手である賃借人Bが、貸し手である賃貸人Aの承諾を得て、適法に甲建物を借りて利用する権利(賃借権)をCに譲渡した、というケースです。
さて、この事例で、Bは賃貸人Aに対し、敷金の返還請求ができるでしょうか?
結論。
BはAに対し、敷金の返還請求ができます。
この結論の法的な論理はこうです。
賃借人Bは、適法にCへ賃借権を譲渡したことにより、賃貸借契約から離脱します。
すると、Bは甲建物の借り手、すなわち賃借人(借主)ではなくなります。
甲建物の賃借人ではなくなるということは、甲建物を借りて利用するため(賃借するため)の担保として賃貸人(貸主・オーナー)Aに預けている敷金は、その役割がなくなります。
敷金は家賃不払いなどのための担保として、借り手である賃借人から貸し手である賃貸人へと預けるお金です。
もはや賃借人ではなくなり、賃借人としての債務(借り手としての義務)もなくなったBが、賃貸人(貸主・オーナー)Aに、賃借人(借主)の債務の担保として敷金を預けておく、というのはおかしな話です。
したがいまして、Cへ適法に賃借権を譲渡して、甲建物の賃貸借契約から離脱したBは、Aに対し敷金の返還請求ができるのです。
なお、適法に賃借権が「旧賃借人→新賃借人」と譲渡されても、敷金についての権利義務関係が当然に「旧賃借人→新賃借人」と引き継がれることはありません。
特段の事情がない限りは、AB間の「敷金についての権利義務関係」が終了して、AC間に新たな敷金の権利義務関係ができる、という形になります。
だからこそ、AはBに対し敷金返還請求ができるという訳です。
ここはオーナーチェンジの場合とは異なっていますので、ご注意ください。
ちなみに、現実の実務においては、賃貸人(貸主・オーナー)のAが、賃借権の譲渡の承諾を与える際に、新たに賃借人となるCから敷金を受領すること(Cに敷金を払わせること)を条件としますので、旧賃借人のBに敷金を返還しても、賃貸人(貸主・オーナー)のAには何の問題もありません。
前借主の滞納家賃はどうなる?
適法に賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は賃貸借契約から離脱します。
事例3の場合、Bが賃貸借契約から離脱し、AC間の賃貸借契約がスタートします。
さて、では事例3で、適法に賃借権を譲渡する前に、Bに滞納家賃があった場合、その滞納家賃の行方はどうなるのでしょうか?
これについては、BからCに債務引受などがされない限り、Cに引き継がれることはありません。
したがいまして、賃貸人(貸主・オーナー)Aは、賃借権の譲渡前の滞納家賃については、旧賃借人Bに対して請求することになります。
つまり、賃貸借契約から離脱したとはいえ、旧賃借人Bには賃借権の譲渡前の家賃支払い債務は残るので、それで滞納家賃がチャラになるわけではないのです。
世の中それほど甘くありません。
補足:必要費(修繕費)や有益費は?
必要費とは、建物の修繕費です。
賃借人が支出した必要費は、直ちに賃貸人に償還請求できます。
では、事例のBに、賃借権の譲渡前に支出した必要費があった場合、その必要費の行方はどうなるのでしょうか?
これについては、BからCに債権譲渡がされない限り、Cに引き継がれることはありません。
したがいまして、賃借権の譲渡前に支出した必要費がある場合、その償還請求は、旧賃借人のBが賃貸人(貸主・オーナー)Aに対して行います。
また、有益費についてですが、有益費とは、建物の価値を増大するための費用です。
通常、有益費は、賃貸借契約終了時に、その償還請求ができます。
となると、事例3で、賃借権の譲渡前に、賃貸人(貸主・オーナー)Aに有益費の支出があった場合、その償還請求を行うのは旧賃借人Bと新賃借人C、どちらになるのでしょうか?
これについては、争いがあります。争いがあるということは、結論が割れているということです。
この問題については、これ以上の解説は割愛しますが、とりあえず「結論が定まっていない」ということだけ、覚えておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・賃借権の無断譲渡・転貸
・賃借権を無断に譲渡・転貸することができない理由
・例外的に無断譲渡・転貸が認められるとき
・賃貸人(貸主・オーナー)の解除権
・信頼関係破壊の法理
・賃借権の適法な譲渡
・前借主の滞納家賃の問題
・必要費(修繕費)や有益費の問題
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者にもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。

賃借権の無断譲渡・転貸
早速ですが、まずは事例をご覧ください。
事例1
BはA所有の甲建物を賃借している。
これだけでは、BがAから甲建物を借りて使用している、というだけの何の変哲もない不動産賃貸借ですが、問題はここからです。
この事例1で、AとBは、A所有の甲建物の賃貸借契約を結んでいます。
そして、A所有の甲建物の賃借人(借主)となったBは、甲建物の賃借権という権利を取得します。
賃借権とは、借りて利用する権利です。
つまり、賃借人Bは、甲建物を借りて利用する賃借権を持っています。
さて、それでは賃借人Bは、その賃借権を、他の誰かに譲り渡したり、また貸ししたりすることはできるのでしょうか?
これについて、民法は次の規定を置いています。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法612条
1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
これは、この民法612条の条文を読めば一目瞭然かと思います。
賃借権を譲り渡したり転貸(また貸し)したりするには、賃貸人(貸主・オーナー)の承諾が必要です。
ということで結論。
賃借人Bは、賃貸人Aの承諾なしに、甲建物の賃借権を、他の誰かに譲り渡したり転貸したりすることはできません。
もしそれに違反して、賃貸人Aの承諾なしで、勝手に賃借権を譲り渡したり転貸したりした場合は、上記の民法612条2項の規定により、賃貸人Aは、賃借人Bとの賃貸借契約を解除することができます。
賃借権を無断に譲渡・転貸することができない理由
例えば、家を借りて住もうとするとき、申し込みを入れてから契約に至るまでに、入居審査がありますよね?
それはつまり、オーナー(賃貸人)は入居者を選んでいるということです。
なぜ選ぶの?
それは、家賃滞納や夜逃げ、その他トラブルを避けたいからです。
当たり前の話ですよね。
つまり、今、賃貸物件を借りて住んでいる人は、オーナー(貸主)が「この人だったら大丈夫だな」と思ったので、入居できた訳です。
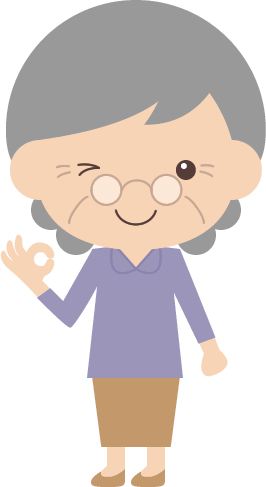
となると、せっかくオーナーが「この人だったら大丈夫だな」と入居者を選んだのに、賃借権を他の誰かに勝手に譲り渡されたり、他の誰かに勝手にまた貸し(転貸)されたりして、入居者が素性のわからない別の人に代わってしまったら、そもそも入居者審査をした意味がなくなります。
もし、賃借権を譲り渡した相手、また貸し(転貸)した相手が、ヤ◯ザだったりなど、とんでもない人だったらどうしましょう?
という訳なので、賃貸人(オーナー)の承諾なしに、賃借権の譲り渡しや転貸を勝手にすることはできないのです。
例外的に無断譲渡・転貸が認められる(賃貸人の解除権が制限される)こともある
賃貸人の承諾なしに賃借権を譲渡(譲り渡すこと)、転貸することができないのが、民法の原則です。
しかし、それが「原則」ということは、例外の場合もあります。
例外ってどんな場合?
これは民法の条文上でも借地借家法の条文上でもなく、判例で、次のような場合には、賃借権の無断譲渡・転貸も認められるとしています。
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」
これはどういう場合を指しているのかといいますと、賃貸人に実害がないであろうことが確実と言えるような場合です。
例えば、個人で事務所を借りている人が法人化して(会社になって)、結果的に賃借権が個人から法人(会社)に移っても、経営の実質は何の変わりなく事務所の使用にも何の影響もないような場合が、まさにその典型です。
「背信的行為」というのは「ルールにそむく行為」という意味です。
この場合のルールとは「無断譲渡・転貸はダメ」ですよね。
つまり「個人で事務所を借りている人が法人化して、結果的に賃借権が個人から法人に移っても、経営の実質は何の変わりなく、事務所の使用にも何の影響もないような場合」は背信的行為とまでは言えないから、例外的にこれを認め、このような場合には、賃貸人の解除権は制限されます。
賃貸人(貸主・オーナー)の解除権
事例2
BはA所有の甲建物を賃借している。BはAに無断で、Cと甲建物の転貸借契約を結んだ。なお、Bはまだ甲建物をCに引き渡していない。
これは、借り手である賃借人Bが貸し手である賃貸人Aの承諾なしに甲建物をまた貸しする契約をCと結んだ、つまり、借主の勝手なまた貸しという無断転貸のケースです。
そして、この事例2のポイントは「まだ甲建物をCに引き渡していない」ところです。
さて、この事例2で、賃貸人Aは、無断転貸をしたがまだその引渡しはしていない賃借人Bとの、甲建物の賃貸借契約を解除できるでしょうか?
結論。
賃貸人Aは、賃借人Bとの甲建物の賃貸借契約を解除することはできません。
これはちょっと意外な結果ではないでしょうか?
本来であれば、賃借人(借主)の無断転貸に対して、賃貸人(貸主・オーナー)は原則その賃貸借契約を解除できます。
しかし、事例2の場合、賃借人Bは、無断転貸をしたとはいえ、まだ甲建物をCへ引き渡していません。
そこで判例では、このような場合、無断で賃借人が転貸借契約をしたとはいえ、まだその引渡しを行なっていない以上、賃貸人と賃借人の「信頼関係は破壊されていない」ので解除できない、としています。
信頼関係破壊の法理

先ほど「信頼関係は破壊されていない」ので、その賃貸借契約は解除はできない、という旨の話をしましたが、これを信頼関係破壊の法理(理論)といいます。
ところで、不動産賃貸借契約は、実はそう簡単に解除することはできません。
不動産の「立ち退き問題」という言葉を耳にすることは割とよくあるか思いますが、この「不動産の立ち退き問題」を難しくしている原因に、実は「信頼関係破壊の法理」が影響しています。
これはどういう事かといいますと、例えば、BがA所有の甲アパートを借りて住んでいるとします。
そして、Bが1ヶ月分の家賃を滞納します。
すると、賃借人のBは債務不履行に陥ります。
債務不履行に陥るとは、簡単に言うと「約束を守らなかった(破った)」ということです。
そして、債務不履行にはペナルティがあります。
そのひとつが契約解除です。
債務不履行は契約の解除の原因になります。
債権者は債務不履行に陥った債務者に、相当の期間を定めて催告した上で、その契約を解除することができます。
しかし!
不動産賃貸借の場合は、そう簡単にはいきません。
賃貸人A(貸主・オーナー)は、賃借人B(借主)が1ヶ月分の家賃を滞納した、というだけでは、甲アパートの賃貸借契約を解除することはできません。
なぜなら、それだけでは「信頼関係が破壊されたとは言えない」と判断されるからです。
このようにして、信頼関係破壊の法理が働くのです。
じゃあ賃借人Bはいつまでも家賃を滞納できちゃうの?
当然そういう訳ではありません。
通常は、賃借人の家賃滞納については、3ヶ月分は滞納しないと、賃貸人は賃貸借契約の解除はできないとされています。
つまり、賃借人Bの家賃滞納が3ヶ月分までいけば、そこで「信頼関係が破壊された」と判断され、賃貸人Aは、賃借人Bとの甲アパートの賃貸借契約を解除できます。
もちろん、家賃滞納以外に信頼関係を破壊するような事由があれば、家賃滞納があろうがなかろうが、賃貸借契約を解除できます。
以上、ざっくりと噛み砕いて簡単にまとめますとこうです。
信頼関係破壊の法理が働くことにより、賃貸人は、家賃滞納については、少なくとも3ヶ月分の家賃滞納がなければ、その賃貸借契約を解除できない。
つまり、賃借人の滞納家賃が3ヶ月分までいって初めて、賃貸人は賃借人に対し「出てけ!」と言える、ということです。
【補足】
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」とは、言葉を変えれば「信頼関係が破壊されたとは認められないとき」ということです。
不動産賃貸借について考えるとき「信頼関係破壊の法理」は非常に重要になりますので、是非覚えておいてください。
なお、不動産の家賃滞納、立ち退きの問題は、まだまだ深い問題がございます。
ですので、その問題につきましては、また別途改めて取り上げたいと存じます。
賃借権の適法な譲渡
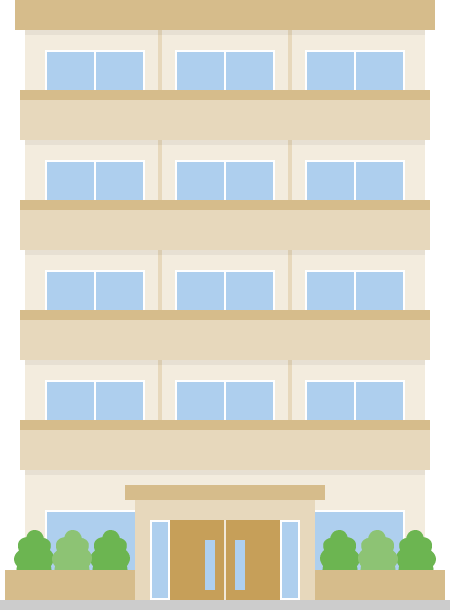
事例3
BはA所有の甲建物を賃借している。その後、BはAの承諾を得て、その賃借権をCに譲渡した。
これは、借り手である賃借人Bが、貸し手である賃貸人Aの承諾を得て、適法に甲建物を借りて利用する権利(賃借権)をCに譲渡した、というケースです。
さて、この事例で、Bは賃貸人Aに対し、敷金の返還請求ができるでしょうか?
結論。
BはAに対し、敷金の返還請求ができます。
この結論の法的な論理はこうです。
賃借人Bは、適法にCへ賃借権を譲渡したことにより、賃貸借契約から離脱します。
すると、Bは甲建物の借り手、すなわち賃借人(借主)ではなくなります。
甲建物の賃借人ではなくなるということは、甲建物を借りて利用するため(賃借するため)の担保として賃貸人(貸主・オーナー)Aに預けている敷金は、その役割がなくなります。
敷金は家賃不払いなどのための担保として、借り手である賃借人から貸し手である賃貸人へと預けるお金です。
もはや賃借人ではなくなり、賃借人としての債務(借り手としての義務)もなくなったBが、賃貸人(貸主・オーナー)Aに、賃借人(借主)の債務の担保として敷金を預けておく、というのはおかしな話です。
したがいまして、Cへ適法に賃借権を譲渡して、甲建物の賃貸借契約から離脱したBは、Aに対し敷金の返還請求ができるのです。
なお、適法に賃借権が「旧賃借人→新賃借人」と譲渡されても、敷金についての権利義務関係が当然に「旧賃借人→新賃借人」と引き継がれることはありません。
特段の事情がない限りは、AB間の「敷金についての権利義務関係」が終了して、AC間に新たな敷金の権利義務関係ができる、という形になります。
だからこそ、AはBに対し敷金返還請求ができるという訳です。
ここはオーナーチェンジの場合とは異なっていますので、ご注意ください。
ちなみに、現実の実務においては、賃貸人(貸主・オーナー)のAが、賃借権の譲渡の承諾を与える際に、新たに賃借人となるCから敷金を受領すること(Cに敷金を払わせること)を条件としますので、旧賃借人のBに敷金を返還しても、賃貸人(貸主・オーナー)のAには何の問題もありません。
前借主の滞納家賃はどうなる?
適法に賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は賃貸借契約から離脱します。
事例3の場合、Bが賃貸借契約から離脱し、AC間の賃貸借契約がスタートします。
さて、では事例3で、適法に賃借権を譲渡する前に、Bに滞納家賃があった場合、その滞納家賃の行方はどうなるのでしょうか?
これについては、BからCに債務引受などがされない限り、Cに引き継がれることはありません。
したがいまして、賃貸人(貸主・オーナー)Aは、賃借権の譲渡前の滞納家賃については、旧賃借人Bに対して請求することになります。
つまり、賃貸借契約から離脱したとはいえ、旧賃借人Bには賃借権の譲渡前の家賃支払い債務は残るので、それで滞納家賃がチャラになるわけではないのです。
世の中それほど甘くありません。
補足:必要費(修繕費)や有益費は?
必要費とは、建物の修繕費です。
賃借人が支出した必要費は、直ちに賃貸人に償還請求できます。
では、事例のBに、賃借権の譲渡前に支出した必要費があった場合、その必要費の行方はどうなるのでしょうか?
これについては、BからCに債権譲渡がされない限り、Cに引き継がれることはありません。
したがいまして、賃借権の譲渡前に支出した必要費がある場合、その償還請求は、旧賃借人のBが賃貸人(貸主・オーナー)Aに対して行います。
また、有益費についてですが、有益費とは、建物の価値を増大するための費用です。
通常、有益費は、賃貸借契約終了時に、その償還請求ができます。
となると、事例3で、賃借権の譲渡前に、賃貸人(貸主・オーナー)Aに有益費の支出があった場合、その償還請求を行うのは旧賃借人Bと新賃借人C、どちらになるのでしょうか?
これについては、争いがあります。争いがあるということは、結論が割れているということです。
この問題については、これ以上の解説は割愛しますが、とりあえず「結論が定まっていない」ということだけ、覚えておいていただければと存じます。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【不動産賃貸借の基本】賃貸人たる地位の移転(オーナーチェンジ)と新賃貸人&賃借人の対抗要件(登記と引渡し)を初学者にもわかりやすく解説!
【不動産賃貸借の基本】賃貸人たる地位の移転(オーナーチェンジ)と新賃貸人&賃借人の対抗要件(登記と引渡し)を初学者にもわかりやすく解説!
-
 【賃借権の無断&適法な譲渡と転貸】賃貸人の解除権と信頼関係破壊の法理とは/賃借権が譲渡されると敷金や滞納家賃や必要費&有益費はどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
【賃借権の無断&適法な譲渡と転貸】賃貸人の解除権と信頼関係破壊の法理とは/賃借権が譲渡されると敷金や滞納家賃や必要費&有益費はどうなる?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【借地権】賃借権と地上権の違い/借地人の対抗要件と対抗力とは/借地上の建物滅失問題/借地人の賃借権の譲渡(転貸)を初学者にもわかりやすく解説!
【借地権】賃借権と地上権の違い/借地人の対抗要件と対抗力とは/借地上の建物滅失問題/借地人の賃借権の譲渡(転貸)を初学者にもわかりやすく解説!
-
 【賃借権の相続】賃貸人&相続人vs内縁の妻の対抗問題/賃料債権&債務の相続と不可分債務とは?わかりやすく解説!
【賃借権の相続】賃貸人&相続人vs内縁の妻の対抗問題/賃料債権&債務の相続と不可分債務とは?わかりやすく解説!
-
 【賃貸不動産の損傷&滅失】賃借人(借主)の同居人は履行補助者とは/不可抗力の建物損傷をわかりやすく解説!
【賃貸不動産の損傷&滅失】賃借人(借主)の同居人は履行補助者とは/不可抗力の建物損傷をわかりやすく解説!
-
 【賃貸借契約の存続期間】立ち退き請求と正当事由とは/建物築造(再築)による借地期間延長と地主の承諾の有無をわかりやすく解説!
【賃貸借契約の存続期間】立ち退き請求と正当事由とは/建物築造(再築)による借地期間延長と地主の承諾の有無をわかりやすく解説!
-
 【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!
【賃貸借の終了】必要費と有益費・価値増加現存分の償還請求とは?造作買取請求権と建物買取請求権とは?わかりやすく解説!
-
 【定期借地&借家契約】定期借地権と定期建物賃貸借と取壊し予定の建物賃貸借と短期賃貸借とは?わかりやすく解説!
【定期借地&借家契約】定期借地権と定期建物賃貸借と取壊し予定の建物賃貸借と短期賃貸借とは?わかりやすく解説!
-