
▼この記事でわかること
・取消権者と取消しの効果
・制限行為能力者の追認
・法定追認について
・相手方の催告権
・制限行為能力者の詐術
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

制限行為能力者の
取消権者と取消しの効果
未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者の契約等の法律行為には、法律による制限や保護があります。
そのひとつに、制限行為能力者が単独で有効にできる法律行為を限定し、もし単独で行ってしまったとしても後から取り消すことができる、という制度があります。
ところで、制限行為能力者が単独でした契約等の法律行為を取り消すことができるのは、一体誰なのでしょうか?
それは民法120条により、次のように規定されています。
(取消権者)
民法120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
上記、民法120条の規定により、制限行為能力者の法律行為を取り消せるのは「制限行為能力者・代理人・承継人・同意ができる者」となります。
制限行為能力者というのは、制限行為能力者本人です。
代理人というのは、未成年者であれば法定代理人(子供の親など)、成年被後見人であれば成年後見人になります。
承継人というのは、もっともわかりやすいところだと、相続人がそうです。
つまり、承継人が取り消す場合というのは、成年被後見人が法律行為を取り消す前に死亡し、相続人となった息子がその法律行為を取り消す、というようなことです。
同意ができる者というのは、保佐人・補助人を指すと思っていただいて良いでしょう。
つまり、被保佐人が単独でした法律行為を後に保佐人が取り消す、といったことです。
取消しの効果
さて、制限行為能力者が単独でした法律行為を取り消せるのは誰なのかはわかりました。
では、実際に取り消した後は一体どうなるのでしょうか?
これについての民法の規定はこちらです。
(取消しの効果)
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
上記、民法121条により、取消しの効果は遡及(そきゅう)します。
遡及というのは「さかのぼって及ぶ」ということです。
つまり、取消しの効果は「さかのぼって無かったことになる」ということです。
そして、さかのぼって無かったことになると、後は原状回復という流れになります。
(こちら【不当利得】受益者が善意か悪意かで返還すべき利益が変わる?/現存利益の範囲とは?わかりやすく解説!の解説も参考まで)
(原状回復の義務)
民法121条の2
3項 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
制限行為能力者は
取り消した事を取り消せるか
なんだかややこしいですが、要するに、制限行為能力者が「この前の取消し、やっぱナシで!」と言えるか、ということです。
結論は、取消しを取り消すことはできません。
そもそも、取消しの取消しなんてことがまかり通ってしまったら、法的安定性が保たれず、世の中が混乱してしまいかねません。
それに、取消しが取り消せなくても、おそらく損害が生じることはないでしょう。
なぜなら、取り消すと初めから無かったことになり元に戻るだけなので、もし取り消さなければ何らかのプラスがあったとしても、取消しを取り消せなかったところで、ゼロに戻るだけでマイナスはないでしょう。
したがって、取消しを取り消すことはできません。
制限行為能力者の追認
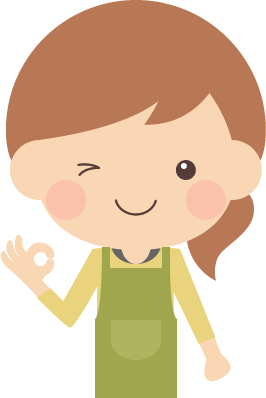
追認とは、後から追って認める、ということです。
例えば、制限行為能力者(例えば子供や成年被後見人)が単独では有効にならない法律行為をした後、法律で規定された者(例えばその子供の親や成年後見人)が、その法律行為を後から「それOK」と追認することによって、制限行為能力者が単独で行ったその法律行為は有効になります。
では、追認権を行使できるのは一体誰なのでしょうか?
民法122条の条文を読むと「120条に規定する取消権者」が追認できる者、ということになりますが、ここでひとつ問題があります。
というのは、もし取消権者=追認権者となると、例えば、子供が単独でした行為を、子供自身で追認することも可能になってしまいます。
あるいは、痴呆になって成年被後見人となった老人が単独でした行為を、老人自身で追認することもできてしまいます。
それってマズイですよね。
事例
お金持ちのお坊っちゃんの未成年者Aは、自己所有の高級ジュエリーをBに売り渡した。その後、Aはその行為(高級ジュエリーの売渡し)を追認した。
この事例のようなケースで、仮に次のような文言が入った売買契約書をAB間で交わしていたらどうなるでしょう?
「売主Aはこの売買契約を追認する」
もし「取消権者=追認権者」だから、未成年者自身も追認できるとなると、上記のような契約も可能になってしまいます。
となると、法律による制限行為能力者の保護の意味がなくなってしまいますよね。
この問題を民法はどう解決するのか?
民法では、以下の条文で規定しています。
(追認の要件)
民法124条1項
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
この民法124条1項が何を言っているのかといいますと「制限行為能力者が自分自身で追認するには制限行為能力者じゃなくなってからじゃないとダメ!」ということです。
条文の「取消しの原因」というのが「制限行為能力者であること」にあたりますので、その状況が消滅した後というのは「制限行為能力者でなくなった後」ということになります。
したがいまして、制限行為能力者が単独した行為を、制限行為能力者自身で追認することはできません。
ですので、事例の未成年者Bが、高級ジュエリーの売渡し行為を自ら追認することはできません。
もし、Aが自分自身で追認するには、A自身が成年になってからでないとできません。
なお、未成年者Aの法定代理人が追認することは当然できます。
多くの場合、未成年者の法定代理人は親権者(通常は親)なので、Aの親が、AからBへの高級ジュエリーの売渡し行為を追認すれば、それは当然に有効になります。
念のため申し上げておきます。
成年被後見人の追認の場合
未成年者の場合は、自らが成年になってからでないと自分自身で追認できないように、成年被後見人は行為能力者となってから、つまり、自らが成年被後見人でなくなって自らの行為を認識してからでないと自分自身で追認できません。
なお、これは被保佐人・被補助人も同様になります。
【補足」
民法124条1項の規定は「詐欺・強迫」についても適用があります。
つまり、騙されたり脅されたりした被害者が、騙されたことに気づいたり脅された状態から脱した後であれば、被害者自身で、詐欺・強迫によってした法律行為を追認できるということです。
ちょっと細かい話ですが、一応、頭の片隅に入れておいていただければと存じます。
なお、これは誰がする場合に限らずですが、一度追認した行為は、もはや取り消すことはできません。
追認も取消しも、できるのは一度までです。
そうでないと、法的安定性が損なわれてしまうからです。
この点もご注意ください。
法定追認について
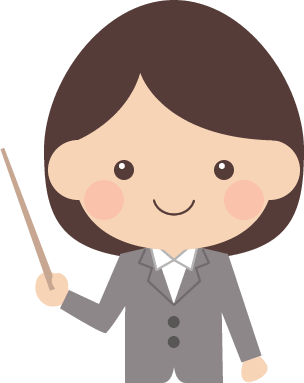
通常の追認は、追認権を持つ者が「その法律行為を追認します」と追認することにより行います。
しかし、それ以外にも追認する方法があります。
それが法定追認です。
法定追認とは、追認権者が追認の意思表示をしなくとも、ある一定の行為を行った場合は、法律上当然に追認したとみなされる、というものです。
つまり、追認権を持っている人が「追認します」と言わなくても、ある一定の行為を行ってしまった場合は、法律が勝手に「おまえのとった行動は追認したのと一緒だ!」として、法律上の追認として扱われてしまうということです。
そして、その「法律上追認したとみなされてしまう行為」が、民法125条により規定されています。
それは以下になります。
【法定追認される行為】民法125条抜粋
1 全部又は一部の履行
2 履行の請求
3 更改
4 担保の供与
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6 強制執行(自らが強制執行をする場合のみ)
これだけだと今ひとつよくわかりませんよね。
次の事例をもとに、ひとつひとつ解説して参ります。
事例
相続により甲土地を取得した未成年者Aは、単独で甲土地をBに売却した。
1・全部又は一部の履行
この事例で、制限行為能力者である未成年者Aが単独で行った甲土地の売買契約は、有効に成立していません。
では、Aが成年となってから、すなわち行為能力者となってから、追認も取消しもしないまま甲土地をBに引き渡したとしましょう。
あるいはBから、代金の全額または一部の支払いを受けたとしましょう。
するとAは、甲土地の売買契約を追認したとみなされます。
たとえ追認する気がなかったとしてもです。
これが法定追認の効果です。
2・履行の請求
この事例で、Aが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金を払ってくれ」と請求すると、その時点で、Aは甲土地の売買契約を追認したとみなされます。
3・更改
更改に関しては、初学者の方はすっ飛ばしてもかまいません。ですので、ざっくり申し上げておきます。
事例で、Aが一定の年齢に達し成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま甲土地の売買契約を乙土地の売買契約に変えた、というようなケースです。
この場合も、Aは追認したとみなされます。
4・担保の供与
担保というものについての詳細はここでは割愛しますが、法定追認においての担保の供与についての簡単な説明は、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま、Bからお金の代わりに何らかの物を受け取ったような場合です。
そのような場合も、Aは追認したとみなされます。
これだけだとピンと来ないと思いますが、とりあえず、このような規定もあるということだけ、何となく覚えておいてください。
そして後々、担保物権等を学習してから思い出していただければと存じます。
5・取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
これは、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金はCに払ってくれ」と言って、甲土地の売買代金を受け取る権利(債権)を他人に譲り渡すと、その時点でAは追認したとみなされます。
ちなみに、このようなAの行為を債権譲渡といいます。
要するに、債権譲渡にも追認効果があるということです。
(債権譲渡の基本についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権は譲れる?譲るとどうなる?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
6・強制執行(自ら強制執行する場合のみ)
強制執行についてを今ここで詳しく説明しようとすると、内容がテンコ盛りになり過ぎて逆に訳がわからなくなってしまいますので、超ざっくり申します。
事例でAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしていない状況で、裁判所の力を使って問答無用でBにお金を払わせることです。
超ざっくりで申し訳ございません(笑)。
とりあえず、そのような場合もAは追認したとみなされる、ということを頭に入れておいてください。
(強制執行の基本についての詳しい解説は「【差押え&強制執行&破産の超基本】借金で考える債権の世界~債務者に財産が無いとどうなる?わかりやすく解説!」をご覧ください)
【補足】
追認は、追認権者が取消権を有することを知らずにした場合はその効果を生じません。
追認は、取消権を持っている事を知った上で行うものです。
相手方の催告権
制限行為能力者が、単独では有効にできない法律行為を単独でした場合、その法律行為の相手方は、取り消されるか追認されるかされるまでは、言ってみれば宙ぶらりんの状態です。
事例
被保佐人のAは、単独で自己所有の甲土地をBに売却した。※
※被保佐人は民法13条の規定により、単独で有効に不動産の売買契約を結ぶことはできません。
この事例の場合、売主側の追認がない限り、買主のBは甲土地を手に入れることができません。
その上、取り消されない限りは追認の場合の支払い債務も考えて、代金の準備を欠かすわけにもいきません。
これは買主Bとしては、非常に厄介な状況ですよね。気の毒とも言えます。
そこで民法は、このような宙ぶらりんの状態にされた制限行為能力者の相手方に、催告権という救いの手を差し伸べています。
催告権とは
宙ぶらりんにされた制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者側に対し1ヶ月以上の期間を定めて「追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と求めることができます。
この権利を催告権といいます。
そしてこの催告権は、ただ相手に答えを求めるだけの権利ではありません。そこには法的効果が存在します。
そしてその法的効果は、催告をする相手によって変わってきます。
それでは、催告権の法的効果の違いについて、事例にあてはめて考えていきます。
被保佐人Aに対し催告した場合
買主Bが、1ヶ月以上の期間を定めた上で被保佐人Aに対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合、まず被保佐人Aは、定められた期間内に、追認するか取り消すかの選択をしなければなりません。
ここまでは当たり前のことです。
では、定められた期間内に被保佐人Aが返事をしなかった場合どうなるでしょうか?
この場合、被保佐人Aは甲土地の売買契約を取り消したとみなされます。
これが、民法が制限行為能力者の相手方に与えた救いの手、催告権の法的効果です。
つまり、買主Bは、催告することによって、自分から宙ぶらりんの状態を脱することができます。
なぜ制限行為能力者の返事がない場合、取り消したみなすかといいますと、宙ぶらりん状態の解消はもちろんですが、取り消したとみなす分には制限行為能力者への損害が生じる可能性はないと考えられるからです。
元の状態に戻るだけなので。
被保佐人Aの保護者「保佐人」に催告した場合
では、買主Bが1ヶ月以上の期間を定めた上で、今度は被保佐人Aの保護者の保佐人に対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合は、どうなるのでしょうか?
この場合、Aの保護者である保佐人が、定められた期間内に追認するか取り消すかの返事をすることになりますが、もしこのとき、保佐人が定められた期間内に返事をしないとどうなるでしょう?
なんとこの場合、保佐人は追認したとみなされます。
なぜ保佐人の場合はこのようになるかといいますと、保佐人には通常の判断能力(意思能力)があるからです。
通常の判断能力で考えて結論を出せるはずだからです。
したがって、買主BがAの保佐人に催告し、期間内に返事がなかった場合は、保佐人は追認したとみなされるのです。
このように、制限行為能力者の相手方には、催告権という救いの一手が与えられていて、誰に催告するかによってその法的効果は変わってきます。
つまり、こういった形で、制限行為能力者の保護と制限行為能力者の相手方の公平をコントロールしているということです。
制限行為能力者の詐術

制限行為能力の制度に定められた制限行為能力者の単独でした法律行為が取り消せることはすでに解説済みですが、実は、制限行為能力者がした法律行為でも、取り消せないものがあります。
それは制限行為能力者の詐術です。
事例
17歳の未成年者Aは免許証を偽造し、Bと甲不動産の売買契約を締結した。
さて、この事例で、Aは未成年者(制限行為能力者)ということを理由に、Bと結んだ甲不動産の売買契約を取り消すことができるでしょうか?
結論。
Aは未成年者を理由に甲不動産の売買契約を取り消すことができません。
なぜなら、Aは詐術を用いているからです。
詐術というのはウソをつくことです。
民法の規定はこちらです。
(制限行為能力者の詐術)
民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
いくら制限行為能力者だからといって、自分は行為能力者であると自ら相手を騙しておいて、後からやっぱり制限行為能力者なので取り消します、なんてことを許してしまうのは信義に反します。
よって、民法21条の規定により、自ら詐術を用いた制限行為能力者の行為は、取り消すことができません。
また、こう考えることもできます。
制限行為能力者の保護は、制限行為能力者の判断能力(意思能力)には問題があると考えられるからですが、判断能力(意思能力)に問題がある人間が、自ら考えて詐術を用いることができるでしょうか?
むしろ、そこまで考えて実行している時点で、そこまで頭が回っているってことですよね?
ということから、制限行為能力者が詐術を使って制限行為能力者ではないと相手を誤信させて行った行為は取り消すことはできない、と考えることもできます。
第三者が詐術を用いた場合
例えば、未成年者自らでなく、第三者が「あいつは成人だから大丈夫だよ」といって相手方が誤信してしまった場合は、どうなるでしょうか?
この場合、未成年者自身は何も悪くありません。
むしろ、大人っぽい見た目が災いしただけの被害者とも言えるかもしれません。
したがいまして、このようなケースでは取消権の行使は可能です。
民法21条の規定は、あくまで自ら詐術を用いた制限行為能力者に対するペナルティなのです。
【補足】
一口に詐術といっても、一体どこまでが詐術となるのでしょうか?
判例では以下のように示しています。
「民法21の詐術とは、積極的術策を用いた場合だけでなく、制限行為能力者がその旨を黙秘していた場合でも、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合には、なお詐術にあたる。しかし、単に制限行為能力者であることを黙認したのみでは、詐術にはあたらない」
この判例で何を言っているかといいますと、要するに、制限行為能力者が自分から積極的に詐術を用いていなくとも詐術にあたる場合がある、ということです。
例えば、未成年者が「私は成年です」という旨を言わなくても、会話の中で「この前飲みに行った時さ~」みたいな事を言っていた場合に、契約の相手方がそれを聞いて「あ、この人は成年なのか」と誤信してしまうこともありますよね。
そのようなケースも詐術にあたる可能性があるということです。
ただ、単に制限行為能力者であることを黙っていただけでは詐術にはあたらない、ということも「しかし~」の部分で述べられています。
例えば、未成年者が未成年年者であることをただ黙っていただけでは、それは詐術にはあたらないということです。
この点はご注意ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・取消権者と取消しの効果
・制限行為能力者の追認
・法定追認について
・相手方の催告権
・制限行為能力者の詐術
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

制限行為能力者の
取消権者と取消しの効果
未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者の契約等の法律行為には、法律による制限や保護があります。
そのひとつに、制限行為能力者が単独で有効にできる法律行為を限定し、もし単独で行ってしまったとしても後から取り消すことができる、という制度があります。
ところで、制限行為能力者が単独でした契約等の法律行為を取り消すことができるのは、一体誰なのでしょうか?
それは民法120条により、次のように規定されています。
(取消権者)
民法120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
上記、民法120条の規定により、制限行為能力者の法律行為を取り消せるのは「制限行為能力者・代理人・承継人・同意ができる者」となります。
制限行為能力者というのは、制限行為能力者本人です。
代理人というのは、未成年者であれば法定代理人(子供の親など)、成年被後見人であれば成年後見人になります。
承継人というのは、もっともわかりやすいところだと、相続人がそうです。
つまり、承継人が取り消す場合というのは、成年被後見人が法律行為を取り消す前に死亡し、相続人となった息子がその法律行為を取り消す、というようなことです。
同意ができる者というのは、保佐人・補助人を指すと思っていただいて良いでしょう。
つまり、被保佐人が単独でした法律行為を後に保佐人が取り消す、といったことです。
取消しの効果
さて、制限行為能力者が単独でした法律行為を取り消せるのは誰なのかはわかりました。
では、実際に取り消した後は一体どうなるのでしょうか?
これについての民法の規定はこちらです。
(取消しの効果)
民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
上記、民法121条により、取消しの効果は遡及(そきゅう)します。
遡及というのは「さかのぼって及ぶ」ということです。
つまり、取消しの効果は「さかのぼって無かったことになる」ということです。
そして、さかのぼって無かったことになると、後は原状回復という流れになります。
(こちら【不当利得】受益者が善意か悪意かで返還すべき利益が変わる?/現存利益の範囲とは?わかりやすく解説!の解説も参考まで)
(原状回復の義務)
民法121条の2
3項 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
制限行為能力者は
取り消した事を取り消せるか
なんだかややこしいですが、要するに、制限行為能力者が「この前の取消し、やっぱナシで!」と言えるか、ということです。
結論は、取消しを取り消すことはできません。
そもそも、取消しの取消しなんてことがまかり通ってしまったら、法的安定性が保たれず、世の中が混乱してしまいかねません。
それに、取消しが取り消せなくても、おそらく損害が生じることはないでしょう。
なぜなら、取り消すと初めから無かったことになり元に戻るだけなので、もし取り消さなければ何らかのプラスがあったとしても、取消しを取り消せなかったところで、ゼロに戻るだけでマイナスはないでしょう。
したがって、取消しを取り消すことはできません。
制限行為能力者の追認
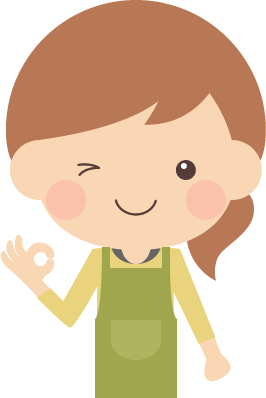
追認とは、後から追って認める、ということです。
例えば、制限行為能力者(例えば子供や成年被後見人)が単独では有効にならない法律行為をした後、法律で規定された者(例えばその子供の親や成年後見人)が、その法律行為を後から「それOK」と追認することによって、制限行為能力者が単独で行ったその法律行為は有効になります。
では、追認権を行使できるのは一体誰なのでしょうか?
民法122条の条文を読むと「120条に規定する取消権者」が追認できる者、ということになりますが、ここでひとつ問題があります。
というのは、もし取消権者=追認権者となると、例えば、子供が単独でした行為を、子供自身で追認することも可能になってしまいます。
あるいは、痴呆になって成年被後見人となった老人が単独でした行為を、老人自身で追認することもできてしまいます。
それってマズイですよね。
事例
お金持ちのお坊っちゃんの未成年者Aは、自己所有の高級ジュエリーをBに売り渡した。その後、Aはその行為(高級ジュエリーの売渡し)を追認した。
この事例のようなケースで、仮に次のような文言が入った売買契約書をAB間で交わしていたらどうなるでしょう?
「売主Aはこの売買契約を追認する」
もし「取消権者=追認権者」だから、未成年者自身も追認できるとなると、上記のような契約も可能になってしまいます。
となると、法律による制限行為能力者の保護の意味がなくなってしまいますよね。
この問題を民法はどう解決するのか?
民法では、以下の条文で規定しています。
(追認の要件)
民法124条1項
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
この民法124条1項が何を言っているのかといいますと「制限行為能力者が自分自身で追認するには制限行為能力者じゃなくなってからじゃないとダメ!」ということです。
条文の「取消しの原因」というのが「制限行為能力者であること」にあたりますので、その状況が消滅した後というのは「制限行為能力者でなくなった後」ということになります。
したがいまして、制限行為能力者が単独した行為を、制限行為能力者自身で追認することはできません。
ですので、事例の未成年者Bが、高級ジュエリーの売渡し行為を自ら追認することはできません。
もし、Aが自分自身で追認するには、A自身が成年になってからでないとできません。
なお、未成年者Aの法定代理人が追認することは当然できます。
多くの場合、未成年者の法定代理人は親権者(通常は親)なので、Aの親が、AからBへの高級ジュエリーの売渡し行為を追認すれば、それは当然に有効になります。
念のため申し上げておきます。
成年被後見人の追認の場合
未成年者の場合は、自らが成年になってからでないと自分自身で追認できないように、成年被後見人は行為能力者となってから、つまり、自らが成年被後見人でなくなって自らの行為を認識してからでないと自分自身で追認できません。
なお、これは被保佐人・被補助人も同様になります。
【補足」
民法124条1項の規定は「詐欺・強迫」についても適用があります。
つまり、騙されたり脅されたりした被害者が、騙されたことに気づいたり脅された状態から脱した後であれば、被害者自身で、詐欺・強迫によってした法律行為を追認できるということです。
ちょっと細かい話ですが、一応、頭の片隅に入れておいていただければと存じます。
なお、これは誰がする場合に限らずですが、一度追認した行為は、もはや取り消すことはできません。
追認も取消しも、できるのは一度までです。
そうでないと、法的安定性が損なわれてしまうからです。
この点もご注意ください。
法定追認について
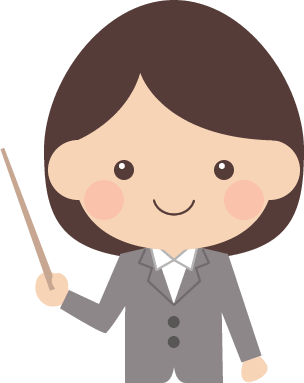
通常の追認は、追認権を持つ者が「その法律行為を追認します」と追認することにより行います。
しかし、それ以外にも追認する方法があります。
それが法定追認です。
法定追認とは、追認権者が追認の意思表示をしなくとも、ある一定の行為を行った場合は、法律上当然に追認したとみなされる、というものです。
つまり、追認権を持っている人が「追認します」と言わなくても、ある一定の行為を行ってしまった場合は、法律が勝手に「おまえのとった行動は追認したのと一緒だ!」として、法律上の追認として扱われてしまうということです。
そして、その「法律上追認したとみなされてしまう行為」が、民法125条により規定されています。
それは以下になります。
【法定追認される行為】民法125条抜粋
1 全部又は一部の履行
2 履行の請求
3 更改
4 担保の供与
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6 強制執行(自らが強制執行をする場合のみ)
これだけだと今ひとつよくわかりませんよね。
次の事例をもとに、ひとつひとつ解説して参ります。
事例
相続により甲土地を取得した未成年者Aは、単独で甲土地をBに売却した。
1・全部又は一部の履行
この事例で、制限行為能力者である未成年者Aが単独で行った甲土地の売買契約は、有効に成立していません。
では、Aが成年となってから、すなわち行為能力者となってから、追認も取消しもしないまま甲土地をBに引き渡したとしましょう。
あるいはBから、代金の全額または一部の支払いを受けたとしましょう。
するとAは、甲土地の売買契約を追認したとみなされます。
たとえ追認する気がなかったとしてもです。
これが法定追認の効果です。
2・履行の請求
この事例で、Aが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金を払ってくれ」と請求すると、その時点で、Aは甲土地の売買契約を追認したとみなされます。
3・更改
更改に関しては、初学者の方はすっ飛ばしてもかまいません。ですので、ざっくり申し上げておきます。
事例で、Aが一定の年齢に達し成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま甲土地の売買契約を乙土地の売買契約に変えた、というようなケースです。
この場合も、Aは追認したとみなされます。
4・担保の供与
担保というものについての詳細はここでは割愛しますが、法定追認においての担保の供与についての簡単な説明は、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないまま、Bからお金の代わりに何らかの物を受け取ったような場合です。
そのような場合も、Aは追認したとみなされます。
これだけだとピンと来ないと思いますが、とりあえず、このような規定もあるということだけ、何となく覚えておいてください。
そして後々、担保物権等を学習してから思い出していただければと存じます。
5・取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
これは、事例のAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしないままBに対して「甲土地の売買代金はCに払ってくれ」と言って、甲土地の売買代金を受け取る権利(債権)を他人に譲り渡すと、その時点でAは追認したとみなされます。
ちなみに、このようなAの行為を債権譲渡といいます。
要するに、債権譲渡にも追認効果があるということです。
(債権譲渡の基本についての詳しい解説は「【債権譲渡の超基本】債権は譲れる?譲るとどうなる?実際に債権譲渡が利用されるケースとは?わかりやすく解説!」をご覧ください)
6・強制執行(自ら強制執行する場合のみ)
強制執行についてを今ここで詳しく説明しようとすると、内容がテンコ盛りになり過ぎて逆に訳がわからなくなってしまいますので、超ざっくり申します。
事例でAが成年(行為能力者)となってから、追認も取消しもしていない状況で、裁判所の力を使って問答無用でBにお金を払わせることです。
超ざっくりで申し訳ございません(笑)。
とりあえず、そのような場合もAは追認したとみなされる、ということを頭に入れておいてください。
(強制執行の基本についての詳しい解説は「【差押え&強制執行&破産の超基本】借金で考える債権の世界~債務者に財産が無いとどうなる?わかりやすく解説!」をご覧ください)
【補足】
追認は、追認権者が取消権を有することを知らずにした場合はその効果を生じません。
追認は、取消権を持っている事を知った上で行うものです。
相手方の催告権
制限行為能力者が、単独では有効にできない法律行為を単独でした場合、その法律行為の相手方は、取り消されるか追認されるかされるまでは、言ってみれば宙ぶらりんの状態です。
事例
被保佐人のAは、単独で自己所有の甲土地をBに売却した。※
※被保佐人は民法13条の規定により、単独で有効に不動産の売買契約を結ぶことはできません。
この事例の場合、売主側の追認がない限り、買主のBは甲土地を手に入れることができません。
その上、取り消されない限りは追認の場合の支払い債務も考えて、代金の準備を欠かすわけにもいきません。
これは買主Bとしては、非常に厄介な状況ですよね。気の毒とも言えます。
そこで民法は、このような宙ぶらりんの状態にされた制限行為能力者の相手方に、催告権という救いの手を差し伸べています。
催告権とは
宙ぶらりんにされた制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者側に対し1ヶ月以上の期間を定めて「追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と求めることができます。
この権利を催告権といいます。
そしてこの催告権は、ただ相手に答えを求めるだけの権利ではありません。そこには法的効果が存在します。
そしてその法的効果は、催告をする相手によって変わってきます。
それでは、催告権の法的効果の違いについて、事例にあてはめて考えていきます。
被保佐人Aに対し催告した場合
買主Bが、1ヶ月以上の期間を定めた上で被保佐人Aに対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合、まず被保佐人Aは、定められた期間内に、追認するか取り消すかの選択をしなければなりません。
ここまでは当たり前のことです。
では、定められた期間内に被保佐人Aが返事をしなかった場合どうなるでしょうか?
この場合、被保佐人Aは甲土地の売買契約を取り消したとみなされます。
これが、民法が制限行為能力者の相手方に与えた救いの手、催告権の法的効果です。
つまり、買主Bは、催告することによって、自分から宙ぶらりんの状態を脱することができます。
なぜ制限行為能力者の返事がない場合、取り消したみなすかといいますと、宙ぶらりん状態の解消はもちろんですが、取り消したとみなす分には制限行為能力者への損害が生じる可能性はないと考えられるからです。
元の状態に戻るだけなので。
被保佐人Aの保護者「保佐人」に催告した場合
では、買主Bが1ヶ月以上の期間を定めた上で、今度は被保佐人Aの保護者の保佐人に対し「甲土地の売買契約を追認するのか取り消すのか、どっちかハッキリしてくれ!」と催告した場合は、どうなるのでしょうか?
この場合、Aの保護者である保佐人が、定められた期間内に追認するか取り消すかの返事をすることになりますが、もしこのとき、保佐人が定められた期間内に返事をしないとどうなるでしょう?
なんとこの場合、保佐人は追認したとみなされます。
なぜ保佐人の場合はこのようになるかといいますと、保佐人には通常の判断能力(意思能力)があるからです。
通常の判断能力で考えて結論を出せるはずだからです。
したがって、買主BがAの保佐人に催告し、期間内に返事がなかった場合は、保佐人は追認したとみなされるのです。
このように、制限行為能力者の相手方には、催告権という救いの一手が与えられていて、誰に催告するかによってその法的効果は変わってきます。
つまり、こういった形で、制限行為能力者の保護と制限行為能力者の相手方の公平をコントロールしているということです。
制限行為能力者の詐術

制限行為能力の制度に定められた制限行為能力者の単独でした法律行為が取り消せることはすでに解説済みですが、実は、制限行為能力者がした法律行為でも、取り消せないものがあります。
それは制限行為能力者の詐術です。
事例
17歳の未成年者Aは免許証を偽造し、Bと甲不動産の売買契約を締結した。
さて、この事例で、Aは未成年者(制限行為能力者)ということを理由に、Bと結んだ甲不動産の売買契約を取り消すことができるでしょうか?
結論。
Aは未成年者を理由に甲不動産の売買契約を取り消すことができません。
なぜなら、Aは詐術を用いているからです。
詐術というのはウソをつくことです。
民法の規定はこちらです。
(制限行為能力者の詐術)
民法21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
いくら制限行為能力者だからといって、自分は行為能力者であると自ら相手を騙しておいて、後からやっぱり制限行為能力者なので取り消します、なんてことを許してしまうのは信義に反します。
よって、民法21条の規定により、自ら詐術を用いた制限行為能力者の行為は、取り消すことができません。
また、こう考えることもできます。
制限行為能力者の保護は、制限行為能力者の判断能力(意思能力)には問題があると考えられるからですが、判断能力(意思能力)に問題がある人間が、自ら考えて詐術を用いることができるでしょうか?
むしろ、そこまで考えて実行している時点で、そこまで頭が回っているってことですよね?
ということから、制限行為能力者が詐術を使って制限行為能力者ではないと相手を誤信させて行った行為は取り消すことはできない、と考えることもできます。
第三者が詐術を用いた場合
例えば、未成年者自らでなく、第三者が「あいつは成人だから大丈夫だよ」といって相手方が誤信してしまった場合は、どうなるでしょうか?
この場合、未成年者自身は何も悪くありません。
むしろ、大人っぽい見た目が災いしただけの被害者とも言えるかもしれません。
したがいまして、このようなケースでは取消権の行使は可能です。
民法21条の規定は、あくまで自ら詐術を用いた制限行為能力者に対するペナルティなのです。
【補足】
一口に詐術といっても、一体どこまでが詐術となるのでしょうか?
判例では以下のように示しています。
「民法21の詐術とは、積極的術策を用いた場合だけでなく、制限行為能力者がその旨を黙秘していた場合でも、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合には、なお詐術にあたる。しかし、単に制限行為能力者であることを黙認したのみでは、詐術にはあたらない」
この判例で何を言っているかといいますと、要するに、制限行為能力者が自分から積極的に詐術を用いていなくとも詐術にあたる場合がある、ということです。
例えば、未成年者が「私は成年です」という旨を言わなくても、会話の中で「この前飲みに行った時さ~」みたいな事を言っていた場合に、契約の相手方がそれを聞いて「あ、この人は成年なのか」と誤信してしまうこともありますよね。
そのようなケースも詐術にあたる可能性があるということです。
ただ、単に制限行為能力者であることを黙っていただけでは詐術にはあたらない、ということも「しかし~」の部分で述べられています。
例えば、未成年者が未成年年者であることをただ黙っていただけでは、それは詐術にはあたらないということです。
この点はご注意ください。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【制限行為能力者】成年被後見人・被保佐人・被補助人とは?その違いは?わかりやすく解説!
【制限行為能力者】成年被後見人・被保佐人・被補助人とは?その違いは?わかりやすく解説!
-
 【制限行為能力者:未成年者の超基本】未成年者が単独でできることは/棋士は個人事業主?タレントは?初学者にもわかりやすく解説!
【制限行為能力者:未成年者の超基本】未成年者が単独でできることは/棋士は個人事業主?タレントは?初学者にもわかりやすく解説!
-
 【制限行為能力の取消権者と取消しの効果】追認と法定追認/相手方の催告権/制限行為能力者の詐術をわかりやすく解説!
【制限行為能力の取消権者と取消しの効果】追認と法定追認/相手方の催告権/制限行為能力者の詐術をわかりやすく解説!
-