
▼この記事でわかること
・嫡出子と非嫡出子
・嫡出推定
・推定される嫡出子と推定されない嫡出子
・嫡出推定の及ばない子
・父を定める訴え
・認知の基本~成年の認知と死後の認知
・認知の無効、認知の撤回、法定代理人の同意
・婚姻外の認知
・非嫡出子の相続権と遺産分割
・準正
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係の夫婦間の子のことです、
非嫡出子とは、婚姻していない男女間の子のことです。
例えば、夫Aと妻Bの子は嫡出子であり、夫Aと愛人Cの子は非嫡出子となります。
ですが、嫡出子と非嫡出子はいずれも夫Aの子です。
嫡出子が夫Aの子となるためにAの認知は不要です。
しかし、非嫡出子は認知によって初めて法律上の夫Aの子となります。
非嫡出子と父母
民法779条は、嫡出でない子は、その父または母がこれを認知することができると規定します。
通常、問題になるのは父の方です。
父が認知をしなければ、子は法律上、父のない子となります。
子は母の戸籍に入り、その戸籍上の父の欄は空欄となるのです。
昔、カルメンマキの「時には母のない子のように」という歌がありましたが、父が認知しない子は「父のない子のように」なってしまいます。
なんて余談はさておき...
これに対して、母と子の関係は認知がなくても分娩により当然に発生します。
つまり、認知せずとも母と子は(分娩により)法律上の親子となります。
嫡出子
嫡出子とは、婚姻による子です。
母の懐胎の期間中、ずっと父母が婚姻中であれば、嫡出子かどうかについての疑義は生じません。
つまり、父母が婚姻をして1年後に母が父の子を懐胎し、そのまま出産した子が嫡出子であることは誰の目にも明らかです。
しかし、婚姻してすぐに生まれた子、あるいは離婚後に生まれた子の場合には、果たして嫡出子の身分を取得するのでしょうか?
この点については、母の懐胎期間のうち、一部でもその父母の婚姻期間に該当すれば嫡出子になると考えることができます。
例えば、婚姻後すぐに子が出生した、いわゆる出来ちゃった婚の場合でも、嫡出子出生届出は受理されるのが実務の取扱いです。
また、離婚後の子でも、離婚前に懐胎していれば、嫡出子の身分を取得することができます。
以上、ここまでは、子が父母の子であることを前提としての解説です。
それでは、父母の子ではない子を嫡出子として届け出るとどうなるのでしょうか?
非嫡出子
事例1
婚姻中の父母が、アカの他人の子を嫡出子として出生届を出した。
この事例1の場合、父母と子の間に親子関係は生じません。
この出生届は虚偽の届出あり無効です。
また、この出生届を養子縁組の意思によるものと考えることもできません。
そもそも出生と縁組では、その意味するところが違います。
出生届は自然血族の発生に関する届けであるのに対して、養子縁組は法的血族関係の発生に関する届けであり、その性質がまったく異なるのです。
続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例2
婚姻中の父母が、父が愛人に生ませた子を嫡出子として出生届を出した。
この場合は、父と愛人の子に法律上の親子関係が生じます。
事例2の場合、愛人の子とはいえ、確かに父の子ではあります。
そこで、この出生届に認知届としての意味を持たせるのが判例の考え方です。
出生届には、自己の子であることの申告という意思が含まれていますから、その点で、認知としての効力が発生するということです。
したがって、事例2の場合は、非嫡出子として法律上の父子関係が生じます。
嫡出推定
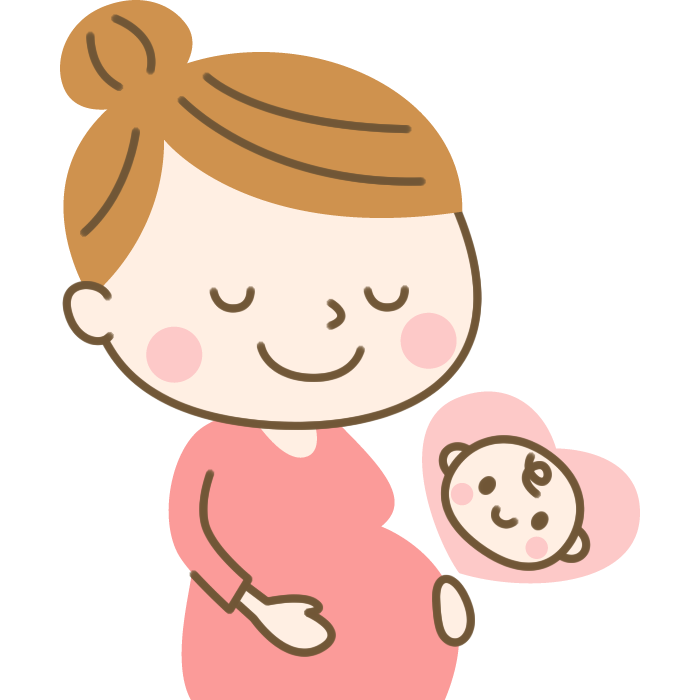
子の父が誰かは母しかわからない、と言われることがあります。
これはある意味核心かもしれません。
そしてこの点は、民法のおいても大きなテーマであり、少々ややこしい規定が存在しています。
基本的な考え方としては、民法は嫡出推定という制度を設け、夫婦間の子は夫の子であると推定します。(あくまで推定)
そして、この推定を覆すためには、嫡出否認の訴えという、きわめて厳格な訴訟手続による方式だけを認めています。
これは、身分関係の安定を優先した民法の態度の現れと言えるでしょう。
民法の規定はこちらです。
(嫡出否認の訴え)
民法775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
この民法775条と民放777条が、嫡出される子について、夫が「俺の子じゃない」と父子関係を切るための方法を定めた条文です。
出訴期間は、子の出生を知った時から1年です。
この期間は、法律実務の感覚からすれば、極めて短いと言えます。
そして、この期間を経過すれば、夫が子の法律上の関係を切る方法は存在しなくなります。
DNA鑑定をしても無駄なことです。
嫡出否認の訴えの被告(訴える相手)は、子または親権を行う母です。
通常は、子は幼少であるでしょうから、親権を行う母を被告とします。
これが存在しない場合、つまり、母がいないか、いても母に親権がない場合には、裁判所が特別代理人を選任します。
もちろん、特別代理人は子を代理します。
子が被告であり、その代理人という意味です。
しかし、子に意思能力がある場合、または、子が成人している場合(この場合母に親権はない)には、子を被告席に座らせることができます。
このケースは、夫が子の出生を、出生日からかなりの月日が経ってから初めて知った、そして、その時点から1年以内に嫡出否認の訴えを提起したという極めて例外的な場合です。
以上が、嫡出否認の訴えの概要です。
この訴訟は、推定される嫡出子の、その推定をひっくり返すことを目的とします。
【補足1】親権を行う母を被告とするわけ
子を代理するのは法定代理人です。
なので、子に意思能力がなければ、法定代理人が被告となります。
これが民法の常識です。
ではなぜ、民法は、この嫡出否認のケースに限り被告を親権を行う母に限定したのでしょうか?
答えは簡単です。
ここで先述にもある話が出て来ます。
そう。
子の真実の父は母しか知らない、です。
事情が本当にわかるのは母しかいないので、原則として母が被告なのです。
【補足2】嫡出の承認
民法776条は、先述の出訴期間を経過せずとも、夫が子の出生後に、子の嫡出性を承認したときには否認権を失うとしています。
ここで問題になるのが、子の出生届です。
夫が役所で子の嫡出子出生届を出した場合、民法776条のいう嫡出性の承認に該当するのでしょうか?
そうだとすれば、夫は子の嫡出性を争うことは不可能になります。
しかし、判例はこの考え方を採用しません。
つまり、夫は戸籍法が定める公法上の義務として出生届を提出した(提出しない場合、過料の規定がある)に過ぎず、その事をもって嫡出性を承認したことにはならないのです。
推定される嫡出子と推定されない嫡出子
実は、嫡出子には、推定される嫡出子と推定されない嫡出子がいます。
どちらも、嫡出子には違いないのですが、嫡出否認の制度は、あくまでも推定される嫡出子の嫡出性を否認する制度であり、推定されない嫡出子とは無関係です。
では、民法は、どういう場合に子の嫡出子の推定(夫の子であるという推定)が働くしているのでしょうか?
民法の規定はこちらです。
(嫡出の推定)
民法772条
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この民法772条の規定により、ある夫婦が存在したとして、その婚姻届を出した日から200日後、そして、離婚、死別、婚姻取消から300日以内に生まれた子が、夫の子と推定される嫡出子となるのです。
ということは、例えば、デキちゃった婚で婚姻届を出してから半年後(つまり200日以内)に生まれた子がいた場合、この子は嫡出子の身分は取得するが、夫の子であるという推定は働かない子であるということになります。
この場合に、夫が「この子は俺の子じゃない」と思ったらどうすればいいのでしょうか?
この子に対しては、嫡出否認の訴えなどという厳格な手続は要しません。
つまり、民法上の推定を覆そうと汗を流す必要はないのです。
単に、親子関係不存在確認の訴えを提起し、勝訴すれば父子関係を切ることができます。
親子関係不存在確認の訴えは、文字通り「この子は俺のじゃない」のでその事実をご確認願います、というだけの意味です。
事の性質上、出訴期間の定めなどありません。
つまり、子の出生を知ってから何年経過しようがこの訴えの提起は可能です。
嫡出推定の及ばない子
推定の及ばない子と推定されない嫡出子は別の概念です。
嫡出推定の及ばない子の場合、父母は婚姻中なのです。
しかし、それにも関わらず嫡出子の推定が及ばないのです。
以下に具体例を挙げます。
・明らかに異人種の子
・夫が長期海外出張中の子
・夫に生殖機能がないことが医学的に明らかな場合
こういう事例では、子には嫡出推定が及びません。
したがって、夫による「この子は俺の子じゃない」という主張は、親子関係の不存在確認という形ですることができます。
父を定める訴え

再婚禁止期間中に女が再婚をし、この婚姻届が誤って受理されると、その後に出生した子の出生日が「前婚の解消または取消しから300日以内」であり「後婚の成立の日から200日を経過した後」、という困った事態が生じ得ます。
子の嫡出推定が重なり、前婚と後婚の双方の父の嫡出子と推定されてしまう訳です。
この場合、民法773条は、裁判所がその子の父を定めると規定しています。
これを、父を定める訴えといいます。
この訴えに出訴期間の定めはありません。(何年経過しようが訴え可能)
認知
認知は、戸籍の届出によってします。(民法781条1項)
また、遺言によりすることができます。(民法781条2項)
民法は、遺言によりすることができることを厳格に定めます。
それは、遺言は、相続がらみの問題を生じるので、紛争を避けるために遺言の要式やその内容をきっちりと決めておく必要があるからです。
遺言による認知を認めた趣旨は、父である男の側に、生きている間は認知をしにくいという事情もあろうかという点を考慮してのことです。
認知は、戸籍に記載されますから、万一、愛人の子の存在が妻に知れたら「男は非常に困る」ことがあり得るのです。
そこで、妻に怒られる心配のない、死と同時の認知を制度化したのです。
認知により子は父を相続することができますから、子の福祉にも適うわけです。
成年の子の認知
成年の子は、その承諾がなければこれを認知することはできません(民法782条)。
これは、例えば、父が成人した子を認知する場合の規定です。
子はすでに成人しています。
したがって、父による扶養の必要はないと考えられます。
しかし、今後、父は老います。
したがって、認知により父子間に血族関係が生じると子の父への扶養義務が生じ得ます。
つまり、成人の子を認知するということは、父は自らは子の扶養をしなかったにもかかわらず、その老後の扶養を子に求めることになりかねません。
それはつまり、父の身勝手とも言えるので、認知をするために子の承諾がいるとされています。
死後の認知
続いて、次のような場合の認知はどうなるのでしょうか?
事例3
A男には婚姻外の子がいたが、幼少時に死亡した。
この事例3は、婚姻していない男女の間に生まれた幼い子供がいたが、まだ幼いうちにその子が死亡してしまった、という話です。
さて、ではA男は、子の死後に認知をすることができるのでしょうか?
結論。
認知をすることはできません。
子の死後においては、通常の場合、認知をすることはできないのです、
なぜなら、認知できたとしても、子が扶養を受けることもなく、子が父を相続することもありません。
つまり、子の死後に認知をすることができても、子にとって実益がないのです。
しかし、子にも子がいるケースは例外です。
例えば、A男に成人の子がいて、その子にも子(A男にとっての孫)がいるケースです。
この場合、父が子を認知することにより、父と孫が直系血族となります。
となると、孫は父に扶養を請求できますし、また孫が父を相続することもできます。
つまり、このケースなら、孫の福祉に適うから死後の子の認知が認められるのです。(民法783条2項)
しかし、先述の成人の子の場合と同様、孫が成人であれば、その者の承諾がなければ認知をすることはできません。
認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人であっても、その法定代理人の同意は要しません。(民法780条)
身分行為については、本人に意思能力があれば、その意思によるべきであり、第三者の同意はなじまないのが原則なのです。
色々な認知
認知の無効、認知の撤回、法定代理人の同意
ここから、さらに認知の様々なケースについて、事例とともに解説して参ります。
なお、Aが父、Bが子、という前提です。
事例4
第三者が父Aの名を語り認知届を出した。なお、父Aと子Bの間には真実の父子関係かある。
さて、この事例での認知は有効でしょうか?
結論。
この認知届は無効です。
認知は、法律上の父子関係を創設する意思表示と考えられますから、認知者本人の意思に基づかなければ無効です。
つまり、認知とは、単に父子であるという事実の申告ではなく、法律上の父子になろうという意思の申告なのです。
事例5
父Aが認知届を出した後死亡した。
さて、この事例で、父Aと子Bの間に父子関係がない場合、子Bは認知の無効を主張できるでしょうか?
結論。
認知の無効を主張できます。
届出上の父子間に実際の血縁関係が存在しないので、認知は無効なのです。
父の生前は父を被告として、父の死後は検察官を被告として、子Bは上記の無効主張をすることになります。
この事例5では、父は死亡しており、その代理人という存在はあり得ませんから、やむを得ず検察官が被告(無効主張する相手)となります。
参考条文
(認知に対する反対の事実の主張)
民法786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
事例6
父Aは認知届を出した。しかし、その後に気が変わった。
さて、この事例で、父Aは認知の撤回をすることはできるでしょうか?
結論。
一度した認知の撤回は不可能です。
認知をした父または母は、その認知を取り消すことができません。(民法785)
ここにいう取消しとは、撤回の意味であると解釈されています。
事例7
未成年の父Aは、子Bの認知をしようとした。
さて、この事例で、未成年の父Aは、子の認知をするために法定代理人の同意を要するでしょうか?
結論。
法定代理人の同意は要しません。
民法780条の規定「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない」により、父が未成年であっても、法定代理人の同意は要しません。
認知と子の氏
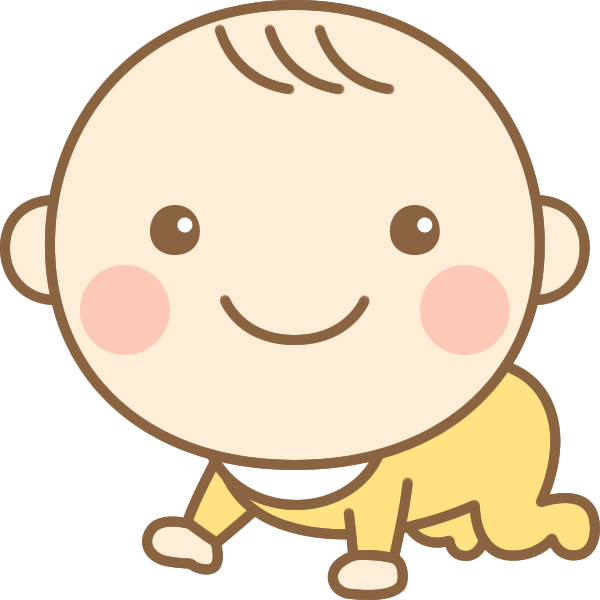
民法790条2項は、嫡出でない子は母の氏を称すると規定しています。
婚姻外の子は母の戸籍に入り、母と同じ氏を称します。
さて、ここで父が認知をするとどうなるのでしょうか?
どうにもなりません。
子の氏は、子に独立のものですから影響を受けないのです。
しかし、この場合は、子が父または母と氏を異にする場合に該当しますから、家庭裁判所の許可を得て、父の氏に変えることができます。(民法791条1項)
このケースでは、父母が婚姻中ではありませんから、家庭裁判所の許可は必須です。
また、父が子を認知しても親権者は母のままですが、父母の協議で父を親権者と定めたときは、父が親権者となります。(民法819条4項)
【補足】胎児の認知
父が胎児の認知をすることは可能です。
しかし、そのために母の承諾を要します。
常識的に考えても「お前のお腹の子は俺の子だ」という態度は、女性に対して失礼ですよね。
なので、母の承諾を要するのです。(民法783条1項)
婚姻外の認知
事例8
A男とB子が、内縁関係を始めて、200日経過後に娘Cが出生した。
さて、この事例で、娘CはA男の子と推定されるでしょうか?
まず、この問題は嫡出推定の話とは直接の関係はありません。
なぜなら、A男とB子が法律上の夫婦ではないので、嫡出子になるわけはないのです
しかし、この場合、判例は、娘CはA男の子であると事実上推定されるとしています。
すなわち、AC間に血の繋がりがあるかどうかが、裁判上の争点となったとき、事実上の問題として、娘CはA男の子と推定され、これを否定する場合、A男の側に親子ではないことの立証が求められることになります。
事例9
A男とB子の間に、婚姻外の娘Cがいる。しかし、A男は認知をしない。
さて、この事例で、娘CからA男に対して認知を強制することはできるでしょうか?
結論。
できます。
強制認知という方法が存在します。
民法の規定はこちらです。
(認知の訴え)
民法787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
上記、民法787条の規定により、この訴訟は、父が生存中であれば、いつでも提起することができます。
この場合、父子間に血縁関係が存在するかどうかが争点となります。
事例10
A男とB子の間に、婚姻外の娘Cがいる。その後、A男が死亡した。
さて、この事例で、娘CがA男の認知を求めることはできるでしょうか?
結論。
父または母の死亡後は、死亡の日から3年間に限り、認知の訴えを提起することができます。(民法787条ただし書)
この訴えの被告は検察官です。
民法上、死者の代理人は考えにくいからです。(代理は本人に権利義務を帰属させる制度です。死者には権利能力がないからその代理という仕組みは基本的に存在しません)
なお、訴えが可能な時期は、死亡後3年までであり、子が父の死亡の事実を知った時から3年ではありません。
【補足】
父の死後に強制認知をした非嫡出子の相続権
認知の効力は子の出生にさかのぼります。(民法784条)
したがって、死後に認知された場合でも、子は出生のときから父の子です。
つまり、父の死亡時にも子として存在したことになります。
なので、父の死後に強制認知をした非嫡出子には相続権が発生します。
非嫡出子の相続権と遺産分割
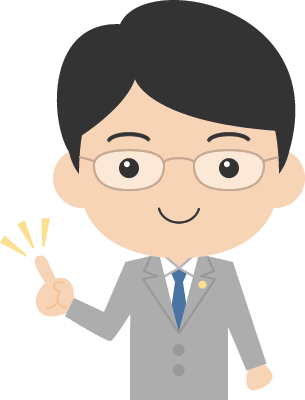
遺産分割とは、共同相続人が死者の遺産分けをすることをいいます。
あの土地は長男、株は次男、預貯金は三男という具合です。
遺産分割は、相続人全員でしなければその効力を発生しません。
なので、例えば、死者が生前に認知した非嫡出子の存在を知らずに(まさか故人に愛人の子がいるとは知らなかったケース)、他の共同相続人が遺産分割をしても、それは無効です。
しかし、相続の開始後、認知によって相続人となった者がいる場合、つまり、典型的には死後の強制認知の場合に、他の共同相続人が認知前にした遺産分割協議は無効とはなりません。(民法910条)
この場合には、認知された子は価額のみによる支払の請求額を有することになります。
すなわち、他の共同相続人の遺産分けは有効だが、認知された子の取り分はお金を渡すという形になるわけです。
【補足】胎児の権利能力
胎児は認知の訴えの提起はできません。
それは、認知の訴えの提訴権者が「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人」と規定されているから(民法787条)でもありますが、一般論として胎児には権利能力がないので、訴訟の場合に、訴状に原告胎児とは書けないからとも言えます。
なお、例外的に、次のケースでは、胎児の権利能力が認められています。
いずれも、生まれてくる子の財産を確保しようという趣旨の規定です。
・不法行為の損害賠償請求権(民法721条)胎児が加害者に損害賠償請求をすることができる。
・相続権(民法886条1項)胎児の相続権が認められます。
・受遺能力(民法965条)胎児に対する遺贈は有効である。
準正
準正は、非嫡出子が、嫡出子の身分を取得する仕組みです。
その要件は次の2つです。
・父母が婚姻すること
・父が子を認知すること
上記2つの要件がそろえば、例外なく、子は嫡出子の身分を取得します。
元々、婚姻中の父母の子であれば、嫡出子の身分を取得できますので、父母の婚姻、認知の2つの要件が時期をずらして満たされた場合でも、子が嫡出子となるという仕組みです。
婚姻によって準正が生じる場合、つまり、認知先行型を婚姻準正といいます。
(準正)
民法789条1項
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
認知によって準正が生じる場合、つまり、婚姻先行型を認知準正といいます。
(準正)
民法789条2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
この民法789条の条文が言っていることは極めて明快です。
1項の認知先行型、すなわち婚姻準正の場合は、婚姻により非嫡出子は嫡出子となります。
2項の婚姻先行型、すなわち認知準正の場合は、認知により非嫡出子は嫡出子となります。
では、どの場合に準正が生じ得るのか?いくつかのケースに分けて解説して参ります。
1・父が死亡した場合
これは、例えば、子の出生後に父母が婚姻し(この時点では父が子を認知していないから父と子の関係は姻族1親等であり法律上の親子関係は存在しない)、その後に父が死亡した場合です。
一例として、父の死後3年以内に子が認知の訴えを提起し、これが認められれば認知準正が生じます。
2・母が死亡した場合
準正が生じる事があり得ます。
例えば、子の出生後に父母が婚姻し、その後に母が死亡したとします。
その後、父が子を認知すれば準正が生じ、子は嫡出子の身分を取得します。
3・子が死亡した場合
準正が生じる事があり得ます。
例えば、子の出生後に父母が婚姻し、その後に子が死亡したが、その子にさらに子(父母から見れば孫)がいたため、父が死亡した子を認知することができたケースです。
〈参考条文〉
民法789条3項
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
 ⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
⇒⇒LECで宅建試験・行政書士試験・公務員試験の合格講座&テキストを探す!
・嫡出子と非嫡出子
・嫡出推定
・推定される嫡出子と推定されない嫡出子
・嫡出推定の及ばない子
・父を定める訴え
・認知の基本~成年の認知と死後の認知
・認知の無効、認知の撤回、法定代理人の同意
・婚姻外の認知
・非嫡出子の相続権と遺産分割
・準正
(上記クリックorタップでジャンプします)
今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、わかりやすく学習できますよう解説して参ります。

嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係の夫婦間の子のことです、
非嫡出子とは、婚姻していない男女間の子のことです。
例えば、夫Aと妻Bの子は嫡出子であり、夫Aと愛人Cの子は非嫡出子となります。
ですが、嫡出子と非嫡出子はいずれも夫Aの子です。
嫡出子が夫Aの子となるためにAの認知は不要です。
しかし、非嫡出子は認知によって初めて法律上の夫Aの子となります。
非嫡出子と父母
民法779条は、嫡出でない子は、その父または母がこれを認知することができると規定します。
通常、問題になるのは父の方です。
父が認知をしなければ、子は法律上、父のない子となります。
子は母の戸籍に入り、その戸籍上の父の欄は空欄となるのです。
昔、カルメンマキの「時には母のない子のように」という歌がありましたが、父が認知しない子は「父のない子のように」なってしまいます。
なんて余談はさておき...
これに対して、母と子の関係は認知がなくても分娩により当然に発生します。
つまり、認知せずとも母と子は(分娩により)法律上の親子となります。
嫡出子
嫡出子とは、婚姻による子です。
母の懐胎の期間中、ずっと父母が婚姻中であれば、嫡出子かどうかについての疑義は生じません。
つまり、父母が婚姻をして1年後に母が父の子を懐胎し、そのまま出産した子が嫡出子であることは誰の目にも明らかです。
しかし、婚姻してすぐに生まれた子、あるいは離婚後に生まれた子の場合には、果たして嫡出子の身分を取得するのでしょうか?
この点については、母の懐胎期間のうち、一部でもその父母の婚姻期間に該当すれば嫡出子になると考えることができます。
例えば、婚姻後すぐに子が出生した、いわゆる出来ちゃった婚の場合でも、嫡出子出生届出は受理されるのが実務の取扱いです。
また、離婚後の子でも、離婚前に懐胎していれば、嫡出子の身分を取得することができます。
以上、ここまでは、子が父母の子であることを前提としての解説です。
それでは、父母の子ではない子を嫡出子として届け出るとどうなるのでしょうか?
非嫡出子
事例1
婚姻中の父母が、アカの他人の子を嫡出子として出生届を出した。
この事例1の場合、父母と子の間に親子関係は生じません。
この出生届は虚偽の届出あり無効です。
また、この出生届を養子縁組の意思によるものと考えることもできません。
そもそも出生と縁組では、その意味するところが違います。
出生届は自然血族の発生に関する届けであるのに対して、養子縁組は法的血族関係の発生に関する届けであり、その性質がまったく異なるのです。
続いては、こちらの事例をご覧ください。
事例2
婚姻中の父母が、父が愛人に生ませた子を嫡出子として出生届を出した。
この場合は、父と愛人の子に法律上の親子関係が生じます。
事例2の場合、愛人の子とはいえ、確かに父の子ではあります。
そこで、この出生届に認知届としての意味を持たせるのが判例の考え方です。
出生届には、自己の子であることの申告という意思が含まれていますから、その点で、認知としての効力が発生するということです。
したがって、事例2の場合は、非嫡出子として法律上の父子関係が生じます。
嫡出推定
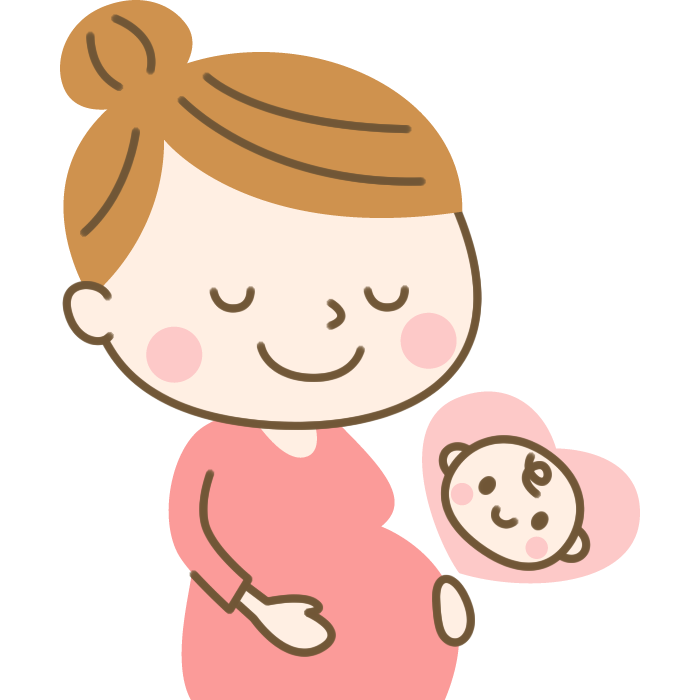
子の父が誰かは母しかわからない、と言われることがあります。
これはある意味核心かもしれません。
そしてこの点は、民法のおいても大きなテーマであり、少々ややこしい規定が存在しています。
基本的な考え方としては、民法は嫡出推定という制度を設け、夫婦間の子は夫の子であると推定します。(あくまで推定)
そして、この推定を覆すためには、嫡出否認の訴えという、きわめて厳格な訴訟手続による方式だけを認めています。
これは、身分関係の安定を優先した民法の態度の現れと言えるでしょう。
民法の規定はこちらです。
(嫡出否認の訴え)
民法775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
この民法775条と民放777条が、嫡出される子について、夫が「俺の子じゃない」と父子関係を切るための方法を定めた条文です。
出訴期間は、子の出生を知った時から1年です。
この期間は、法律実務の感覚からすれば、極めて短いと言えます。
そして、この期間を経過すれば、夫が子の法律上の関係を切る方法は存在しなくなります。
DNA鑑定をしても無駄なことです。
嫡出否認の訴えの被告(訴える相手)は、子または親権を行う母です。
通常は、子は幼少であるでしょうから、親権を行う母を被告とします。
これが存在しない場合、つまり、母がいないか、いても母に親権がない場合には、裁判所が特別代理人を選任します。
もちろん、特別代理人は子を代理します。
子が被告であり、その代理人という意味です。
しかし、子に意思能力がある場合、または、子が成人している場合(この場合母に親権はない)には、子を被告席に座らせることができます。
このケースは、夫が子の出生を、出生日からかなりの月日が経ってから初めて知った、そして、その時点から1年以内に嫡出否認の訴えを提起したという極めて例外的な場合です。
以上が、嫡出否認の訴えの概要です。
この訴訟は、推定される嫡出子の、その推定をひっくり返すことを目的とします。
【補足1】親権を行う母を被告とするわけ
子を代理するのは法定代理人です。
なので、子に意思能力がなければ、法定代理人が被告となります。
これが民法の常識です。
ではなぜ、民法は、この嫡出否認のケースに限り被告を親権を行う母に限定したのでしょうか?
答えは簡単です。
ここで先述にもある話が出て来ます。
そう。
子の真実の父は母しか知らない、です。
事情が本当にわかるのは母しかいないので、原則として母が被告なのです。
【補足2】嫡出の承認
民法776条は、先述の出訴期間を経過せずとも、夫が子の出生後に、子の嫡出性を承認したときには否認権を失うとしています。
ここで問題になるのが、子の出生届です。
夫が役所で子の嫡出子出生届を出した場合、民法776条のいう嫡出性の承認に該当するのでしょうか?
そうだとすれば、夫は子の嫡出性を争うことは不可能になります。
しかし、判例はこの考え方を採用しません。
つまり、夫は戸籍法が定める公法上の義務として出生届を提出した(提出しない場合、過料の規定がある)に過ぎず、その事をもって嫡出性を承認したことにはならないのです。
推定される嫡出子と推定されない嫡出子
実は、嫡出子には、推定される嫡出子と推定されない嫡出子がいます。
どちらも、嫡出子には違いないのですが、嫡出否認の制度は、あくまでも推定される嫡出子の嫡出性を否認する制度であり、推定されない嫡出子とは無関係です。
では、民法は、どういう場合に子の嫡出子の推定(夫の子であるという推定)が働くしているのでしょうか?
民法の規定はこちらです。
(嫡出の推定)
民法772条
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この民法772条の規定により、ある夫婦が存在したとして、その婚姻届を出した日から200日後、そして、離婚、死別、婚姻取消から300日以内に生まれた子が、夫の子と推定される嫡出子となるのです。
ということは、例えば、デキちゃった婚で婚姻届を出してから半年後(つまり200日以内)に生まれた子がいた場合、この子は嫡出子の身分は取得するが、夫の子であるという推定は働かない子であるということになります。
この場合に、夫が「この子は俺の子じゃない」と思ったらどうすればいいのでしょうか?
この子に対しては、嫡出否認の訴えなどという厳格な手続は要しません。
つまり、民法上の推定を覆そうと汗を流す必要はないのです。
単に、親子関係不存在確認の訴えを提起し、勝訴すれば父子関係を切ることができます。
親子関係不存在確認の訴えは、文字通り「この子は俺のじゃない」のでその事実をご確認願います、というだけの意味です。
事の性質上、出訴期間の定めなどありません。
つまり、子の出生を知ってから何年経過しようがこの訴えの提起は可能です。
嫡出推定の及ばない子
推定の及ばない子と推定されない嫡出子は別の概念です。
嫡出推定の及ばない子の場合、父母は婚姻中なのです。
しかし、それにも関わらず嫡出子の推定が及ばないのです。
以下に具体例を挙げます。
・明らかに異人種の子
・夫が長期海外出張中の子
・夫に生殖機能がないことが医学的に明らかな場合
こういう事例では、子には嫡出推定が及びません。
したがって、夫による「この子は俺の子じゃない」という主張は、親子関係の不存在確認という形ですることができます。
父を定める訴え

再婚禁止期間中に女が再婚をし、この婚姻届が誤って受理されると、その後に出生した子の出生日が「前婚の解消または取消しから300日以内」であり「後婚の成立の日から200日を経過した後」、という困った事態が生じ得ます。
子の嫡出推定が重なり、前婚と後婚の双方の父の嫡出子と推定されてしまう訳です。
この場合、民法773条は、裁判所がその子の父を定めると規定しています。
これを、父を定める訴えといいます。
この訴えに出訴期間の定めはありません。(何年経過しようが訴え可能)
認知
認知は、戸籍の届出によってします。(民法781条1項)
また、遺言によりすることができます。(民法781条2項)
民法は、遺言によりすることができることを厳格に定めます。
それは、遺言は、相続がらみの問題を生じるので、紛争を避けるために遺言の要式やその内容をきっちりと決めておく必要があるからです。
遺言による認知を認めた趣旨は、父である男の側に、生きている間は認知をしにくいという事情もあろうかという点を考慮してのことです。
認知は、戸籍に記載されますから、万一、愛人の子の存在が妻に知れたら「男は非常に困る」ことがあり得るのです。
そこで、妻に怒られる心配のない、死と同時の認知を制度化したのです。
認知により子は父を相続することができますから、子の福祉にも適うわけです。
成年の子の認知
成年の子は、その承諾がなければこれを認知することはできません(民法782条)。
これは、例えば、父が成人した子を認知する場合の規定です。
子はすでに成人しています。
したがって、父による扶養の必要はないと考えられます。
しかし、今後、父は老います。
したがって、認知により父子間に血族関係が生じると子の父への扶養義務が生じ得ます。
つまり、成人の子を認知するということは、父は自らは子の扶養をしなかったにもかかわらず、その老後の扶養を子に求めることになりかねません。
それはつまり、父の身勝手とも言えるので、認知をするために子の承諾がいるとされています。
死後の認知
続いて、次のような場合の認知はどうなるのでしょうか?
事例3
A男には婚姻外の子がいたが、幼少時に死亡した。
この事例3は、婚姻していない男女の間に生まれた幼い子供がいたが、まだ幼いうちにその子が死亡してしまった、という話です。
さて、ではA男は、子の死後に認知をすることができるのでしょうか?
結論。
認知をすることはできません。
子の死後においては、通常の場合、認知をすることはできないのです、
なぜなら、認知できたとしても、子が扶養を受けることもなく、子が父を相続することもありません。
つまり、子の死後に認知をすることができても、子にとって実益がないのです。
しかし、子にも子がいるケースは例外です。
例えば、A男に成人の子がいて、その子にも子(A男にとっての孫)がいるケースです。
この場合、父が子を認知することにより、父と孫が直系血族となります。
となると、孫は父に扶養を請求できますし、また孫が父を相続することもできます。
つまり、このケースなら、孫の福祉に適うから死後の子の認知が認められるのです。(民法783条2項)
しかし、先述の成人の子の場合と同様、孫が成人であれば、その者の承諾がなければ認知をすることはできません。
認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人であっても、その法定代理人の同意は要しません。(民法780条)
身分行為については、本人に意思能力があれば、その意思によるべきであり、第三者の同意はなじまないのが原則なのです。
色々な認知
認知の無効、認知の撤回、法定代理人の同意
ここから、さらに認知の様々なケースについて、事例とともに解説して参ります。
なお、Aが父、Bが子、という前提です。
事例4
第三者が父Aの名を語り認知届を出した。なお、父Aと子Bの間には真実の父子関係かある。
さて、この事例での認知は有効でしょうか?
結論。
この認知届は無効です。
認知は、法律上の父子関係を創設する意思表示と考えられますから、認知者本人の意思に基づかなければ無効です。
つまり、認知とは、単に父子であるという事実の申告ではなく、法律上の父子になろうという意思の申告なのです。
事例5
父Aが認知届を出した後死亡した。
さて、この事例で、父Aと子Bの間に父子関係がない場合、子Bは認知の無効を主張できるでしょうか?
結論。
認知の無効を主張できます。
届出上の父子間に実際の血縁関係が存在しないので、認知は無効なのです。
父の生前は父を被告として、父の死後は検察官を被告として、子Bは上記の無効主張をすることになります。
この事例5では、父は死亡しており、その代理人という存在はあり得ませんから、やむを得ず検察官が被告(無効主張する相手)となります。
参考条文
(認知に対する反対の事実の主張)
民法786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
事例6
父Aは認知届を出した。しかし、その後に気が変わった。
さて、この事例で、父Aは認知の撤回をすることはできるでしょうか?
結論。
一度した認知の撤回は不可能です。
認知をした父または母は、その認知を取り消すことができません。(民法785)
ここにいう取消しとは、撤回の意味であると解釈されています。
事例7
未成年の父Aは、子Bの認知をしようとした。
さて、この事例で、未成年の父Aは、子の認知をするために法定代理人の同意を要するでしょうか?
結論。
法定代理人の同意は要しません。
民法780条の規定「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない」により、父が未成年であっても、法定代理人の同意は要しません。
認知と子の氏
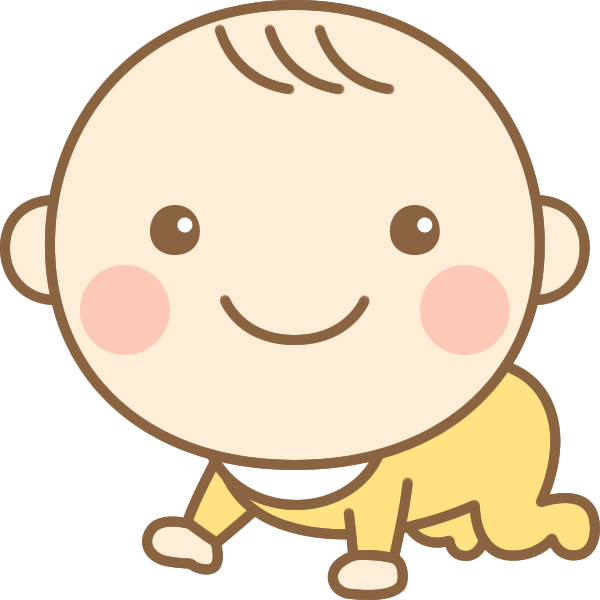
民法790条2項は、嫡出でない子は母の氏を称すると規定しています。
婚姻外の子は母の戸籍に入り、母と同じ氏を称します。
さて、ここで父が認知をするとどうなるのでしょうか?
どうにもなりません。
子の氏は、子に独立のものですから影響を受けないのです。
しかし、この場合は、子が父または母と氏を異にする場合に該当しますから、家庭裁判所の許可を得て、父の氏に変えることができます。(民法791条1項)
このケースでは、父母が婚姻中ではありませんから、家庭裁判所の許可は必須です。
また、父が子を認知しても親権者は母のままですが、父母の協議で父を親権者と定めたときは、父が親権者となります。(民法819条4項)
【補足】胎児の認知
父が胎児の認知をすることは可能です。
しかし、そのために母の承諾を要します。
常識的に考えても「お前のお腹の子は俺の子だ」という態度は、女性に対して失礼ですよね。
なので、母の承諾を要するのです。(民法783条1項)
婚姻外の認知
事例8
A男とB子が、内縁関係を始めて、200日経過後に娘Cが出生した。
さて、この事例で、娘CはA男の子と推定されるでしょうか?
まず、この問題は嫡出推定の話とは直接の関係はありません。
なぜなら、A男とB子が法律上の夫婦ではないので、嫡出子になるわけはないのです
しかし、この場合、判例は、娘CはA男の子であると事実上推定されるとしています。
すなわち、AC間に血の繋がりがあるかどうかが、裁判上の争点となったとき、事実上の問題として、娘CはA男の子と推定され、これを否定する場合、A男の側に親子ではないことの立証が求められることになります。
事例9
A男とB子の間に、婚姻外の娘Cがいる。しかし、A男は認知をしない。
さて、この事例で、娘CからA男に対して認知を強制することはできるでしょうか?
結論。
できます。
強制認知という方法が存在します。
民法の規定はこちらです。
(認知の訴え)
民法787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
上記、民法787条の規定により、この訴訟は、父が生存中であれば、いつでも提起することができます。
この場合、父子間に血縁関係が存在するかどうかが争点となります。
事例10
A男とB子の間に、婚姻外の娘Cがいる。その後、A男が死亡した。
さて、この事例で、娘CがA男の認知を求めることはできるでしょうか?
結論。
父または母の死亡後は、死亡の日から3年間に限り、認知の訴えを提起することができます。(民法787条ただし書)
この訴えの被告は検察官です。
民法上、死者の代理人は考えにくいからです。(代理は本人に権利義務を帰属させる制度です。死者には権利能力がないからその代理という仕組みは基本的に存在しません)
なお、訴えが可能な時期は、死亡後3年までであり、子が父の死亡の事実を知った時から3年ではありません。
【補足】
父の死後に強制認知をした非嫡出子の相続権
認知の効力は子の出生にさかのぼります。(民法784条)
したがって、死後に認知された場合でも、子は出生のときから父の子です。
つまり、父の死亡時にも子として存在したことになります。
なので、父の死後に強制認知をした非嫡出子には相続権が発生します。
非嫡出子の相続権と遺産分割
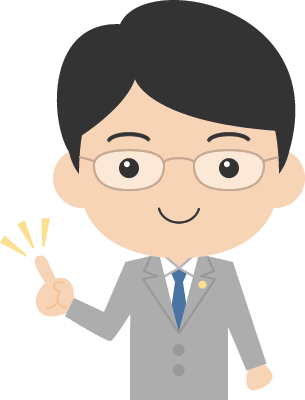
遺産分割とは、共同相続人が死者の遺産分けをすることをいいます。
あの土地は長男、株は次男、預貯金は三男という具合です。
遺産分割は、相続人全員でしなければその効力を発生しません。
なので、例えば、死者が生前に認知した非嫡出子の存在を知らずに(まさか故人に愛人の子がいるとは知らなかったケース)、他の共同相続人が遺産分割をしても、それは無効です。
しかし、相続の開始後、認知によって相続人となった者がいる場合、つまり、典型的には死後の強制認知の場合に、他の共同相続人が認知前にした遺産分割協議は無効とはなりません。(民法910条)
この場合には、認知された子は価額のみによる支払の請求額を有することになります。
すなわち、他の共同相続人の遺産分けは有効だが、認知された子の取り分はお金を渡すという形になるわけです。
【補足】胎児の権利能力
胎児は認知の訴えの提起はできません。
それは、認知の訴えの提訴権者が「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人」と規定されているから(民法787条)でもありますが、一般論として胎児には権利能力がないので、訴訟の場合に、訴状に原告胎児とは書けないからとも言えます。
なお、例外的に、次のケースでは、胎児の権利能力が認められています。
いずれも、生まれてくる子の財産を確保しようという趣旨の規定です。
・不法行為の損害賠償請求権(民法721条)胎児が加害者に損害賠償請求をすることができる。
・相続権(民法886条1項)胎児の相続権が認められます。
・受遺能力(民法965条)胎児に対する遺贈は有効である。
準正
準正は、非嫡出子が、嫡出子の身分を取得する仕組みです。
その要件は次の2つです。
・父母が婚姻すること
・父が子を認知すること
上記2つの要件がそろえば、例外なく、子は嫡出子の身分を取得します。
元々、婚姻中の父母の子であれば、嫡出子の身分を取得できますので、父母の婚姻、認知の2つの要件が時期をずらして満たされた場合でも、子が嫡出子となるという仕組みです。
婚姻によって準正が生じる場合、つまり、認知先行型を婚姻準正といいます。
(準正)
民法789条1項
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
認知によって準正が生じる場合、つまり、婚姻先行型を認知準正といいます。
(準正)
民法789条2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
この民法789条の条文が言っていることは極めて明快です。
1項の認知先行型、すなわち婚姻準正の場合は、婚姻により非嫡出子は嫡出子となります。
2項の婚姻先行型、すなわち認知準正の場合は、認知により非嫡出子は嫡出子となります。
では、どの場合に準正が生じ得るのか?いくつかのケースに分けて解説して参ります。
1・父が死亡した場合
これは、例えば、子の出生後に父母が婚姻し(この時点では父が子を認知していないから父と子の関係は姻族1親等であり法律上の親子関係は存在しない)、その後に父が死亡した場合です。
一例として、父の死後3年以内に子が認知の訴えを提起し、これが認められれば認知準正が生じます。
2・母が死亡した場合
準正が生じる事があり得ます。
例えば、子の出生後に父母が婚姻し、その後に母が死亡したとします。
その後、父が子を認知すれば準正が生じ、子は嫡出子の身分を取得します。
3・子が死亡した場合
準正が生じる事があり得ます。
例えば、子の出生後に父母が婚姻し、その後に子が死亡したが、その子にさらに子(父母から見れば孫)がいたため、父が死亡した子を認知することができたケースです。
〈参考条文〉
民法789条3項
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
というわけで、今回は以上になります。
宅建試験や行政書士試験や公務員試験などの民法の学習、独学、勉強、理解の助力としていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
- 関連記事
-
-
 【親族と親等】【血族と姻族とその違い】【相続と戸籍】【親子関係と戸籍の届出】【家族法と財政問題】をわかりやすく解説
【親族と親等】【血族と姻族とその違い】【相続と戸籍】【親子関係と戸籍の届出】【家族法と財政問題】をわかりやすく解説
-
 【婚姻】【届出意思と婚姻意思】【婚姻障害と婚姻の取消し】【婚姻の取消権者と取消期間】をわかりやすく解説!
【婚姻】【届出意思と婚姻意思】【婚姻障害と婚姻の取消し】【婚姻の取消権者と取消期間】をわかりやすく解説!
-
 【婚姻解消~離婚と死別】【子の氏】【協議離婚と裁判上の離婚】【有責配偶者からの離婚請求】をわかりやすく解説!
【婚姻解消~離婚と死別】【子の氏】【協議離婚と裁判上の離婚】【有責配偶者からの離婚請求】をわかりやすく解説!
-
 【財産分与と離婚と慰謝料】【財産分与と内縁】【損害賠償請求と財産分与請求】内縁の妻が相続財産を承継する方法とは?わかりやすく解説!
【財産分与と離婚と慰謝料】【財産分与と内縁】【損害賠償請求と財産分与請求】内縁の妻が相続財産を承継する方法とは?わかりやすく解説!
-
 【嫡出子と非嫡出子と認知】【嫡出推定】【準正】成年・死後・婚姻外の認知/無効と撤回/非嫡出子の相続権と遺産分割をわかりやすく解説!
【嫡出子と非嫡出子と認知】【嫡出推定】【準正】成年・死後・婚姻外の認知/無効と撤回/非嫡出子の相続権と遺産分割をわかりやすく解説!
-
 【養子縁組】【縁組障害】【縁組取消しと離縁】【請求権者とその期間】様々な縁組と離縁をわかりやすく解説!
【養子縁組】【縁組障害】【縁組取消しと離縁】【請求権者とその期間】様々な縁組と離縁をわかりやすく解説!
-
 【離縁】【死別と離縁と血族関係】【特別養子】【特別養子と離縁】【15歳未満の未成年者の離縁】をわかりやすく解説!
【離縁】【死別と離縁と血族関係】【特別養子】【特別養子と離縁】【15歳未満の未成年者の離縁】をわかりやすく解説!
-
 【親権】【親権の喪失・停止・回復】【利益相反行為】誰が親権者になるか?様々なケースでわかりやすく解説!
【親権】【親権の喪失・停止・回復】【利益相反行為】誰が親権者になるか?様々なケースでわかりやすく解説!
-
 【後見人】未成年後見と成年後見の違いとは?/解任と辞任/後見人になれる者とは?わかりやすく解説!
【後見人】未成年後見と成年後見の違いとは?/解任と辞任/後見人になれる者とは?わかりやすく解説!
-